世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
幸福度研究の意義は?
(青山学院大学経済学部 教授)
2016.06.27
毎年3月20日は国連が定めた国際幸福デーで,GDPやGNPへのアンチテーゼとして国民総幸福(GNH)を提唱してきたブータンの発案により実現した記念日だという。この日にあわせてWorld Happiness Report(世界幸福報告書)の2016年アップデート版が公表された。150ヵ国以上でそれぞれ約3000人のサンプルに対し,主観的な生活満足度(life evaluationといい,情緒レベルの幸福度と区別される)を0~10のスケールで評価してもらい,その平均値でランク付けをしている。その結果,幸福度1位はデンマーク(7.526),2位スイス(7.509),3位アイスランド(7.501),4位ノルウェー(7.498)など,欧州諸国が上位を占めている。日本は53位(5.921)と先進諸国のなかでは下位に位置し,アジアでもシンガポール(22位,6.739),タイ(33位,6.474),台湾(35位,6.379),さらにマレーシア(47位,6.005)の後塵を拝している。韓国は57位(5.835),中国は83位(5.245)となっている。ブータンが84位(5.196)と低迷しているのは皮肉な結果だ。
同報告書が2012年に最初に公表されて以来,北欧諸国が最上位にランクすること,所得水準に対して東アジア諸国は幸福度が低く,中南米諸国は高いことなど,地域別の大まかな傾向には変化がないようだ。つまり,主観的幸福度には歴史文化的な影響が無視できないことは明らかで,上記ランキングを額面通り受け取って一喜一憂するのは愚かだろう。一方,同報告書は主観的幸福度に影響を与えると考えられる「1人あたりGDP」,「社会的サポート」,「健康年齢寿命」,「人生における選択の自由」,「社会的寛容度」,「実感汚職度」といった説明変数の影響力を統計的に国際比較しており,この点は,国ごとの特性が見られて興味深い。
この報告書の伏線となったのが,サルコジ仏元大統領が諮問して24人の専門家が参加した通称「スティグリッツ委員会」が2009年に発表した報告だろう。同委員会は3つの分科会から成り,「暮らしの質」を議論する分科会において,既存の開発指標の長所・短所を比較検討したうえで,主観的幸福度の導入可能性が検討された。学術世界でもJournal of Happiness Studies が2000年,Journal of Happiness and Well-Beingが2013年に創刊されるなど,幸福度研究は専門学問領域としても認知されてきたようだ。日本でも2011年12月に若いブータン国王夫妻が訪日すると同時に,内閣府の幸福度研究会が日本の幸福感に基づく幸福度指標試案を公表した。
幸福度研究の意義はどこにあるのだろうか。第1に,数学的厳密さを要求する効用理論が立ち入らない領域で興味深い分析が可能かもしれない。第2に,生活満足度に影響を与える社会制度を特定できれば,比較制度分析として有益であろう。第3に,生活満足度が低い層を特定することでターゲッティング政策の立案に役立つかもしれない。例えば,非正規雇用者の生活満足度が個人の属性や所得の違いを排除したうえでも有意に低い,子供時代の虐待やネグレクトが成人以降の幸福感を引き下げる,といった実証結果は政策面でも有用であろう。
とはいえ,単一の幸福度指標を考案してランク付けしたり,その指標自体の向上を目指したりするのは無謀であろう。理論上は「アローの不可能性定理」が示すように,個人の好みを集計して首尾一貫した民主的な公共選択メカニズムをデザインすることはできない。倫理上も国家が個人の私的空間に介入すべきではないだろう。都道府県別幸福度ランキングといったエクササイズは理論上も倫理上も問題が多い。
最後に,前稿でも紹介したディートン(2013)の興味深い指摘を紹介する。購買力平価で調整した1人当たりGDPを横軸に,主観的な生活満足度スコアを縦軸にとって各国をプロットすると,前者が1万ドルあたりに達するまでは両変数間に強い相関関係があるが,そこを超えると,所得に応じた生活満足度の上昇が急激に小さくなる。これをもって「イースタリン・パラドックス」が示唆するような所得を源泉とする満足度の飽和点のようなものがあると考えるべきか。否,とディートンは解説する。横軸のスケールを「4倍数」表示(つまり,横軸目盛りが等間隔に1つ進むごとに250ドル,1000ドル,4000ドル,1万6000ドル,6万4000ドル)に変換すると,両変数間に一貫した正の相関が現れる。つまり,所得の限界効用が逓減するという仮定を採用すれば,少なくとも国際比較の文脈ではパラドックスは消える。世界全体で見れば,高所得国から低所得国へ所得移転をするのが幸福度上昇によさそうだ。1人当たり所得は開発指標としてまだ捨てたものではない。
J.S.ミルが語ったという“Ask yourself whether you are happy, and you cease to be so.” (幸せかどうか自分に聞けば幸せでなくなってしまう)という言葉で本稿を締めくくることにする。
関連記事
藤村 学
-
[No.4230 2026.02.23 ]
-
[No.4119 2025.12.08 ]
-
[No.3862 2025.06.09 ]
最新のコラム
-
New! [No.4245 2026.03.02 ]
-
New! [No.4244 2026.03.02 ]
-
New! [No.4243 2026.03.02 ]
-
New! [No.4242 2026.03.02 ]
-
New! [No.4241 2026.03.02 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
文眞堂 -
 アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済:最後のフロンティアの成長戦略
本体価格:3,200円+税 2019年12月
アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済:最後のフロンティアの成長戦略
本体価格:3,200円+税 2019年12月
文眞堂 -
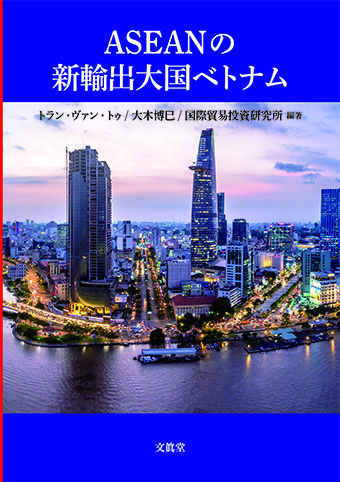 ASEANの新輸出大国ベトナム
本体価格:3,000円+税 2018年12月
ASEANの新輸出大国ベトナム
本体価格:3,000円+税 2018年12月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 貿易実務:新たな研究潮流
本体価格:3,500円+税 2026年1月
貿易実務:新たな研究潮流
本体価格:3,500円+税 2026年1月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂
