世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
学歴論争再訪:人的資本論 vs シグナリング理論
(青山学院大学経済学部 教授)
2017.04.24
日本の大学にとって受験前後のシーズンは「書き入れどき」である。さて,大学という職場で生計を立てる者の1人として,大学は社会にどんな貢献をなしているのだろうかと思う時である。一般に教育サービスは,その「消費財」の側面はさておき,その「投資財」としての社会的価値を正確に測るのは困難である。英エコノミスト誌の2015年3月28日号は “The world is going to university: more and more money is being spent on higher education, but too little is known about whether it is worth it.”と題して高等教育について特集した。それは,世界中で高学歴化が進み,大学は国際ランキングを競い,研究者も学生もブランド力のある大学・大学院を目指して競争する時代に入ったが,このように高等教育につぎ込まれる私的・公的資源の量はそれに見合う社会的価値をもたらしているのだろうか,という趣旨の問題提起であった。
OECDが毎年公表している“Education at a Glance”という資料の2012年版によれば,OECD諸国の大学進学率の平均値はすでに62%に達し,豪州やアイスランドは90%超,北欧諸国は70%超,韓国も68%となっている。日本は51%と先進諸国間では「中の下」に位置しており,1人当たりGDPに占める高等教育への公的支出の割合は,日本はOECD諸国の中で下から3番目に位置した。一方で,同2015年版によれば,高等教育への学生1人当たり公的支出額と時間当たり労働生産性の間に0.83という高い正の相関係数が得られたと報告している。これらの数字をもって,日本は高等教育に対する公的支出が過少であるとする議論が大学側(とくに私立大学)からはなされる。しかし,相関関係は因果関係ではなく,高等教育支出増加によって生産性が向上するのか,高い生産性によって経済が成長して財政が潤い,その結果高等教育支出が増えるのか,どちらなのかは言えない。
そこで「教育の経済学」分野におけるノーベル賞受賞学者の2つの対照的な理論を再訪してみる。
教育を投資財とみなす人的資本論を定式化したのはゲイリー・ベッカーの1962年の著作である。そこでは,教育は人的資本への投資と考えられ,知識や技能を身につけさせることで個人の生産性を高め,経済成長に貢献する。そこでは高卒者と大卒者の賃金差は大学教育を通じて蓄積された人的資本の差を反映すると考える。
一方,マイケル・スペンスの1974年の著作は,労働者と企業の間の情報非対称を前提とし,個人は労働市場に発するシグナルへの投資として進学する,というシグナリング理論を展開した。そこでは能力の高い者(俗な言い方で「高ジアタマ」グループとする)は学歴取得のためのコスト(お金と時間)が相対的に低く,「低ジアタマ」グループはそのコストが相対的に高いとする。高卒時点で両グループそれぞれが一定の割合で存在し,その関係は大学教育期間を通じて変化しないと仮定する。企業がこの仮定を共有する場合,ある水準以上のブランド学歴を持つ学生のほうが「統計的に」能力が高いと判断し,人事部は学歴シグナルを利用して効率的な採用を行う。そうした企業のカウンター・シグナルに対し,「高ジアタマ」グループは合理的にそのシグナルに投資するというフィードバックが起こる。受験勉強にはかなりの努力とコミットメントが要求されるので,財市場における「1年保証」というようなシグナル効果よりも,労働市場における学歴シグナル効果ははるかに高い。日本の大手企業のなかには大学1年生から内定を出す究極の学歴シグナル派も存在するようだ。
どちらの理論も高等教育を投資行為とみなすが,政策含意は正反対である。人的資本論に立てば,高等教育への公的支出は肯定されるが,純粋なシグナリング理論に立てばそれは否定され,「低ジアタマ」グループの高等教育を公的に支援することは労働市場の失敗を軽減しているシグナリング機能を阻害することになる。
学歴社会の根強さは決して日本の「ガラパゴス」現象ではなく,学歴シグナルの支配傾向はむしろグローバル化してきたと筆者は見ている。大学の国際ランキングの評価基準に関して異論は多いが,一度ランキングされてしまうとそれがグローバルな偏差値情報となり,これもシグナリング効果を発揮してしまうのではないだろうか。
日本の「教育の経済学」専門家の間では,人的資本論とシグナリング理論は相互排他的なものではなく,両者の要素が混在していて,具体的な政策提言は実証分析に基づかなければならないという解釈が主流のようである。しかし,人的資本論対シグナリング理論の「神学論争」を解消するような実証分析を,門外漢である筆者はまだ見かけない。この2つの理論とは別に「仕事競争モデル」というのがあるようで,これは企業が大卒者の能力水準をそもそも評価対象とせず,OJTの段階ごとに潜在能力が顕在化し,その顕在能力にしたがって報酬を上昇させていくという日本型の(欧米の「ジョブ」型に対する)メンバーシップ型雇用形態を良く説明するモデルであり,こちらについては実証研究が見られ,支持されているようだが,これがシグナリング理論の検証に結びつくわけではない。シグナリング理論の実証研究には,観測不可能な潜在的な訓練可能性(trainability)というようなものを反映する外生変数(回帰分析用語ではinstrumental variableといわれる)が必要と思われるが,その指標を特定するのがそもそも難しいのかもしれない。
その間,ごく大まかな政策判断材料を求めるとすれば,高等教育投資の便益費用比較が考えられる。大学教育の私的便益は大学進学によって個人が生涯にわたって得られる追加的期待賃金としてとらえられ,私的費用は大学進学費用(受験勉強の心理的ストレスも定量化できれば含めればよい)・学費・通学費用および失われた稼得賃金(機会費用)を合計する。一方,大学教育の「社会的便益」は,追加的な税収入に加え,経済成長や環境改善など,大学教育を受けた個人がその追加的生涯賃金以上に社会にプラスに貢献する「外部経済」効果を含む。「社会的費用」は私的費用に加え,財政から支出される補助金や奨学金の公的補助部分などを含む。外部経済効果を定量的に推計するのは困難なため,社会的便益費用分析は税収や補助金支出の財政効果を加えたものが現実的な限界となることが多い。
以上についてデータがある程度揃えば,追加的教育1年についての私的および社会的な「内部収益率」が計算できる。私的内部収益率が市場の利回りよりも高ければ,私的投資の「元が取れる」と判定され,社会的内部収益率がその国の「社会的割引率」(この概念の説明を割愛する)よりも高ければ公的投資が正当化される。
上記OECDの2016年版資料では加盟諸国のうちデータが揃う国について実際に内部収益率を推計している。2012年データに基づく高等教育(大学・大学院をあわせて)の私的内部収益率はOECD平均で男子14%,女子12%に対し,日本は男子8%(下から2番目),女子3%(最下位)であった。一方,社会的内部収益率はOECD平均で男子10%,女子8%に対し,日本は男子21%(第2位),女子28%(第1位)であった。これらから,日本の若者(とくに女子)にとって高等教育は高価な割にはその金銭的見返りが比較的小さい一方,社会にとっての見返りは大きいので,人的資本論の立場からは高等教育への公的支出を増やすべきだと解釈できる。ただし,これがシグナリング効果を否定する証拠とはならない。大学全入時代に入れば高等教育の「平均的な」シグナル効果は当然落ちるが,個別ブランドのシグナル効果は健在であり,むしろ高まるのではないかという見方も否定できない。
関連記事
藤村 学
-
[No.4230 2026.02.23 ]
-
[No.4119 2025.12.08 ]
-
[No.3862 2025.06.09 ]
最新のコラム
-
New! [No.4257 2026.03.09 ]
-
New! [No.4256 2026.03.09 ]
-
New! [No.4255 2026.03.09 ]
-
New! [No.4254 2026.03.09 ]
-
New! [No.4253 2026.03.09 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
文眞堂 -
 アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済:最後のフロンティアの成長戦略
本体価格:3,200円+税 2019年12月
アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済:最後のフロンティアの成長戦略
本体価格:3,200円+税 2019年12月
文眞堂 -
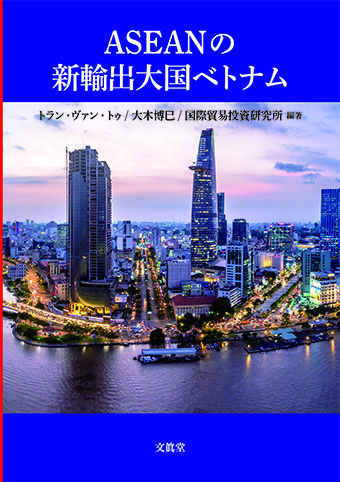 ASEANの新輸出大国ベトナム
本体価格:3,000円+税 2018年12月
ASEANの新輸出大国ベトナム
本体価格:3,000円+税 2018年12月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 詳説 国際人的資源管理:多国籍企業の人材マネジメントの理論的・実証的研究
本体価格:4,500円+税 2026年1月
詳説 国際人的資源管理:多国籍企業の人材マネジメントの理論的・実証的研究
本体価格:4,500円+税 2026年1月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
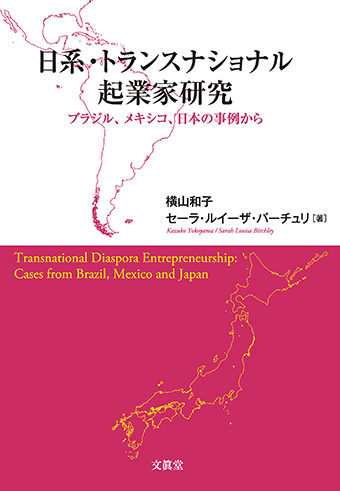 日系・トランスナショナル起業家研究:ブラジル、メキシコ、日本の事例から
本体価格:2,600円+税 2026年2月
日系・トランスナショナル起業家研究:ブラジル、メキシコ、日本の事例から
本体価格:2,600円+税 2026年2月
文眞堂
