世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
日本企業の国際経営の新たな地平を拓く
(桜美林大学 教授)
2016.02.01
日本企業の国際経営は,新たなステージに入っている。日本企業の国際展開は1970年代初期からスタートし,85年のプラザ合意を契機に本格化,さらには90年代半ばから中国をはじめとする新興国市場へと,その範囲を拡大してきた。この間,その重点課題も販売,生産,調達,R&Dの海外移転へと順次シフトしてきた。この結果,大企業の場合,今ではグローバルなネットワークを構築して経営を展開するようになっている。一方,日本の国内市場が少子・高齢化により急速に縮小する中,かつてドメスティック産業の典型で海外展開が難しいと考えられていたサービス業も,急ピッチで海外進出を行っている。
このような状況のもと,日本企業の国際経営や競争優位の構築の方法について,パラダイムシフトが求められている。これまでの日本企業は,製造業の場合,高品質の製品を製造する生産技術や生産システムなど,いわゆる「日本的な強み」を海外拠点に移転するという方法で競争優位を構築してきた。最近ではサービス業の海外展開でも,「おもてなし」など,サービスの日本的な強みを競争優位とみなし,その海外移転が試みられている。
確かに,このような方法での国際経営の展開や競争優位の構築は,海外進出の初期の段階や一定の期間までは有効であろうが,進出先国が経済・社会の発展を遂げ,その子会社や人々も多くの資源や能力を蓄積するようになると,その優位性を失うことになる。近年の製造業についてみると,ITの飛躍的な発達によって,もの造りの方法が一変し,日本のエレクトロニクスメーカーは韓国,台湾,中国などの企業のキャッチアップにあい,急速に競争力を失ったケースはそれを如実に物語っている。
また,近年のグローバル競争も,かつてのそれとは異質なものになってきている。従来の企業間競争は既存の同一産業内における競争だったが,近年のそれは異業種間の企業同士の競争,さらには未来に向けての市場創造の競争に変わってきている。
このような事情を考えると,まず日本企業は海外子会社のイニシアチブを尊重し,その経営資源や能力をフルに活用する経営に着手する必要がある。海外子会社は年数が経つにつれて,その経営資源や能力を蓄積させる。これは現地の子会社経営にとってのみならず,企業グループ全体のグローバル経営にとっても大きな財産である。これらの子会社の経営資源や能力の活用から,子会社発のイノベーションが期待される。GEの中国子会社の超音波診断装置の開発,ネスレ日本のインスタントのアイスコーヒーやコーヒー機の貸与サービスのビジネスは,そのような事例である。まさしく,リバース・イノベーションである。
次に,日本企業は外国企業など,多様なステーク・ホルダーとの協創の経営へと向かうことも重要である。外国企業などとの協創は,一般に提携を通じるケースが多いが,国際提携の場合は,かつてパートナー同士が双方の不足する経営資源を補完するケースが多かった。しかし,国際提携を進化させ,企業の価値創造へとつなげるにはパートナー同士が学習し,協創する必要がある。外国の企業や人々には,日本人にはない優れたアイデア,知識,能力などがある場合も少なくない。こうした経営資源や能力を活用しない手はない。事実,国際提携を通じて新しい製品や技術を開発した企業は少なくない。
加えて,今日の製造業ではビジネス・エコシステムが形成され,多くの企業が協創的な行動をとっている。さらに,新興国市場で貧困層を対象にしたBOPビジネスを展開する場合には,ユニリーバのインド子会社による下痢性疾患の撲滅の事例をはじめ,多くの事例が示すように,企業と政府機関,国際機関,社会起業家などとの協創が不可欠である。
このように,これからの日本企業の国際経営には日本的な強みを海外に移転するのみならず,海外子会社,外国企業,その他多くのステーク・ホルダーとの協創がきわめて重要になる。そのような経営でなければ,今世紀のグローバル時代に存在する難問に立ち向かい,企業や地球社会に求められる新たな価値創造はできない。ここに日本企業の国際経営の新たな地平が拡がっている。そのためには,外部環境の情報や知識の変化をいち早く察知し,それを組織のメンバーに伝達・共有して,新たな価値創造へと導く「バウンダリー・スパナー」のような人材が必要となる。日本でグローバル人材の育成が話題になって久しいが,日本企業にはまた,このような人材の育成こそが求められている。
関連記事
桑名義晴
-
[No.2903 2023.04.03 ]
-
[No.2588 2022.07.04 ]
-
[No.2443 2022.03.07 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
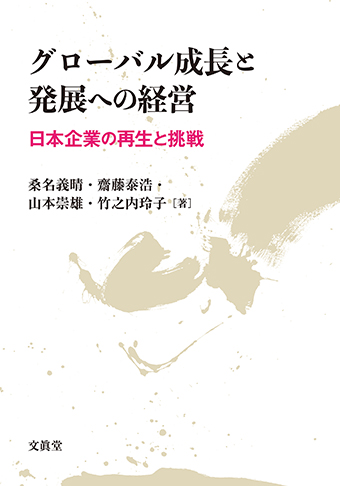 グローバル成長と発展への経営:日本企業の再生と挑戦
本体価格:2,800円+税 2022年5月
グローバル成長と発展への経営:日本企業の再生と挑戦
本体価格:2,800円+税 2022年5月
文眞堂 -
 パーソナルファイナンス研究の新しい地平
本体価格:4,200円+税 2017年11月
パーソナルファイナンス研究の新しい地平
本体価格:4,200円+税 2017年11月
文眞堂 -
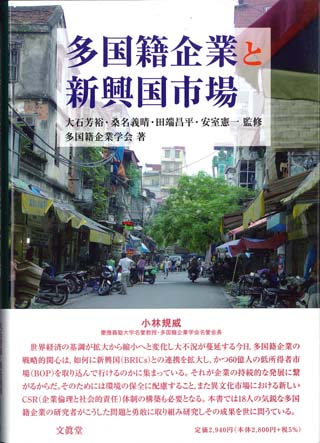 多国籍企業と新興国市場
本体価格:2,800円+税 2012年10月
多国籍企業と新興国市場
本体価格:2,800円+税 2012年10月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂
