世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
米国「相互関税」ショック:自由貿易体制を守る日本とASEANの責務
(国士舘大学政経学部 教授・泰日工業大学 客員教授)
2025.04.07
2025年4月,トランプ米政権が180カ国を対象に前例のない大規模な「相互関税」措置の発動を発表,世界の自由貿易体制に深刻な衝撃を与えた。この全方位的な関税引き上げに世界の市場は動揺し,欧州連合(EU)や中国も猛反発して対抗関税を示唆するなど,貿易戦争への懸念が現実味を帯びている。米国が掲げる論理は「経済的安全保障」だが,関税乱発の手法は戦後築かれた自由貿易秩序に逆行している。
今回の相互関税政策はWTO(世界貿易機関)の基本原則にも明らかに反する。最恵国待遇(加盟国を平等に扱う原則)から見ても,国ごとに関税率を変えるのは明白な違反だ。各国がWTOで約束した上限(関税拘束)を超えて課税すれば協定違反となる。米国はGATT第21条(安全保障例外)を盾に取るかもしれないが,貿易赤字を理由に世界的な関税引き上げを正当化するのは同条の趣旨を逸脱した濫用である。トランプ氏の第1期政権下での鉄鋼関税も国家安保を名目としたが,WTOでも容認されないと判断された。もし大国がこのような理屈で自国本位の策を押し通せば,他国も追随し,多角的な貿易ルールが空洞化しかねない。
自由貿易体制の恩恵を享受してきた日本にとって,これは看過できない事態だ。戦後,日本は開かれた市場と国際ルールの下で成長してきた。さらに日本は「法の支配」を重視し,国際秩序の擁護者を自任してきた。それにもかかわらず,今回の米国強硬策に日本政府が静観したり,自国だけの除外を求めたりするにとどまれば,日本の国際的信頼を損ねよう。普段「自由で開かれた経済秩序を守る」と唱える日本が,同盟国の圧力に及び腰では,「自国の利益しか考えないのか」と周辺国に失望されかねない。
今回の相互関税は日本の隣接地域であるASEAN諸国にも大きな打撃を与える。東南アジアの多くの途上国が対象となっており,中でもカンボジアやラオスなど経済基盤の脆弱な国々は特に高率の関税を課せられた。これらの国々は米国市場への輸出に依存しており,高関税は現地の雇用や産業を直撃しかねない。ASEAN全体でも自由貿易に支えられてきた国が多く,今回の措置に対する不安と不満が広がっている。日本まで米国に追随するように沈黙すれば,アジアの隣人たちは孤立感を深めるだろう。
ルールに基づく多角的貿易体制を守るため,日本とASEANは連携して行動すべきだ。第一に,WTOの場で協力し,今回の措置が協定違反であることを国際社会に訴えることである。米国がWTOの紛争解決を拒んでも,日ASEANなど有志国が結束して法の支配を守る姿勢を示す意義は大きい。
第二に,地域主導の自由貿易枠組みを一層強化したい。日本は米国が2017年に環太平洋経済パートナーシップ協定(TPP)から離脱した際も残る参加国をまとめ,環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)として発効に漕ぎつけた経緯がある。現在,CPTPPには英国の新規加盟が決まり,自由貿易圏は拡大しつつある。今あるCPTPPやASEAN主導の地域的な包括的経済連携(RCEP)などの協定を着実に拡充し,域内の自由貿易圏を盤石に固めることが重要だ。こうした枠組みにより,一部の大国が保護主義に傾こうとも,地域として自由貿易の旗を掲げ続けることができる。
幸い,ASEAN諸国の世論調査では日本への信頼感が厚い。先頃発表されたシンガポールのユソフ・イシャク研究所の「東南アジアの現状2025年版」で,日本は主要国の中で最も「世界の平和,安全,繁栄,統治への貢献するため『正しいことをする』国」と評価されており,その信頼に応える責任がある。対米遠慮のあまり声を上げられないようでは,信頼もリーダーシップも得られまい。米国の論理に安易に同調せず,培ってきた自由貿易の原則を堅持することこそ日本の取るべき道だ。無論,同盟国への直接的な批判には慎重さが要るが,建設的な対話と粘り強い外交によって米国にも多国間体制の重要性を説いていくことが不可欠である。
パンデミックからの回復途上にある世界経済で,貿易ルールが揺らぐ現状は憂慮すべきだ。日本が今,本気で自由貿易体制の擁護に取り組むことは,自国の繁栄のみならず,地域・世界の安定への投資でもある。日本が主体的に動けば,地域の信頼を高め,通商秩序づくりで主導的役割を果たす契機ともなろう。日本とASEANが協調して行動すれば,国際社会に「法の支配」と開かれた経済秩序を改めて示し,新たな保護主義の波に歯止めをかけられるだろう。
関連記事
助川成也
-
[No.4076 2025.11.10 ]
-
[No.4041 2025.10.20 ]
-
[No.4024 2025.10.06 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
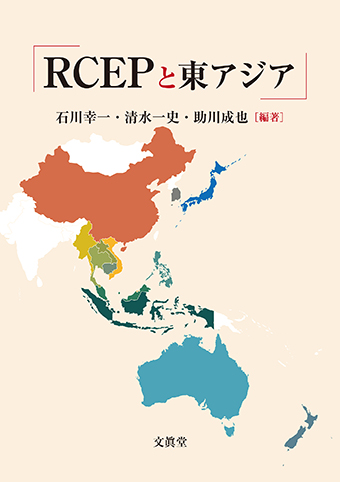 RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
文眞堂 -
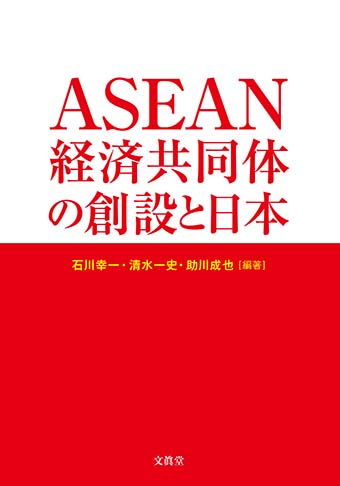 ASEAN経済共同体の創設と日本
本体価格:2,800円+税 2016年11月
ASEAN経済共同体の創設と日本
本体価格:2,800円+税 2016年11月
文眞堂 -
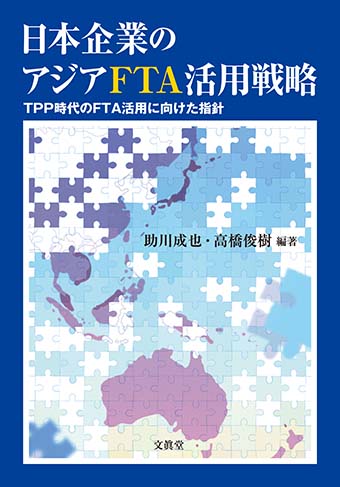 日本企業のアジアFTA活用戦略:TPP時代のFTA活用に向けた指針
本体価格:2,400円+税 2016年2月
日本企業のアジアFTA活用戦略:TPP時代のFTA活用に向けた指針
本体価格:2,400円+税 2016年2月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂

