世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
「中国の21世紀」再論
(兵庫県立大学 名誉教授)
2022.09.19
25年ぶりに,天児慧編著『中国の21世紀』(東洋経済新報社,1997年)を読んでみた。本書は,天児氏を中心に10名の中国専門家が自由闊達に発言するシンポジウム形式である。このシンポジウムは香港の中国返還の前年に行われた(注1)。今日の視点から見ると,本書は驚くべき正確さで「未来の中国」を予想している。ただし,誰も中国の経済規模が日本の2.5倍に成長するとは思わなかっただろうが。
しかし本書では,重大な1点を見逃していた(殆どの中国関連の研究も同様)。それは「人口動態」の変化である。
人口動態の変化は,その国の体制に関わらず進行する。資本主義国も社会主義国でも少子化や高齢化は刻々と進む。その国が将来どのような姿になるか予測するのは,「人口動態」を見ればわかる。「少子高齢化」が最も進んだ日本の経験を尺度にすれば,おおよその予測が可能になる。日本の高度成長は1970-80年代,バブル崩壊は1991年頃,それが浸透したのが1994-95年であろう。2000年に入ってからは経済の成熟化により低成長が続く。
中国も2015-16年頃までは経済成長が著しかった。しかし,それを過ぎると,経済は急速に低迷し始めた。日本の1990年代によく似てきた。つまり,中国は日本より25~30年ほど遅れて「成長の限界」に近づいたと言える。天児編著の『中国の21世紀』は,1979年の中国の「一人っ子政策」の法定化が40年後に何をもたらすかを予測できなかった。中国の「少子高齢化」は,日本よりも深刻な事態を招くことはほぼ確実である。
少子化は若者が成人になったときの住宅事情にマイナスの影響をもたらす。不動産の高騰のため若者は住宅が買えない。さらに一戸あたり価格は高騰するが,住居用ビルの需要は減少する。いずれかの時点で,住宅バブルが崩壊する。住宅やマンションに投資してきた人々が,莫大な評価損を被るだろう。これが波及すると,大規模な金融危機が発生する。
このバブル崩壊による社会の大混乱は,共産党政府が社会・経済の隅々まで支配してきた中国の国家体制を根底から揺るがす。中国政府は早めに対策を講じておかなければならない。2019年以降3年にわたって「COVID19」が猛威を振るった。武漢市の全面封鎖は徹底したコロナ対策によって国民の健康を守る作戦だった。ところがその後の「都市封鎖」は,少数のコロナ患者が発見されただけで断行された。2022年9月現在,33箇所の都市部で封鎖が行われているという。これは明らかに初期の目的を逸脱している。習近平氏の異例の総書記3期目入が有力視されるなか,9000万人余の共産党員が,13億人の国民(非共産党員)を監視・抑圧するように見える。習近平体制は,中国の経済発展よりも社会・政治体制の安定を優先している。台湾紛争を有利に進めるためにも,国内の結束を固め,社会の無用な混乱を避けたい。そこで「コロナ対策」に名を借りて国民監視・統制を強化しているのだろう。
中国に降りかかる課題は国内問題だけではない。「一帯一路」政策のツケが回ってくる。中国は高度成長期に,不足する資源・エネルギーを調達するために,発展途上国に対して惜しみなく借款や直接投資を行った。ただし,中国の対外援助はOECD諸国とは異なる方法で行われた。経済支援を掛け声に,中国政府高官が開発途上国の独裁者に大規模計画を提案する。中国船が寄港する港湾開発や鉄道建設,鉱山開発,高速道路や橋梁,ダムなどの電源開発である。中国の特徴は,大規模な工事に際し,中国の建設会社を起用し,中国人のエンジニアや工事関係の労働者を引き連れて行くことである。現地国での雇用は単純労働や補助職に限られる。中国人に対する給与支払いは現地通貨ではなく,中国本国の銀行口座に人民元で支払われる。現場での工事は短期間で終わるが,その国に産業集積をほぼ残さない。この結果,現地国には中国政府からの莫大な借金が残るが,期待したほどの経済効果や個人所得の増加は得られない。この仕組は,現地国の政治家や経済官僚の汚職を蔓延させるだけでなく,返済不能な多額な借金を膨らませる。独裁者が失脚しても,国の借金はそのまま残る。途上国が次々とデフォルト(返済不能)に陥れば,中国政府は金銭以外の代償を要求する。これは「隠れた植民地化」とみなされ,国際的な批判の的になる。
国内(コロナ騒動)・海外(一帯一路)で行き詰まった中国は,活路を「台湾攻勢」に見出そうとする。しかし,これは致命的なミスになる。アメリカはともかく,日本や韓国と敵対する。中国経済の成長に欠かせない直接投資や技術の源泉を失う。
台湾攻勢に没頭していると,インドの台頭を見逃してしまう。IT産業,ソフトウエアやAI・ロボットで追いつかれるだけでなく,インドは欧米日・オーストラリアなどと手を組んで,製造業を強化してくるだろう。インドの人口動態は中国に比較してずっと若い。成長の余地は非常に大きい。油断をしていると,21世紀の中庸には,経済規模で追い越されてしまうかもしれない。台湾問題やロシアーウクライナ戦争に気を取られて,インドの台頭に目が届かないと,思わぬ落とし穴に陥るだろう。
[注]
- (1)筆者も1997年の香港返還がどのように進むのか大変興味があった。前年の1996年に交換教授として広州の大学に赴任し,中国サイドから香港返還のプロセスを観察することにした。当時の広州市はまだ経済発展中の田舎町で,香港は憧れの都だった。結局,何の事件も起こらず,がっかりした。当時の中国の実力(経済・軍事等)はその程度しかなかった。
関連記事
安室憲一
-
[No.4102 2025.12.01 ]
-
[No.3863 2025.06.09 ]
-
[No.3741 2025.03.03 ]
最新のコラム
-
New! [No.4219 2026.02.16 ]
-
New! [No.4218 2026.02.16 ]
-
New! [No.4217 2026.02.16 ]
-
New! [No.4216 2026.02.16 ]
-
New! [No.4215 2026.02.16 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
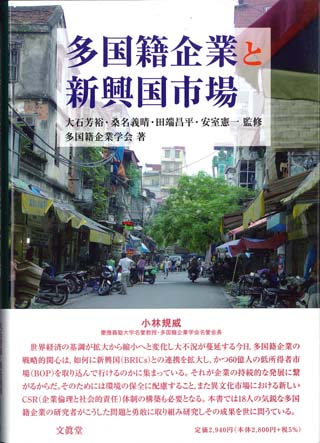 多国籍企業と新興国市場
本体価格:2,800円+税 2012年10月
多国籍企業と新興国市場
本体価格:2,800円+税 2012年10月
文眞堂 -
 ケースブック ビジネスモデル・シンキング
本体価格:2,700円+税 2007年4月
ケースブック ビジネスモデル・シンキング
本体価格:2,700円+税 2007年4月
文眞堂 -
 多国籍企業文化
本体価格:2,300円+税 1994年1月
多国籍企業文化
本体価格:2,300円+税 1994年1月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂
