世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
中国製AI「ディープシーク」は福音か災厄か?
(兵庫県立大学・大阪商業大学 名誉教授)
2025.03.03
中国の新興企業ディープシーク(注1)がAIの「ディープシークR1言語モデル」と画像処理・生成のための「ビジョンベースAI」(Janis Pro 7B)を相次いで発表した。創業者の梁文峰氏によれば,ディープシークの初期モデルV3の開発費は560万ドル(約8億7000万円)。これはChatGPTの開発費の100分の1に過ぎない。オープンAIの最新版「ChatGPT-4 o1」はNVIDIAの最高レベル半導体「H100」を数万個使用しているが,ディープシークは,アメリカの対中半導体輸出規制のために,NVIDIAが中国向けに開発した性能の劣る「H800」を2048個使って開発したという。チップの取得方法などに複雑な経緯があるようだが,報道内容はほぼ間違いないようだ。
しかも,ディープシークは無料公開するだけでなく,オープンソース化したという。つまり「AIのリナックス版」の登場である。ディープシークのソースコードが無料公開されれば,米国のビックテックの「課金モデル」は吹き飛ぶだろう。NVIDIAの株価が一時17%も下落する大ショックがアメリカを襲った。ディープシークのユーザー数は公開から1週間で1億人に達したという(現在4億人)。本来,非営利組織の「オープンAI Inc.」は「AIのリナックス化」を率先して行うべきであった。なぜ中国企業に先を越されたのか。
ディープシークの梁氏はベンチャー精神を発揮して,不利な条件を克服する新技術を開発した。その方法の一つが「知識の蒸留」(knowledge distillation)である。大規模なAIモデル(LLM)を教師とし,厳選した質問を繰り返し発して知識を引き出し,自分の知識ベースを作る。大規模なLLMの開発には約280万時間の事前学習が必要とされ,かつ膨大な費用が必要だ。大先生(LLM)はそれだけの時間と費用をかけて勉強したわけだ。生徒は先生にいろいろ質問して,短期間に要点を習得する。それに独自の知識を組み合わせて先生に劣らない知識体系を作る。つまり,人間はこうして先輩から学んで成長してきたわけだ。この理屈をうまく活用したのが「知識蒸留」だ。しかし,オープンAIの利用規約は「知識蒸留」を禁じている。ディープシークはそうした制約のないMeta(メタはオープン路線を採っている)の知識ベースを利用したのかもしれない。「ディープシークはオープンAIのコピーだ」,「知的財産権を侵害している」と非難する人々がいるが,それはおかしい。「知識蒸留」は学習行動の本質である。さらに,ディープシークは「混合エキスパート」(mixture of experts)という方法を採っている。なんでも知っている大先生にかなわない生徒たちは,それぞれ得意分野,例えば「僕は数学,君は科学,貴方は医学・・」というように専門に分かれて質問に答える。クラス全員が協力すれば,大先生にかなわなくても,「いい線」まで行ける。この方式なら,出来のいい学生たち(性能の劣ったチップ)をうまく組織すれば短期で結果を出せる。
ChatGPTにも問題がある。その学習データは世界中のインターネット情報や新聞雑誌などの記事,各種書籍や論文,アニメや写真・画像など様々な情報から構成されているが,情報の持ち主から許諾を受けることも,著作権料を払うことも,プライバシーの保護もせず,「タダで」使っている。これが許されるのは,学術論文が引用個所を明示すれば,著作権料を支払うことなく作成・公表できることと同じ理屈である(公益性の原則)。ただし,その作品が営利を目的とするなら,引用した情報に対して「使用料」を払う義務があるだろう。もちろん,引用を明記しない場合は盗作にあたる。しかも文字データの総数は有限なのである。
したがって,理屈の上では,オープンAIの最初のバージョンは「無料」でなければならない。それ以降のバージョンは,「無料」版を「知識蒸留」して性能を向上し,「有料」(ChatGPT-4 o1は月200ドル)という戦略がとられる。「有料化」を急ぐのは,LLM開発にかかる費用が天文学的な金額に達し,資金提供者が不安になったからであろう。マイクロソフトに資金提供を受けているサム・アルトマン氏は収益化を急がざるを得ない。この結果,非営利の「オープンAI Inc.」とその下にある営利組織の「オープンAI グローバルLLC」が意見対立を起こし,公益派の理事会メンバーのサッキバー氏と営利派CEOのアルトマン氏が激突,アルトマン氏が解任されるという事態が起きた。その後復帰したアルトマン氏はサッキバー一派を追い出し,オープンAIの営利化に舵を切った。この後ろ盾になったのが,マイクロソフトのCEOサティア・ナデラ氏であることは周知のとおりである。営利化に反対するイーロン・マスク氏が買収提案をぶち上げるという茶番(オープンAI Inc.は非上場なので買収はできない)にまで発展している(注2)。つまり,公益を採るなら「無料・オープンリソース化」,営利を採るなら「有料・クローズド化」である。ピックテックはもちろん営利派である。ただし,「有料」(課金モデル)には無断で利用したデータの「著作権問題」がつきまとう。ディープシークの「オープンソース化」はこのごたごたを吹き飛ばした。ディープシークは資金に行き詰っても最後には中国政府が付いている。AIの課金モデルが困難になると,ビックテックはどうやって投下資本を回収するのか。ビジネスモデルの再検討が避けられない。
ここまでの話なら「ディープシークは素晴らしい」「中国のAI,万歳」「やったね!」となるだろう(注3)。中国贔屓でなくてもディープシークの偉業を称えたくなる。だが,しかしである。話はこれで終わらない。
ディープシークのソースコードを改良し,自社のデータベースに繋げて「クローズド化」する企業が,特に中国を中心に,続出することが予想される。SIerは「それでいいじゃないか」「ビジネスチャンスが増える」と思うかもしれない。だが,それだけでは済まない。
筆者は,1990年代から中国経済を観察してきた経験から,今日の中国経済の不況が「不動産バブル崩壊」だけではないと考えている。それは,極めて高い失業率,とくに大卒などの若年層の失業率が非常に高い原因が,不動産とは関係のない分野で起きているからである。筆者は,中国の不況は「21世紀のテクノ大失業の始まり」と観ている。
中国では,インターネットやスマートフォンの普及のタイミングで「COVIT-19のパンデミック」による都市封鎖が起こった。外出できない市民の間で,ネットショッピングやデリバリー・サービスが急速に普及した。この結果,どこも同じような店舗のショッピングセンターや高級モールが相次いで倒産した。シャッターを下ろした無数の店舗に見るように,サービス産業の雇用は激減した。時を同じくして製造工場の自動化,工作ロボットの普及が進んだ。シャオミの最新鋭電気自動車(EV)工場は自動化率が91%であるという(注4)。このスパーファクトリーの関係者は「多くの作業場では作業員は数百人しかいない」と話している。工場の急激な自動化・ロボット化がブルーカラーの失業をもたらした。
さらに今,オフィスのAI化が進もうとしている。AIの導入によって失われる確率の高い仕事は,税務関係の資料作成,データ入力,経理事務,法律事務補助,スケジュール調整,文書作成・校正,コピーライター,カスタマーサービス,各種マーケティング業務,SNSマネジャー,翻訳,ITサポート,市場アナリスト,旅行代理店スタッフなど,事務仕事のほとんどをカバーする(注5)。定型ジョブに近い管理職の仕事もAIで代替可能であろう。このようにAIはオフィスのほとんどの仕事を代替する。3年もしないうちに大企業のオフィスから人影が消えるだろう。AIは膨大な数のホワイトカラー失業をもたらす。しかも,実務経験のない新卒者は最初から排除される。就職する前の段階でAIに代替されてしまう。人間はトレーニング・コストがかかるからである。この結果,技能を習得すべき人生の若い段階で戦線から脱落して貧困化する。この悲劇の引き金を引くのがディープシークであろう。
この結果,職場単位の生産性(一人当)は飛躍的に増加する。他方,膨大な数の失業者によって経済は著しく衰退する。一部の特権階級は豊かになっても,国民の大多数がギグ・エコノミーで暮らすことになる。つまり,生産性で「勝」っても,経済の持続的成長では「負け」になる。技術革新イコール経済成長ではない。その因果関係の連鎖の中に「人間尊重の(インクルーシブな)雇用政策」がなければならない(注6)。
つまりこういうことだ。技術革新は既存の経済秩序を破壊する。その結果,必要な技能の不足と今や不要になった職業が大量に発生する。そこで必要なのが,企業内での配置転換とそれに伴うリスキリングの教育投資である。企業内で足りないのなら外部の諸機関,職業訓練学校や大学のMBAコースが必要になる。そのための補助金や授業料免除も必要だろう。能力・資格を身に着ければ,転職もスムースになる。なんの教育訓練もなく解雇されれば,もはや有効でない職種の労働者は底辺に落ちていく。失業者が増えれば経済は衰退していく。これを防ぐのは,従業員を大切に思う経営者(人的資源管理),雇用を守る労働組合の抵抗力,国のリスキリング支援である。この雇用の防波堤を失うと,中国のように「生産性では勝ったが,持続的な経済成長では負ける」という状態に陥る。日本は少子高齢化による労働力不足の速度に合わせて情報化を推進し,(外国人労働者に頼ることなく)雇用総数を維持しつつ,緩やかな経済成長を目指すべきだろう。「急がば回れ」「負けるが勝」の,「社会格差を拡大しない」「情報技術革新を柔軟に受けとめる」社会政策が必要だ。
繰り返すが,技術革新が即,経済成長に繋がるのではない。雇用を守るインクルーシブな社会政策があって初めて,経済成長が実現する。雇用は自己実現の場であり,仕事は人生そのものでもある。これを守って初めて社会の安定がある。ディープシークは確かに素晴らしい。だが,それがもたらす福音が災厄に転化しないよう,思慮深い社会政策が必要だ。
[注]
- (1)DeepSeek(深度求索)は2023年に梁文峰によって創業された中国のベンチャー企業。
- (2)「マスク氏,独走阻止に固執」日本経済新聞 2025年2月12日(水)朝刊
- (3)ビビアン・トー「AI独占砕くディープシーク」日本経済新聞 2025年2月15日(土)朝刊
- (4)中央日報/日本語版(2024.04.03.07:46)
- (5)CNET Japan 2025年2月10日付
- (6)ダロン・アセモグル,サイモン・ジョンソン著,鬼澤忍,塩原通緒訳,『技術革新と不平等の1000年史(上)(下)』早川書房,2023年。特に下巻。
関連記事
安室憲一
-
[No.4102 2025.12.01 ]
-
[No.3863 2025.06.09 ]
-
[No.3637 2024.12.02 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
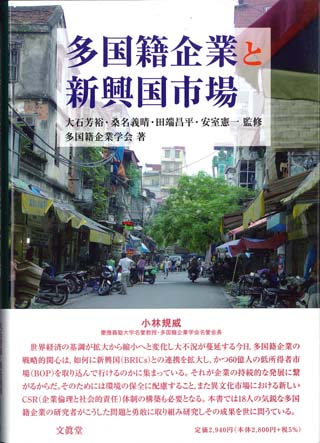 多国籍企業と新興国市場
本体価格:2,800円+税 2012年10月
多国籍企業と新興国市場
本体価格:2,800円+税 2012年10月
文眞堂 -
 ケースブック ビジネスモデル・シンキング
本体価格:2,700円+税 2007年4月
ケースブック ビジネスモデル・シンキング
本体価格:2,700円+税 2007年4月
文眞堂 -
 多国籍企業文化
本体価格:2,300円+税 1994年1月
多国籍企業文化
本体価格:2,300円+税 1994年1月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂

