世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
停戦合意後のカンボジア・タイと国際社会
(元亜細亜大学アジア研究所 特別研究員)
2025.08.18
2025年8月7日,マレーシアで開催された一般国境委員会(GBC)臨時会合では,カンボジアとタイの停戦に関し13項目が合意された。その第10項では,「両国は,停戦,及び,その実施の検証と確保のために,マレーシアに主導された『ASEAN監視団(ASEAN observer team:AOT)』の設立を含む,2025年7月28日の特別会合で達成された共通理解にコミットし続ける」となっているが,AOTの設立には若干時間を要するらしい。そこで,第12項は,「2025年7月28日に両国によって合意されたマレーシア主導のAOTが設立されるまでの間,タイ及びカンボジアに駐在するASEAN加盟国の武官で構成され,マレーシアの武官が主導する『暫定監視団(Interim Observer Team:IOT)』が,定期的に停戦の実施を監視するため,カンボジアとタイに分かれて設置される。各国のIOTの構成員は,マレーシアと協議し,当該国が独自に勧誘する。IOTは国境を越えることなく活動し,各国のGBCと地域国境委員会(RBC)と密接な調整や協議に基づいて活動する」となっている。この監視団の特殊な構成は,国際社会の関与を抑制したいタイの要請を受けてのものだと思われる。両国は1か月以内に次期GBC会合を開催することで合意した(Joint Press Statement Extraordinary General Border Committee (GBC) Meeting, 7 August 2025.)。
ASEANにとって,今回の仲介は,以下2点において貴重な経験となった。第1に,ASEANはこれまで加盟国間の紛争仲介の経験がほとんどなかった。第2に,域外国であるアメリカと中国が仲介役として重要な役割を果たした。その上で,ASEANの政治・安全保障機能の関係者・研究者にとって,今回の出来事は次に示す大きな課題をもたらしたと思われる。
先ず,国境問題に関する課題をみていきたい。現時点で最大の争点は地雷の使用である。国境問題悪化の原因となった銃撃戦が発生したモム・ベイで,7月16日,タイ兵士3人が地雷に触れ,うち1人が左足首を失う重傷,7月23日,タイのウボンラーチャターニー県チョンアーンマーで,タイ兵士1人が地雷を踏んで重傷を負った。23日,タイのプームタム暫定首相は駐カンボジアのタイ大使を召還し,駐タイのカンボジア大使を帰国させる意向を表明した。これが24日の軍事衝突の直接のきっかけとなった。23日,タイは対人地雷禁止条約(オタワ条約)締約国会議議長国の日本に報告書を提出した。タイとカンボジアの両国は停戦後,GBCで地雷撤去の協議を続けているが,カンボジアは「埋設した事実はなくタイの主張は証拠が不十分」と述べたと伝えられる。
8月9日午前10時頃,プレアヴォヒア寺院近郊のタイのシーサケート県カンタララック郡のカンボジア国境で,タイ兵士3人が地雷に触れ,1人が左足を失う重傷を負った。ほかの2人は,腕と背中の負傷および衝撃波を受けたことによる胸や耳の痛みを負った。3人は国境線に沿って有刺鉄線を敷設中,タイ領土内に埋設された地雷に触れた。地雷の破片を調べたところ,8月12日,タ・モアン・トム寺院から約1kmのタイのスリン県パノム・ドンラック郡で,パトロール中のタイ兵士1人が地雷に触れ,片足を失った。タイは,地雷は最近埋設されたものだと主張している。なお,タイもカンボジアも対人地雷禁止条約の締約国である。
ほかに,捕虜の取り扱い,一般市民への攻撃,プレアヴィヒア寺院の損傷,クラスター爆弾の使用,避難民の帰還,国境検問所の再開などの問題がある。
タイは7月29日にシーサケート県で拘束したカンボジア兵18人を捕虜として取り扱うとしている。上記13項目の合意の第6項は,「両国は,生活環境,避難所,食料,負傷している場合には医療を含む捕虜の取り扱いに関し,国際人道法に従う」と規定している(Joint Press Statement Extraordinary General Border Committee (GBC) Meeting, 7 August 2025.)。
一般市民への攻撃に関しては,8月1日,タイとカンボジアは,各々,諸外国の外交官や武官及びメディアを現地視察に招き,被害状況を説明した。タイ側では,シーサケート県の,国境から約30km離れた市街地のコンビニが戦闘の始まった7月24日に砲弾で炎上し,店内などにいた8人が死亡した。視察時,焦げた商品棚はそのままで,周囲にはガラスが散乱していた。コンビニの前で家族を失った遺族らが涙を流した。また,国境から約10kmの同県内の病院は7月26日に直撃した砲弾で窓と内部が破壊された。武力衝突の発生直後に患者らは避難しており,けが人はいなかった。タイは,カンボジアが無差別攻撃をしたと主張した。一方,カンボジアでもウッドーミアンチェイ州で空爆を受けるなどした被害地域と,数千人が滞在する避難所が公開された。カンボジアは,一般市民への攻撃は戦争犯罪だと非難した。実際,ジュネーブ諸条約違反の可能性がある。外交官やメディアはタイの状況により強い印象を持った模様で,メディアを通じて,これが世界に報じられる。この分野ではタイの広報戦略の勝利である。
世界遺産のプレアヴィヒア寺院の損傷に関して,7月24日,カンボジアは,同日のタイ軍の寺院やその周辺地域に対する砲撃や空爆で,建物の一部が壊れ,これは武力紛争時の文化財保護を定めたハーグ条約に違反すると非難し,攻撃停止を求めた。タイ軍は27日にも同寺院に対して砲撃を行った。
強い殺傷力を持ち,非人道的兵器とされるクラスター爆弾に関し,7月25日,カンボジアは,タイ軍がこれを大量に使用したと非難した。対象となったのはポーサット州のプノン・クマオチ山などである。これに対し,同日,タイ陸軍は,「軍事目標に対する破壊力を強化するため,必要に応じて使用を検討する」とし,クラスター爆弾を使用している事実を認めた。また,同軍は,「主要な発射体が目標に当れば,内包された子爆弾は連続して爆発する。そのような兵器は対人地雷ではなく,使用後,一般市民に長期的な影響を残すことは一切ない」と述べている。しかしながら,不発率が5~30%程度あり,犠牲者のほぼすべてが一般市民であるところから,クラスター爆弾は「第2の地雷」と呼ばれている。タイもカンボジアもクラスター爆弾禁止条約(CCM)の締約国ではない(Royal Thai Army Public Relations Center, Army News, 25 July 2025.)。
避難民の帰還,国境検問所の再開などは若干時間を要しそうである。
タイとカンボジアの関係において,タイは強者,カンボジアは弱者である。二国間協議ならば,強者が有利に交渉を進められる。武力抗争においても,タイが圧倒的な強者である。一方,カンボジアは,戦闘を続けるうえでも,交渉をするうえでも,国際世論を味方に付けることが重要である。ここでは真実や嘘ではなく,「真実にみえること」が重要な意味を持つ。カンボジアは地雷疑惑や多数の一般市民殺傷疑惑,タイは,プレアヴィヒア寺院の損傷,クラスター爆弾の使用で,それぞれ弱点を抱えている。両国は,自国の弱点を隠し,相手の弱点に国際社会の注目を集めようとするだろう。その際,プレアヴィヒア寺院を攻撃・破壊したのは相手国だとの言説を確立することが特に重要である。弱者であるカンボジアは被害の大きさを国際社会に訴えて,同情を集める「弱者の武器」を行使し得る。
関連記事
鈴木亨尚
-
New! [No.4166 2026.01.19 ]
-
[No.4136 2025.12.22 ]
-
[No.4118 2025.12.08 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
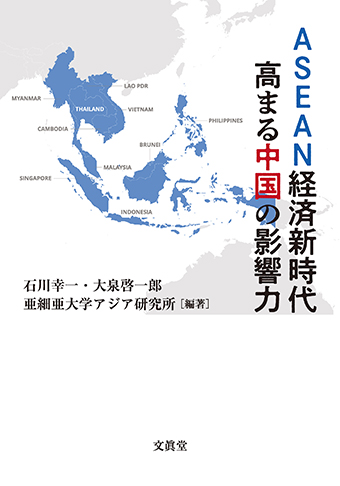 ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂

