世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
EU委員会,効率重視の英米モデル:舞台裏から見る欧州連合
(帝京大学 元教授)
2020.03.23
英米型経営モデルを推進したキノック行政改革
決して下剋上まではいく話ではないが,EU委員会内部における上層部の権力の弱体化というか希薄化は下部の執行部隊のレベルが実力を持っていれば勿論,それほど組織全体として問題ではない。事実,長い間そうであった。しかしそのような時代はもう過ぎ去ってしまった。このキノックの欧州委員会行政改革は,長い間,あのフランス流の中央省庁のモデルを模範にして出来上がった官僚エリート主導型のEU委員会の仕事の仕方を構造的に変革することを目標にしたのである。プロディ欧州連合委員長の時のその副委員長となったニール・キノック(Neil Knnock)は,80年代には英国の労働党党首だったが,嘱望されながら英国では政権にたどりつけなかった思いをブルッセルで実行しようとしたのだろうか,この大胆な改革に踏み切ったのである。どのような改革かと一言でいえば欧州大陸のフランス型のエリート公務員モデルからアングロサクソン型に近い英米風の経営モデルが導入されたのである。そういえば当時,だれでも口を開けば「米国型グローバル・スタンダード」と言われてもてはやされたものである。
私自身はその頃,1997年から3年間,このフランス・エリートの牙城と言われるパリベルシーの経済財政産業省・対外経済関係局(DREE)に出向した経験から,彼らのその戦略と執行,制御と管理などの峻別,事実上,近代経営学の原則を作り上げたアンリ・ファヨール(Henri Fayol)の経営管理論を実践したようなあの軍隊風ともいえる雰囲気が今でも懐かしく思いだされて来る。フランス人のジャン・モネやロベール・シューマンが欧州統合の生みの親であればEU委員会の統治や組織のあり方がフランス風になるのは当然と言えば当然であった。
当時欧州議会の副議長も務めていたフランス急進党のカトリーヌ・ラルミエールは実際にそのEU委員会のまさにこの構造的な改革にも携わっていたが,彼女はこのキノック改革について次の通り雑誌インタビュー(Etudes europeenns, novembre 2004)でちょっと衝撃的なことを告白している。
「EUとして公式にそれこそ効率性と近代化を目指すのだと声明する裏には,EU公務員,ユーロクラットたちの仕事のやり方をできるだけ分散化し,同時に純粋に業務の執行のみに限定していくという強い意志が働いていたのです。それは換言するとこれまでの欧州型の仕事スタイルを捨てて米国流の効率重視の職場に代えようとするものでありました」。
びっくりするような話である。それでは肝心のフランスの政治家はどうだったのか。彼女によると当時のフランスのジョスパン社会党内閣の重鎮で外相だったユベール・ヴェドリーヌも欧州問題担当相のピエール・モスコビッチもこの件には全く関心を示さなかったと言われる。これは恐らくかなり深刻な政治的判断の誤りであろうとカトルメートル氏は指摘する。このキノック行革によってそれまでEU連合の盟主を任ずるフランスの官僚制度に準拠していた欧州連合の考え方を英国・米国型の考え方に転換するきっかけになったと言われている。
金融街シティの投資銀行内のオペレーション・ルームに変貌
この頃から欧州連合公務員採用試験は欧州共同体についての知識に関する筆記試験や欧州統合機関のいかなる職種を希望選択するかの動機付けの口頭試問だったのが,それ以来,チームを引率する能力のような経営組織論に明るい人材を求めるようになったのである。そう言えばあの頃,確かにパリやリヨンの書店では経営戦略や経営組織に関する書物が非常に大きいスペースを占めるようになり,国を挙げてハーバード流のビジネススクールが競い合うように優秀な学生を募集し始めたのを目の当たりにしたものである。この重要な行政改革の陣頭指揮を取ったキーパーソンはキノック副委員長の審議官になったこれまた英国人のニコラ・ダイビッド・ビアフィールド(David Bearfield)であった。彼はそれまでのフランス型の知識重視の試験から知能(IC: intellectuel quotient)・情緒(EQ: emotional quotient)指数と実践即応能力に切り替えたのである。この採用方針の変更によって欧州公務員には欧州連合を魅力あるものにすることより組織管理,チームの効率的な運営,さらに業務の事前事後の評価などが鼓舞されるようになったのである。なんと現在ではEUを離脱してしまった英国人が現在の欧州連合の職員の働き方を変えてしまったのである。
私もよく覚えているが90年代から2000年代にかけて世界的にグローバル・スタンダードという名の妖怪が世界を駆け巡っていた。日本でも欧州でも労働システムでも会計制度でもこぞって効率と収益重視のアングロサクソン型の「グローバル」モデルがこぞってもてはやされたのである。IFRS,時価会計,CSRコーポレート・ガバナンス,などもう目白押しに喧伝されたものである。今日からは想像しにくいかも知れないが当時のトニー・ブレア率いる英国は自国のユーロ導入移行計画を発表したり,EU委員長人事にもベルギーの欧州連邦主義者のジャック・リュック・デハーネ首相任命に反対してルクセンブルグ首相のジャック・サンテールをもってきたり,深くEU統合作業や人事に関わっていたのである。このような訳でここでは欧州連合のビジョンとかフランス語で言う「ボカシオン」(vocation),すなわち使命目的という単語はタブーとなったさえ言われている。欧州統合という使命感や欧州という歴史的概念を金科玉条にしていた組織体制から,たった数年で現実の錯綜する国際関係や統合にまつわる仕事から完全に遊離したような民間企業型の経営組織体のようになってしまったのである。嘆かわしい話である。これでは委員会は今やロンドの金融街シティの投資銀行内のオペレーション・ルームのような場所になってしまったと言われても仕方ない。人材不足も手伝って業務を推進するのには外部のコンサルティング企業に頼る選択しかなくなってしまった。しかもそれらの企業はそれを熟知している英米系の会計弁護士事務所であった。この頃においてもドイツやフランスのコンサルティング企業は自国を越えた欧州規模,あるいは世界レベルの有力な経営力を有しているところはなかったことも一因ではある。
難しい委員会内部と総局の人間関係
キノック改革の悪影響は以上のようなところにとどまらなかった。2004年以前には委員会はどの部局にもいい人材を引っ張ってくることができた。ジャック・ドロールなどは職業歴もある有力ジャーナリスト出身の日刊紙リベラシオンのジャンミッシェル・バエルなどを登用したり,自分の出身国の優秀な人材を採用したものである。いわばドロール・スクールともいえるグループが有能な集団を形成していたが,これが当時委員会を再活性化するのに功を奏したとも言われている。しかし今日ではこうしたことはほとんど不可能になってしまった。問題はこうである。普通なら有力銀行でいたら高給で50才台の有能なエコノミストでもここでは安い報酬でしかも不安定な最大で6年位の期限付き雇用に余んじらなければならないのである。このために折角,OJT(On the Job Training)も含めて養成した職員を定期的に手放なければならなくなる。キノック改革の導入によってそうでない正規の職員は25才あたりでEU委員会に試験で合格し,定年まで終身雇用制度のなかで過ごし,ブルッセルのEU委員会のなかで一生過ごすことになってしまう。
委員会は今でも総局長,総局次長,課長レベルの序列の高い重要ポストには外部から人材を雇うことが認められている。これらの外部からスカウトされる臨時職員には欧州公務員の給与規定が適用されず,通常は本採用の場合より2倍以上の報酬が支払われていることが多いという。
このキノック改革に加えて,2004年(チェコ,エストニア,キプロス,ラトビア,リトアニア,ハンガリー,マルタ,ポーランド,スロヴェニア,スロバキア,)と2007年(ブルガリア,ルーマニア)には12カ国という非常に多くの中東欧・地中海諸国の新規加盟があったが,職員構成の国別バランスに気を使う委員会当局としては従来からの加盟国出身の数百人の早期退職を促すと同時に新規加盟国からの新規職員を採用した。市場経済化推進途上にあったこれらの「後進」国から採用された職員は本国の給与に比べてかなり高い報酬を支給されることになったが,2つ3つ問題が発生したのである。ひとつはEU委員会の業務に必須な知識と能力に欠けるものも中東欧・地中海諸国出身者には非常に多く,また厄介なのは西欧の文化や精神に非常に疎く,肝心の欧州共同体の統合そのものに情熱を傾けるようなことがなかったことである。これ以外にも実際の業務において文書作成規定に抵触するような誤り,例えば感嘆符をつけるかつけないかだけで大騒ぎになったりすることがあり,それを収めるのに時間がかかったりすることがしばしばあると次のようにため息をつく昔からの職員も多い。
「同じ目標,同じ理念,を持ち合わせていない28カ国の人が一緒にうまく働いていくのは本当に不可能に近いのかもしれない」。
さらにこのキノック改革によってコミッショナー委員そのものとコミッショナー付きの大臣官房室の間の関係も機能不全に陥ることがしばしばあるである。プロディ委員長時代以来,たった6人に縮小されてしまった大臣官房職員はそれぞれのコミッショナー委員の政党色に染まっている訳であるが,それでも往々にして自己の考えを実行させていくのに苦労することが多い。それは総局に立てついてまでコミショショナーの思うことについて総局長を説得したいとは思わないのである。いずれ5年すれば行革以来の配置転換の人事異動が控えており,ひょっとしたら昨日,喧嘩までした総局の上司のところに配属されるかもしれないからである。官僚の人事異動は国を問わずいつも官僚仲間の間では一番の話のタネになる。私もパリベルシー勤務のときに昼食時の最大の話題は人事の情報であった。これはどうもどこの国でも同じようである。しかしこんな人事騒ぎに実は英国人の当時仕掛けた行革が影響しているとなると本当にいたしかゆくであろう。
関連記事
瀬藤澄彦
-
[No.4208 2026.02.09 ]
-
[No.4151 2026.01.12 ]
-
[No.4139 2025.12.22 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
文眞堂 -
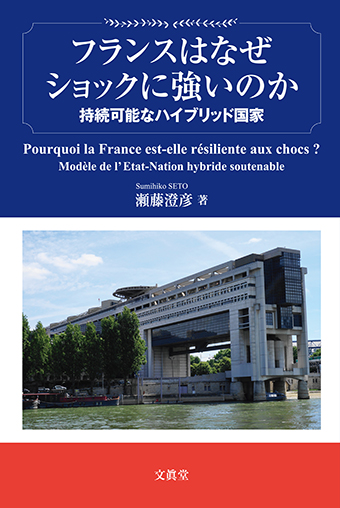 フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂
