世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
多国籍企業のグローバル価値連鎖:トランプ時代のグローバル経営戦略の行方
(国際貿易投資研究所(ITI)客員 研究員・元帝京大学経済学部大学院 教授)
2025.03.31
「多国籍企業の業務活動の世界的な分散こそ,グローリゼーションのもっとも重要な現象である」とノーベル経済学賞受賞学者P. クルーグマンは看破した。このようなグローバルな価値連鎖は世界産業地図を塗り替えてきた。筆者は,国際経営論や異文化経営論を論じていけばいくほど,取り扱う領域が一段と重層的になり隣接する諸科学の概念や考え方を動員しなければならないと常日頃より感じていた。それにも関わらず,米国大統領に返り咲いたトランプの主張する比較優位や競争優位を認めない政策は,言わば17世紀の重商主義を彷彿とさせる政府が貿易取引に積極的に介入し管理するとういう旧体制アンシャン・レジームに後戻りさせるようなものと言えよう。ローカルないしリージョナルな市場開拓を担う自立独立型海外子会社のマルチ・ドメスティック戦略,地理的分散の事業調整や統合の欠如。企業多国籍化の後退。海外投資の引上げ,合理化,投資受け入れ先国工場の閉鎖 の時代を迎えた。私たちはこれからどうアプローチしていくべきか。
まず第1に言えることは,不確実性という概念を導入し戦略を考え直す時期に来ているということである。コンティンジェンシー学派が戦略モデルの与件として考えてきた市場,産業,経済空間などの因子がグローバル化の中でその競争優位のモデルが大きく揺らいでいることを意味している。BOPと呼ばれる低所得途上国の世界市場経済システムへの統合,あらゆる産業で進行する製品・サービスのコモディティ化現象などこれまでの経営戦略モデルでは納得の行く説明はできなくなってしまった。新たな破壊的で攪乱的とも称せられるハイパー・コンペティションには,経済が合理的に収斂,均衡していくという市場メカニズムの調整機能に立脚した経営戦略モデルから脱皮してシュンペーター流の非連続・断続モデルを構築しようとする動きに着目する必要がある。砂浜を彷徨する蟻や蟹を観察し,それを企業内部の人間行動の非合理的で不均衡な限界を情報システムで補完しようとしたH.サイモンや,創発的な戦略構築を重視したミンツバーグ,知識の限界と複雑な問題対処に経済モデルの深化を訴えた2013年のノーベル経済学賞受賞のシカゴ大学教授L.ハンセンなどは重要な示唆を与えるものである。現代のグローバリゼーションの特徴であった多国籍企業の世界的な業務分散は,今,危機に瀕している。
第2に,企業活動のグローバル化が進む過程では,内部化と同時に外部化の動きが顕著となるが,それと同時に2つの現象に注目したい。それはグローバル市場における企業間の合併買収と,企業の海外進出に伴う産業の空洞化現象の議論である。これは企業内部の序列的ヒエラルキーに対抗する市場での自由な契約関係という制度的関係から企業と企業の関係の態様を解釈していこうというものである。これをグローバル市場の中では折衷理論としてニュージャージー大学名誉教授J. ダニングが比較,競争,立地の3優位として解明していた。製造業の空洞化現象を冷静に捉えていくとその理論が教える通り最近ではドイツや米国の企業の本国回帰への郷愁というか動きが「トランプ現象」として理解されるであろう。これに加えて益々,関心を集めるようになってきた世界的な企業ネットワーク論を合併買収や産業クラスターの国際的な拡がりや動きなどを通じて論じなければならない。しかし,トランプの政策にはそれが欠落している。
第3は,グローバリゼーションによる企業活動の世界的な分散がいかに始まり,どう統合し,調整していくかである。競争優位とそれを止揚したハイパー競争の覇権争いの帰趨は,企業の価値連鎖を上流部門から下流部門まで如何に国際的な最適配置を実現できるかにかかっていた。マサチューセッツ工科大学教授スザンヌ・バーガーは,企業に画一的な答えはないとしたが,デューク大学教授G. ジェレフィーがリード企業の存在を産業の特性に応じてモデル化していたように,中間財貿易の流れが世界貿易の重要なトレンドになっていた。世界的レベルのグローバル価値連鎖(GVC)のあり方は日米欧の多国籍企業間で世界戦略の相違となって現れていた。ドイツ企業はその垂直的価値連鎖の配置が東西両独の合併という政治的な歴史を享受しながら最も成功した事例として注目されていたが,ウクライナ戦争とトランプ政策によってその行方は非常に不透明になった。
第4に,これまでは,競争,ネットワーク,価値連鎖という概念で国際経営戦略論は語られてきたが,企業経営はグローバル・スタンダードのような普遍的な論理で貫徹しうるのか,あるいはA. チャンドラーがかつて格言のように唱えた「戦略が経営組織のあり方を変える」のか,またその戦略の態様は国によって違うのか否か。国ごとに執行と監査の体制が一様でないコーポレート・ガバナンス(企業統治)のあり方は,トランプ時代においては制度学派のアプローチで,労使関係,教育制度,金融システムという主要な経済社会の制度間の補完作用によって形成されてきたものであることが一層認識されようとしている。
第5として,現在起こりつつある新たな産業革命では,GVCにおける中間形態としての巨大な請負企業が新興国をむしろ震源地として誕生しつつあることだ。コロラド大学准教授ベアは,これをポスト・フォーディズムのGVCによる世界的産業開発におけるガバナンスの問題として捉える。欧州ではローカルな利害を価値連鎖の流れのプロセスとして参画するものと位置づけようする傾向がある。GVCの高度化によって緻密でハイブリッドなグローバル・ファクトリーが形成されつつある。バックレイによればここではブランド,デザイン,マーケティングなどの無形資産が大脳のように機能していくエンファリゼーション現象化が現出しているという。バーチャル組織や価値連鎖の非物質化という中で,ものを作る人々こそが新たな本格的なデジタル時代の主役になりつつある。
第6として,新しい競争モデルは,従来までの例えばM. ポーターの4つの競争要素のように新規参入,代替品脅威,顧客,供給者というような因子がビジネス空間と時間において静態的に構成されていたのに対して動態的な観点から「不確実性」を前提とせざるを得なくなる。米国のシカゴ学派のフランク・ナイトが述べているように,リスクと不確実性は別のことである。「リスクは結果の配分が観察される統計的計算によって分かっているが,不確実性は状況の特異性によって未知の状態のことを意味する」のである(文末参考参照)。では不確実なグローバル市場に企業はどのように対応していくのか。21世紀に入ってすでにその4分の1の時間が過ぎようとしている。新たなトランプ時代のグローバル経営戦略の行方は透明ではない。現実の世界で起こっている現象を命題として解析することを通じて,新たな国際戦略モデルの模索が始まっていることを示している。
(参考)フランク・ナイト(Frank Hyneman Knight 1885-1972)は,著書Risk, Uncertainty and Profit(危険・不確実性および利潤)において,確率によって予測できる「リスク」と,確率的事象ではない「不確実性」とを明確に区別し,「ナイトの不確実性」と呼ばれる概念を構築した。ナイトは完全競争の下では不確実性を排除することはできないと主張し,その不確実性に対処する経営者への報酬として,利潤を基礎付けた。
関連記事
瀬藤澄彦
-
[No.4208 2026.02.09 ]
-
[No.4151 2026.01.12 ]
-
[No.4139 2025.12.22 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
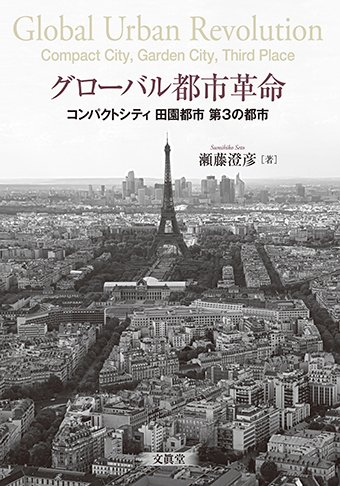 グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
文眞堂 -
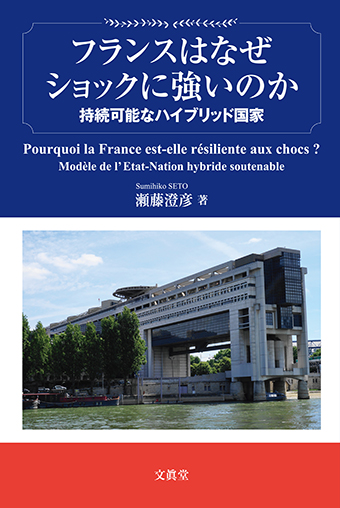 フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂
