世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
デジタルSNS社会がもたらす欧州政治の変容:街角を彷徨する名もない孤独な通りすがりの人
(国際貿易投資研究所(ITI)客員 研究員・元帝京大学経済学部大学院 教授)
2025.08.11
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は単に個人の生活や社会活動のみならず,政治の在り方にも無視しえない重大な影響を与えるものとなった。SNSの普及,その情報拡散のスピードとともに,国民の政治参加,そのあり方,選挙戦略,民主主義政治そのものに革命的と言えるほど大きな変化を生じさせている。Facebook,Twitter(現X),Instagram,WhatsApp,TikTokなど広く利用され,国民のほとんどが何らかのプラットフォームに登録している。政治家や政党もこれらのSNSを積極的に活用し,有権者との直接的なコミュニケーションを駆使して,支持を訴え,政策発信の場として活用することが必須となった。さらに市民自身も自らSNS上で政治的意見を表明,「ジレ・ジョーヌ」運動のように都市郊外住民のデモや署名活動などの集団行動を促進する手段となっている。
今や国家元首が肖像画のように居座り,演劇芝居の主人公のように振る舞い,神話物語のように厳粛に登場してくるかつての国王や将軍の様な優雅な時代は終わった。あるいは高度経済成長時代の政財界のリーダーのように,厚い中間階層がトップを支えていくような時代とも異なるようになった。世論に直接的に影響される新たな民主主義の時代,短時間の視聴覚メディアが動かしていく社会ネットワークや24時間放送のテレビが今やコミュニケーションの主役となった。グローバリゼーションの時代,1990年代~2000年代においては少なくともフランスでは世論調査やテレビ報道が中心的な影響力を発揮してきた。米国での1960年代のケネディ対ニクソンのテレビ党首討論から10年以上遅れて1974年のジスカール・デスタンとフランソワ・ミッテランの党首討論がフランスでは,政党,メディア,世論の3者関係の対話モデルとして出来上がり,これがミッテランとシラクの時代まで続いた(注1)。しかしフランスの社会学者ピエール・ブルデュが言っているように,この時代では「世論」というのは形成さるべきもので,あくまで「人工物」(artefact)であり,本来,アプリオリには存在しなかった。今日のようにデジタル通信の時代ではソ-シャル・メディアを操作すればだれでも直接的な意思表示ができるような時代ではなかった。2007年はフランスにもスマートフォン・インターネット接続などが本格的に導入された節目の年であるが,Apple のiPhoneやAndoriod向けのアプリなどのプラットフォームが一挙に広まった転換の時期でもあった。さらにTNT(Télevision Numerique Térrestre)地上波によるフランスの13海外圏・領土圏も含めた24時間TV放送が,サルコジ大統領の選出と歩調を合わせて発足した。それまでの「大衆民主主義」は,今やSNS上でどんなことでも意見を寸時に表明することのできる中間媒体の介在なしの市民による直接コミュニケーション民主主義に取って替わられてしまった。この新しい民主主義は,大統領を含む政治家の意識と行動に大きな変化をもたらした。 換言すれば,それは政治支配層と一般市民との間にコミュニケーション・チャネルにおける一切の仲介機能が排除されたことである。媒介機能の中間プロセス抜き,政治支配層の一般大衆への直接訴求というポピュリズム,事実や真実が後になって開示される「ポスト・トルース」,選択肢の妥協,などが情報操作と統制が重なり合い,ついには英国の文学者ジョージ・オーウェルが小説『1984年』に描いた全体主義的な監視社会や思想統制などディストピア国家が訪れる条件と時が近づいているのかもしれない。そしてこのような国民国家の社会の中で,私たち個人は,カナダ・ケベック州モントリオールの劇団が演じた「キダム」(注2)のように,街角を彷徨する名もない孤独な通りすがりの人,どこにでもいるありきたりの人,静かな大衆の一人,みんなであり誰でもない人間になってしまった。ここではこれまでの常識や序列の感覚は全く通用しなくなる。一種の「民主的独裁主義」(democrature)の到来とともに,社会的ネットワークは分断されるか,厳しく統制される。ここではデジタル・インフルエンサーたちが評論家に取って代わってしまう。フランス社会科学研究高等大学院(EHESS)フィリップ・ギルベール教授(Philippe Guilbert)によれば都市部の高学歴者や裕福な年金生活者などにアピールしてきた評論家は大衆の期待を裏切り続けてきた。フランス革命から150年後の19世紀にはドイツの哲学者ヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin)が,ラジオと映画こそが大衆独裁であると断じた。とりわけ,テレビはフランスでも米国でも大統領を筆頭に行政府のリーダーシップ,議会に対する優越的な地位に大いに貢献した。ところがスマートフォンは違う。何時でも瞬時にどんな場所でも意思表示が顔認証も含めて行えるスマートフォンは,すべてのひとびとが共同体の一個人として振る舞える「ポピュリズムにおける兵器」である。トランプはTwitter(X),イタリアのサルビニはInstagram,ジョルジア・メロニ首相は YouTube,をそれぞれ個人的な宣伝のツールにしてしまった。さらに言うならば,この新しい兵器はすべての意見を平等に発信し,序列的な優越性,制度的なガバナンスをほぼ無意味なものにしかかっているのである。このような「デジタル民主主義」時代にあっては,今やすべての政治家にとってポピュリストであるないかにかかわらず避けて通れない政治スタイルとなってしまった。言うなればテレビ時代の政治家は垂直型のナポレオン型であり,デジタル時代のそれは水平型のポピュリスト型と言えよう。そしてこの両方の交差する公共空間こそ,政治家だけでなく異議申立てに好都合なところとなった。この典型がふたりの国家元首,すなわち英国のボリス・ジョンソンとフランスのエマヌエル・マクロンであった。伝統的な保守党のスタイルを逸脱したジョンソン首相の保守党は« Get Brexit Done, Unleash Britain’s Potential »(離脱に決着をつけよう)というスローガンを混迷極まった政局の打開のアピールを国民に直接迫り労働党に圧勝もたらした。フランス第5共和国の社会党と共和派の一部は,従来の政治に反発し中道主義の呼びかけに賛同した。こうした動きを背景に,革新と保守を同時に兼ね備えた脱構築とされる思想「アン・メーム・タン」(同時に“En même temps”)というフレーズをSNSなどで連発,マクロンが大統領選に勝利,ルペン候補を寄せ付けなかった。これらはいずれもポピュリスト型の政治スタイルの発想であった。一般大衆の支持を基盤にして,感情的訴えやメッセージで既成の権力システムを批判,選挙民に訴えるやり方は共通していた。ポピュリスト型の波に飲み込まれていなかったのはアンゲラ・メルケルのドイツだけであった。16年間という長期間,在任したメルケル政治にはカリスマ性はなく,またナチス時代のトラウマに縛られ続けてきたドイツ社会には依然として集団的コンセンサスや安定的保守志向,ナチスのような強い権威独裁への警戒心と同時に一種の憧れの感情,他国では警戒される移民に対する寛容な態度,などがここでは既成政党や連邦議会,法治主義,権力の抑制,妥協による合意形成など深く根付いてポピュリズムの入り込む余地は旧東独地域を除きなかったと言える。メルケル政治の功罪のツケは大きかったと政策研究大学院大学教授の岩間陽子は断言する(注3)。
結論的に言うならば,個人の意思を自由に開示できるデジタル型の民主主義国家では政治リーダーは全員,ポピュリストたらざるを得ず,あるいはポピュリスト的スタイルを選択せざるをえないのである。リベラル自由主義によって発生した社会のコンセンサスの分断や,拡大し続ける不平等を被るひとびとはまさにデジタル・ポピュリズムにその敗北の異議を申し立て,同時にそこに誇りにも似た満足を見出したのである。ジレ・ジョーヌ運動は発生からわずか数週間でFacebookを通じフランスばかりでなく欧州の近隣諸国にあっという間に広まった。2023年7月,パリ西郊外ナンテールで交通取り締まりの際に停止命令に応じなかった17歳の少年が警官によって射殺される事件が発生した。この事件を受けて,ナンテールやパリ周辺,さらに全国各地で抗議活動や暴動が短期間で拡大した。このような観点から眺めてみると,中道マクロニズムも極右ルぺンニズムも極左メランショニズムも,リーダーの個人的な党内基盤も,実は堅古でも十分なものでもなく,その政治的長期存続は極めて脆弱なところがあると言えよう。
[注]
- (1)Philippe Guibert, Gullivert enchaine, cerf, P.103, 2024
- (2)キダム(Qruidam)はカナダ・ケベック州の劇団「シルク・ソレーユ」の移動公演の9番目の作品の演目。両親から疎外され無視された少女ゾエの想像する風変わりな世界。ここでは傘と山高帽を持った頭のない男性キャラクターこそ,わたしたちみんなであり,同時にだれでもないことを具象化。
- (3)日経新聞「この一冊」(2025年7月19日),岩間陽子「『自由(上・下)』「ドイツの母」在任16年の功罪」。
関連記事
瀬藤澄彦
-
[No.4208 2026.02.09 ]
-
[No.4151 2026.01.12 ]
-
[No.4139 2025.12.22 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
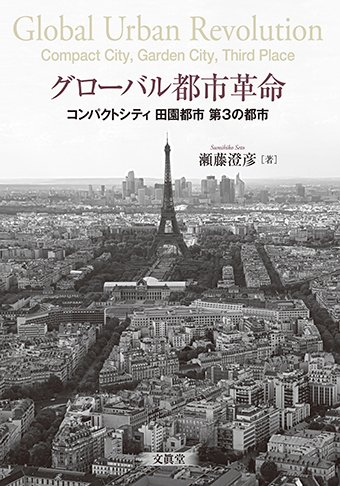 グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
文眞堂 -
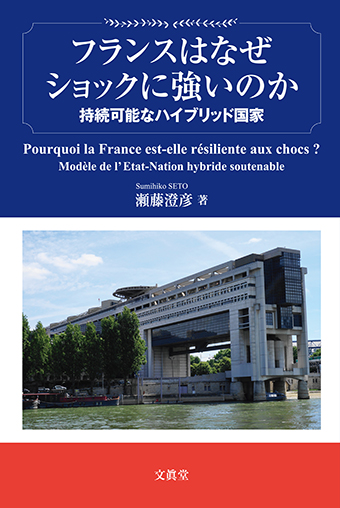 フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂
