世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
険悪な状態に逆戻りした日中関係
(亜細亜大学アジア研究所 教授)
2025.11.24
高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁に端を発する中国の激しい反発に,「またか」と既視感を持つ日本人は少なくないだろう。中国政府の激しい非難とともに各部門が次から次へと繰り出す措置は,毎度のことだが徹底している。駐大阪総領事のXへの暴言投稿やポケットに手を突っ込んだまま横柄な態度で写真を撮らせる外交部局長の姿など,物議を醸す言動も含めすべては上への忠誠心を見せないで傍観していると自分にまで類が及ぶからの一斉行動なのである。上海で予定されていた吉本興業の芸人による公演が中止になった際,中国の主催者側がその理由を「不可抗力」と発表したがその通りである。
10月31日に韓国慶州で高市首相と習近平主席による日中首脳会談がぎりぎりのタイミングで決定し行われたが,首相就任の祝電も送らない主席が正式な会談に応じることはない(せいぜい立ち話)と筆者はみていた。中国側の報道で「応約会見(申し出に応じて)」とただし書きをつけているが,会談に応じたのはなぜだろうか。この会談風景を伝える中国メディアの映像を改めて見ると,大人(たいじん)風の主席が何かを諭すように語り,一方で首相が子供のように頷きながら拝聴している風景だった。すなわち,歴史や台湾といった原則問題に関する両国間の合意に反することのないよう釘を刺したということである。おそらく中国の外交当局も主席が臨んだ会談が裏目に出ることのないよう気を揉んでいたことだろう。
それが同じAPEC首脳会議の場で首相は台湾代表と2度交流し,「総統府資政」という肩書付きでXに投稿した。そして11月7日の国会答弁である。日本外務省のHPでは,日中首脳会談で「首相から日本産水産物の輸入の円滑化を求めた」とあるが,19日には「たとえ日本の水産物を中国に輸出したとしても市場は存在しないだろう」(外交部報道官)とこれを突っ返した。また首脳会談に係る同HPで「尖閣周辺海域を含む東シナ海での中国によるエスカレーションや海洋調査活動,我が国周辺の中国軍の活動の活発化につき,深刻な懸念を伝え,中国側の対応を求めた」とあるが,中国メディアは相次いで「琉球諸島の帰属は未確定」とする論評を公開し始めた。琉球の帰属問題は日清戦争,台湾割譲につながる日本の侵略の起点であるという倍返しの主張である。
中国側の強い反発の背景には,日韓の防衛費増額,高市政権の非核三原則見直しや原子力潜水艦保有の検討,韓国の原潜建造を米国が承認するなど,米国の戦略的撤退によって生じる空白を日本と韓国が埋めようとして,現状変更に踏み込んでいるとする強い危機感がある。日本の主張する抑止力とは中国に対する挑発,というのが先方の受け止めであり,「存立危機事態」という荒唐無稽な主張で日本は軍事介入への法的準備をしているだけ,となる。
高市首相はその人事からも台湾有事への関心が極めて高いことがうかがえる。台湾海峡危機政策シミュレーション(日本政策研究フォーラム主催)に2年連続参加したとHPに掲載している尾崎正直官房副長官,元航空自衛隊(空将)出身の尾上定正首相補佐官(国家安全保障に関する重要政策及び核軍縮・不拡散問題担当)が特筆されるが,首相周辺には木原稔官房長官をはじめ親台派と呼ばれる議員が少なくない。他方,中国との間に一定のパイプを持つ公明党は政権から離脱し,二階俊博氏から日中友好議員連盟会長を引き継いだばかりの森山裕自民党前幹事長は党内非主流派となってしまった。
中国側から見れば,新首相が何か好ましからざる事を起こすことを十分に警戒していただろう。そこで起きたあの踏み込んだ国会答弁である。「建設的かつ安定的な関係」構築の方向性を確認したという首脳会談だったが(外務省HP),あっという間に真逆の方向に走り出してしまった。首相の答弁撤回は考えられず,中国側が軟化することもないだろう。険悪な日中関係の長期化は避けられない。国会答弁の当日午前3時から勉強会を開いて国会に臨んだ首相であるが,こうした事態にどれだけの備えと覚悟があったのだろうか。
関連記事
遊川和郎
-
[No.4014 2025.09.29 ]
-
[No.3872 2025.06.16 ]
-
[No.3755 2025.03.10 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
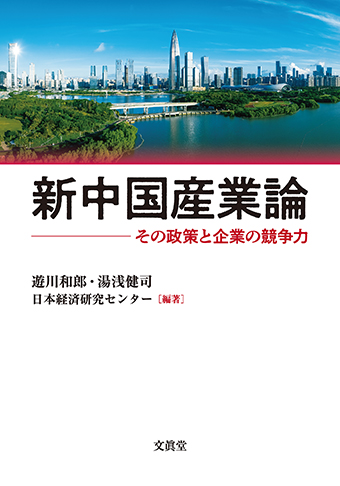 新中国産業論:その政策と企業の競争力
本体価格:2,800円+税 2024年7月
新中国産業論:その政策と企業の競争力
本体価格:2,800円+税 2024年7月
文眞堂 -
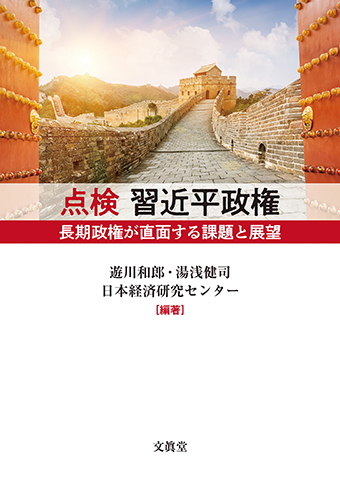 点検 習近平政権:長期政権が直面する課題と展望
本体価格:3,200円+税 2023年7月
点検 習近平政権:長期政権が直面する課題と展望
本体価格:3,200円+税 2023年7月
文眞堂 -
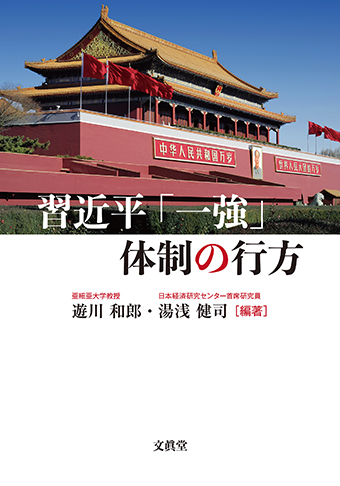 習近平「一強」体制の行方
本体価格:3,200円+税 2022年10月
習近平「一強」体制の行方
本体価格:3,200円+税 2022年10月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂
