世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
最低賃金政策と経済成長
(神奈川大学 名誉教授)
2025.09.15
30年ゼロ成長といわれた日本経済は宿痾であったデフレ型経済(デフレスパイラル)から脱却し始めているようにみえる。黒田前日銀総裁(2013-2023)は2%のインフレを目指し,大規模な異次元金融緩和をとることで実現しようとした。しかし,それまでの15年にわたるデフレは脱却したもののマイナス金利政策をとっても2%インフレは定着しなかった。プラザ合意以降の国内物価水準停滞の結果,物価が先進諸外国より高い内外価格差の時代から,先進諸外国より安い逆内外価格差の時代へと国内経済環境は変化し,ラーメンが先進諸国では日本の約3倍の3000円となっている。この岩盤のようにみえた長期にわたるデフレ経済は,コロナ禍,ウクライナ侵攻と円安が加わることでインフレ体質への転換に成功したようだ。しかし,いまだに国内実質賃金はインフレを補填できるまで上昇していないことが問題で,国民の不満が高まっている。最近の選挙では生活苦から欧米と同じくポピュリスト的な極端な政策を掲げた極右あるいは極左の政党が議席を増やし躍進している。日本では最近まで,経済停滞下で所得が減少しても,政治は安定していた。おそらく,新自由主義的なグローバリゼイションが進むなかでも実質的な格差は拡大せず,生活が維持できたからであろう。ジニ係数を見ると,当初所得ジニ係数は1996年0.4412,1999年0.4720で2021年は0.5700とかなり悪化した。しかし,再分配所得ジニ係数は1996年0.3606,1999年0.3814が2021年は0.3813と悪化はかなり抑えられている。日本の数値は北欧やドイツ,フランスなどよりは悪いが,アメリカやイギリスよりも良い数値である。特に注目されるのは,これら日本より所得の平等性が高い国々はこの30年間で日本より再分配所得ジニ係数が大きく悪化している。しかし,コロナ後のインフレで実質所得の減少が生活苦をもたらした結果,ポピュリズム的な政党に支持が集まり始め政治の安定性が揺らいでいる。
多くの識者がデフレ経済をもたらした要因を分析しているが,最大の問題点はGDPの分配問題である。筆者が多くを学んだ,デーヴィット・アトキンソンの『日本人の勝算』では,日本経済再生への具体的な方策として,中小企業改革と最低賃金引上げをとり上げている。今回は最低賃金引上げから問題にアプローチしたい。
企業の利益剰余金はこの30年間で150兆から600兆円へと約4倍に増加した。同期間中,従業員の賃金は全く伸びず,実質賃金ではこの30年で3%の低下となっている。名目賃金は1991年を100とすると2023年の数字は,日本は102,米国288,英国287,ドイツ228,フランスが208である。
日本の賃金が上昇しなかったのは労働生産性が向上しなかったという説明もある。しかし,河野龍太郎はこの30年間(1998年の数値を基準としている)で日本の時間当たりの労働生産性は30%上昇しているとし,所得再分配が最優先の課題と主張している(河野『日本経済の死角』)。注意点として,河野は言及していないが,この30%の上昇はこの間の日本の労働時間減少が関連している可能性を指摘しておきたい。一方,米国の生産性上昇は50%で実質賃金は25%上昇した。米国においてはイノベーションで生産性が上がっても,一部の人に恩恵が集中するという収奪的な構造が政治の不安定につながっているとし,再分配が不十分と結論付けている。さらに示唆的なのが,ドイツとフランスの事例で,ドイツにおける同期間の時間当たり生産性上昇は25%,フランスは20%である。にもかかわらず,賃金上昇はドイツが15%弱で,フランスは20%弱を記録し,企業が新たに生み出した付加価値はきちんと従業員に配分されている。河野は日本企業の従業員への配分が少ない原因を,メインバンク制の崩壊で保護を失った企業が長期雇用制を継続させるため,国内設備投資を更新投資に限定,ベア上昇を凍結,利益剰余金を積み上げた,と論じている。
失われた30年の賃上げ抑制による影響を強く受けたのが非正規部門の雇用者であった。新自由主義による規制緩和の流れを受け,日本でも雇用・労働の規制緩和が進行し,1980年代半ばには15%程度であった非正規雇用は1993年に20%,2003年に30%を超え,2018年38.3%に達し,その後は37%前後となっている。労働市場の規制緩和は生産性向上と賃金上昇に結びつくはずであったが,ジョブ型雇用への制度再編がうまくいかなかったことで,二重労働市場制を生み出してしまった。非正規雇用部門では同一労働であっても低賃金であり,長期働いても定期昇給の対象外となることが多く,社会保険も盤石ではないなど,多くの不利益がある。日本経済の再生には,この人たちの賃金水準の引き上げが喫緊の課題である。日本は労働組合の組織率が低下し労働組合の交渉力にあまり多くを期待できない状況下,国家が経営側に賃金水準を強制できる最低賃金の引き上げによる経済成長戦略が俎上してきた。
アトキンソンは日本の一人当たりGDPに対する最低賃金の割合は34.9%(2016年のデータ)で,先進国はもちろんインドやタイなどの途上国と比べても低く,最低水準であると指摘している。アトキンソンは118人のエコノミストの論文を読破し検討した結果,最低賃金の継続的な引き上げが日本経済の好循環を実現する要石と結論付けている。その立論は,所得を継続的に上げることで生産性を引き上げる。今の日本経済にとって,所得を継続的に上げる最良の政策が最低賃金の持続的な引き上げである。その目標値は日本の最低賃金水準を一人当たりの平均賃金の50%と設定している。50%は欧州のEU指令(適正な最低賃金に関する指令)が示す参考指標でもある。最低賃金の引き上げは,生産性が特に低い日本のサービス業に効果があり,地方の賃金格差解消にもつながる可能性が高い。政府も積極的な最低賃金の引き上げの必要性は十分認識しているようで,今年度の最低賃金は全国加重平均で過去最大の66円の上昇で1121円になった。石破首相は「賃上げが成長戦略の要」と述べており,格差解消と生産性向上目指している。一方,引き上げに反対する論拠でよく言われるのは,引き上げによって失業者が増大するとの主張である。新古典派は労働市場でも政府などは介入せず,需要と供給の均衡点で決定するのが最も経済合理性が高いと結論付ける。しかし,イギリスの経験から新古典派が主張する最低賃金上昇と失業者増大の関係性は否定されている。労働市場では,情報が非対称性であり,移動に転職コストがあることが関係性成立を阻んでいる。
2021年10月に始まった岸田元首相の新しい資本主義実現会議で非正規雇用者等への分配強化策として最低賃金引上げをとり上げた。今年6月の36回目の新しい資本主義実現会議では「2020年代に全国平均1,500円という高い目標の達成に向け,たゆまぬ努力を継続する」としている。岸田政権時の「2030年代半ばまでに1,500円となることを目指す」とする目標値を早期に実現する目標となっている。
今年度の改定でアルバイトの給与が正社員の給与を上回り,給与体系の見直しを検討する企業も現れている。継続的な引き上げは,既得権とぶつかるであろうが,日本経済の再生と経済格差軽減のため,最低賃金水準が他の先進国のレベルに達するまで,最低賃金上昇を強力に推進することは国家の責務であろう。マリアナ・マッカスキルが言うように,国家は最大のイノベーターであり,現状打破のため国家レベルの強力な最低賃金政策が求められていると考える。
関連記事
山本博史
-
[No.3874 2025.06.16 ]
-
[No.3661 2024.12.16 ]
-
[No.3452 2024.06.17 ]
最新のコラム
-
New! [No.4131 2025.12.15 ]
-
New! [No.4130 2025.12.15 ]
-
New! [No.4129 2025.12.15 ]
-
New! [No.4128 2025.12.15 ]
-
New! [No.4127 2025.12.15 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
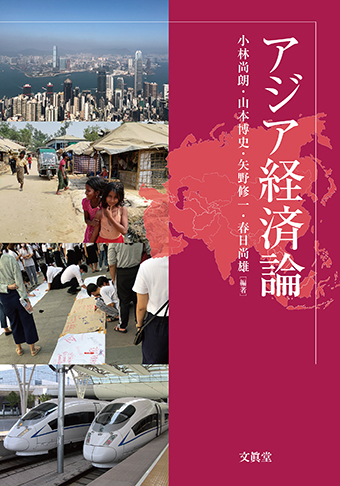 アジア経済論
本体価格:2,600円+税 2022年3月
アジア経済論
本体価格:2,600円+税 2022年3月
文眞堂 -
 アジアにおける民主主義と経済発展
本体価格:4,200円+税 2019年3月
アジアにおける民主主義と経済発展
本体価格:4,200円+税 2019年3月
文眞堂 -
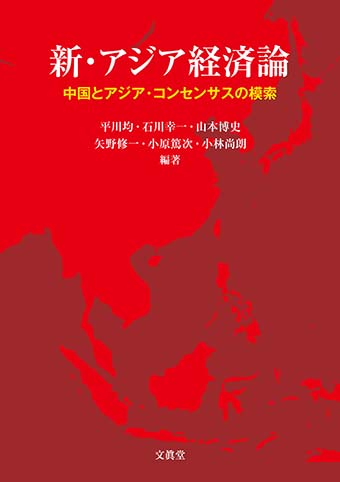 新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
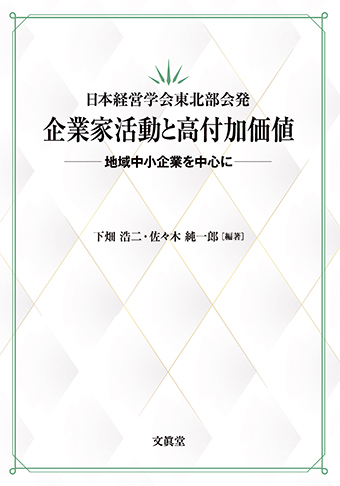 日本経営学会東北部会発 企業家活動と高付加価値:地域中小企業を中心に
本体価格:2,600円+税 2025年6月
日本経営学会東北部会発 企業家活動と高付加価値:地域中小企業を中心に
本体価格:2,600円+税 2025年6月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂

