世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
ASEANに厳しい相互関税
(亜細亜大学アジア研究所 特別研究員)
2025.04.07
米国が4月2日に発表した相互関税は,ASEAN,とくにCLMV(カンボジア,ラオス,ミャンマー,ベトナム)に厳しいものになっている。トランプ1.0では,ASEANに対する追加関税はなく,迂回輸出により対米輸出が伸びるなど漁夫の利を得たといわれた。しかし,相互関税はカンボジア49%,ラオス48%,ベトナム46%,ミャンマー44%とCLMVに極めて高い関税を課している。ASEAN6についてもタイ37%,インドネシア32%,マレーシア24%,ブルネイ24%と高く,フィリピンは17%だった。米国が黒字を計上し関税もほぼ撤廃しているシンガポールにも10%が課されている。CLMVやタイ,インドネシア,マレーシアは対米輸出が増加し米国の貿易赤字が急増していることが背景にある(注1)。ベトナムは米国の貿易赤字計上国として第3位であり,ASEANに対する貿易赤字を合計すると2,305億ドル(2024年)に達し,世界2位の規模になる。中国に制裁関税が課された2018年以降,中国のASEANへの製造業投資が大幅に増加しており中国企業のASEAN迂回輸出戦略が進められたことも赤字の要因である。
米国はASEANの輸出では中国と並ぶ市場であり(注2),相互関税でASEANの対米輸出は悪影響を受けることは避けられない。ASEAN各国の対米輸出依存度をみると,カンボジア37.9%,ベトナム27.4%と極めて高いが,タイは17.2%,フィリピンは15.6%,マレーシア11.3%となり,インドネシアは9.0%,シンガポールは9.3%と一桁である。ミャンマーは4.0%,ラオスは1.4%とほとんど依存していない。とくに影響が大きいのはカンボジアとベトナムである。依存度が10%台の国でも品目によって大きな影響を受ける可能性がある(注3)。なお,ベトナムは鉄鋼製品,カンボジアはアルミ製品を対米輸出しており,鉄鋼とアルミ製品に対する25%関税の影響もうける。
中国に対する関税は79%
中国への相互関税は34%だった。中国へはトランプ1.0で最大25%の制裁関税が課されており,バイデン政権でも継続していた。25年2月と3月に10%の追加関税が課され,トランプ2.0での中国への追加関税は20%となっている。トランプ1.0での25%の制裁関税は撤廃されていないので中国に対する追加関税は合計で45%となり,相互関税34%が加算されると4月9日以降79%という禁止的高関税が中国に対して課され,トランプ氏が選挙期間中に発言していた60%の対中関税を超えてしまう。
ピーターソン国際経済研究所によると,2018年1月に3.1%だった米国の対中平均関税率は2020年1月には21.0%に上昇した。そして2025年2月に30.4%,3月に42.1%に上昇している。相互関税が発動されれば75%前後の水準になるだろう。極めて高い対中関税はASEANに対してプラスとマイナスの影響を与える。対中関税は対ASEAN関税よりもかなり高いため迂回輸出を目的とする対ASEAN投資は続くと予想される。一方,対米輸出が困難になった中国製品がASEAN市場に流入する可能性がある。ASEANは中国の過剰生産能力に起因する中国の消費財などの輸入急増が問題となっており,地場企業への悪影響などが懸念される。また,中国の景気悪化による対中輸出の低迷,EUなど第3国市場における競争の激化なども予想される。
米国の信頼の低下と中国の影響増大
ユスフ・イシャク研究所が毎年実施しているASEAN有識者意識調査によると2024年は米中間で選択を迫られた場合中国を選択するという回答が米国を選択するという回答を上回っていた。WTOルールを無視した大国の横暴というべき相互関税はASEANでの米国への信頼をさらに低下させるだろう。CLMVはASEANだけでなくASEAN域外国や対話国から開発格差の縮小を目的とした「特別かつ異なった待遇」を受けてきた。CLMVに対する極めて高い相互関税はそうした協力と逆行する措置であり,格差是正に対する長年の努力を踏みにじる米国への不信が高まるだろう。相互関税により米国市場へのアクセスが困難となるためASEANと中国の経済的相互依存をさらに深まる可能性がある。また,米国国際協力局(USAID)の実質解体により米国の経済協力は大幅に縮小し,すでに大規模に実施されている中国の経済協力は継続することから中国の影響が強まることになる。
トランプ型政治が今後も継続するようであれば,米国への過度の経済的依存はリスクとなる(注4)。多角化により経済の米国依存を軽減することが課題となり,ASEANは東アジア諸国やEUとの関係を拡大するとともにグローバルサウスとの経済関係の強化を進めることが重要となる。BRICSへの接近はその例であり,インドネシアが2024年にBRICSに加盟し,マレーシア,タイ,ベトナムはBRICSパートナー国となっている。南アジアのRCEP加盟,CPTPPの拡大,GCCとのFTA,中南米さらにはアフリカとの経済連携も課題となってくる。
[注]
- (1)米国の対ASEAN赤字の急増については,石川幸一「ASEANと相互関税」世界経済評論インパクトNo.3732,を参照。
- (2)ASEANの対米貿易については,石川幸一・大泉啓一郎・亜細亜大学アジア研究所編(2025)『ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力』文眞堂を参照。
- (3)相互関税の影響は,競合国の状況,代替品目の有無,米国で製造されているかなどにより異なってくる。相互関税が10%台であれば10%の共通関税との差は一桁となり,関税コストを吸収できる可能性が高くなる。また,衣料品などは米国内で製造すると人件費が高く,労働者を集めることも難しいため,輸入が続く可能性が高い。
- (4)トランプ3.0については,「トランプ3.0,4.0の覚悟が必要」(環太平洋アジア交流協会:SAPA)を参照。
関連記事
石川幸一
-
[No.4120 2025.12.08 ]
-
[No.3957 2025.08.18 ]
-
[No.3856 2025.06.02 ]
最新のコラム
-
New! [No.4149 2025.12.29 ]
-
New! [No.4148 2025.12.29 ]
-
New! [No.4147 2025.12.29 ]
-
New! [No.4146 2025.12.29 ]
-
New! [No.4145 2025.12.29 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
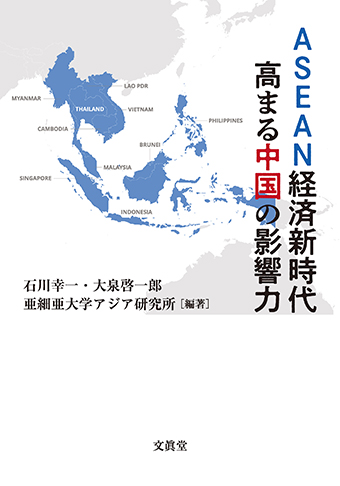 ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
文眞堂 -
 高まる地政学的リスクとアジアの通商秩序:現状と課題、展望
本体価格:2,800円+税 2023年9月
高まる地政学的リスクとアジアの通商秩序:現状と課題、展望
本体価格:2,800円+税 2023年9月
文眞堂 -
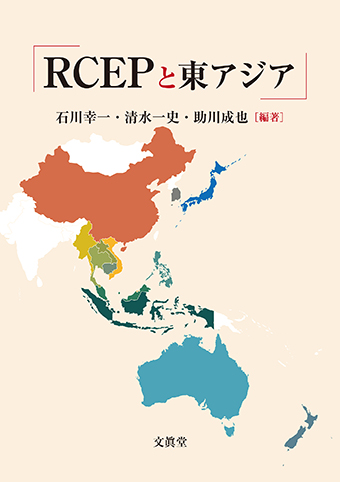 RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂

