世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
クシュタールによるセブン&アイの買収提案:消費者不在のビジネスゲーム
(早稲田大学・文京学院大学 名誉教授)
2025.04.07
2024年8月,セブン&アイ(以下,セブン)はカナダのアリマンタシォン・クシュタール(ATC)から買収提案を受けたことを公表した。買収金額は,当時のセブンの株価総額を2割ほど上回る6兆円規模であった。ATCの株価総額はセブンのそれの2倍であり,セブンのステークホルダーにとって利益になるというのが買収提案の根拠であった。ATCは企業理念のなかで,買収戦略によって成長することを潜在的に謳っており,これまで米コンビニ・サークルKの買収,仏トタールの給油所などの買収により,急成長してきた。
セブンはただちに,社外取締役5人からなる特別委員会を設置し検討に入った。その結果を受けて,セブンは2024年9月に,①6兆円の評価額が低いこと,②両社のM&Aは米国において反トラスト法違反の問題を引き起こすとする理由をもってて,買収提案を受け入れない旨回答した。この回答に対して,10月ATCは買収金額を7兆円規模に引き上げて再提案をおこなった。
セブンは,この買収提案への対抗措置を矢継ぎ早に打ち出した。第1は,コンビニ事業と業績低迷の非コンビニ事業の分離であった。スーパー,外食,専門店などの非コンビニ事業をまとめて中間持株会社「ヨークホールディングス」を設立し,外部資金を導入し上場する。今後は,米ベイン・キャピタルが中心になって同社の合理化・効率化を図るという。コンビニ事業会社は,「セブン―イレブン・コーポレーション」となる予定である。
第2に,セブンの創業家が同社を買収し,非上場化することを提案した。この案は,8兆円規模の資金調達の見通しがたたず,2025年の2月には断念された。第3は,2026年下半期までに,米国コンビニ事業の米国での上場を目指すものである。米国事業の独立性を高め,北米市場での成長を加速させる考えである。第4は,北米子会社の上場益や非核事業売却益を,2030年度までに,時価総額の4割に相当する総額2兆円の自社株買いをおこない,株価上昇を図ろうとしている。
ATCによるセブンの買収提案とその対応は,国際M&Aの問題のみならず,日本企業の抱える問題を浮かび上がらせた。第1は,セブンのような国内の優良大企業であっても,成長が停滞し株価が低迷すると,外国企業によって買収される危険性が生じる時代になったことである。
第2に,こうしたM&Aの提案においてきまって強調されるのは,「企業価値」や「経済合理性」である。しかし,企業価値や経済合理性は,ステークホルダーによって意味は異なる。2019年,米国のビジネス・ラウンドテーブルは,株主第一主義からステークホルダー主義への転換を提唱した。真摯な買収提案に対して真摯な対応を求め,M&Aによって市場を活性化しようとする2023年の経済産業省の「企業買収における行動指針」や東京証券取引所の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」では,企業価値の向上が強調されている。しかし,その本質は株価の上昇であり,ステークホルダーのなかでも株主,とりわけ投資家の視点が強調され,他のステークホルダーにとっての意味は曖昧である。
第3は,第2の問題と関連するが,企業の社会的存在意義が,無視されつつあることである。小売企業の存在意義は,消費者が必要とする商品・サービスを,必要とする時に,必要な量,必要な形で提供することである。セブン―イレブンは,その実現のために,中小小売店の業態転換,単品管理・共同配送・チームマーチャンダイジングなどの小売ミックスの革新をベースに,「日本型コンビニシステム」を構築してきた。
ところが,ATCは給油所併設のコンビニ運営が中心で直営店が7割となっており,セブンーイレブンのコンビニモデルとは大きく異なる。給油所併設のコンビニの場合には,ドライブ中に必要な品揃えやサービスの提供で済む。しかし,「日本型コンビニモデル」ははるかに複雑で,一般消費者が日々必要とする多様な食品・日用品・サービスを提供している。さらに,災害時への対応,女性や子供の駆け込み,高齢者の見守り,青少年の育成,公共サービスの提供も担い,まさに「生活インフラ」の役割を果たしている。
ATCはM&A巧者といわれている。だが,その手法は財務手段によって,買収した企業の収益を次に買収する資金を生み出す手段として利用していくものである。おそらく,ATCにとってセブンの最大の魅力は,セブン―イレブンのもたらす毎年の巨額の利益であり,これをさらなるM&Aの原資として活用することであろう。そのため,両社のコンビニ運営の目的は大きく異なり,ATCがセブンを買収した場合,買収後の事業統合(PMI)は,うまくいかない可能性が懸念される。
また,M&Aで成長する場合には,景気が良く株価が上昇する環境が整っていなければならない。トランプ政権2.0のもと,米国経済のみならず,世界的に景気の先行きがみえない。こうした状況が生まれると,M&Aによって成長してきた企業が困難に陥ることは,歴史の教えるところである。
コンビニのような小売業は,その国の国民生活を支え,ライフスタイルに影響をあたえるという意味では,鉄鋼産業や半導体産業よりもはるかに,国の経済安全保障にとって重要である。その証拠に仏政府は,ATCが仏の代表的スーパーであるカルフールを買収しようとしたとき,食料安全保障に関わるとして認めなかった。日本政府は,コンビニを外為法の「コア業種」に追加した。これを根拠に,日本政府が外国企業に対して,「日本の消費者や企業を守る」と,論陣をはる気概があるのか懸念される。
第4は,社外取締役や経営者の役割と責任についての問題である。2025年3月に,セブンの井阪隆一社長が特別顧問に退き,買収提案を検討してきた特別委員会委員長をつとめていたスティーブン・ヘイズ・ダイカス氏が後任の社長に就くことが発表された。トップの経営責任が明らかにされず,社外取締役で経営執行を監視する立場にあった人物が,執行する側に回ったことについては,企業統治という面からは疑問が残る。
小売企業にとって,最も重要なステークホルダーは消費者である。その消費者を無視した投資家や経営者の視点からおこなう買収提案やそれへの対応は,小売企業の存在意義を失わせる。それのみならず,こういった買収提案は,企業統治構造を歪め,かえって投資家を含む株主の利益を損ね,取引業者,加盟店オーナーなど多様なステークホルダーにとって不利益をもたらすことになるといえよう。
関連記事
川邉信雄
-
[No.4105 2025.12.01 ]
-
[No.3968 2025.08.25 ]
-
[No.3620 2024.11.18 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
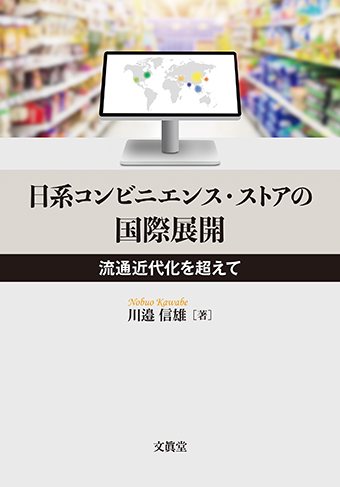 日系コンビニエンス・ストアの国際展開:流通近代化を超えて
本体価格:3,800円+税 2023年5月
日系コンビニエンス・ストアの国際展開:流通近代化を超えて
本体価格:3,800円+税 2023年5月
文眞堂 -
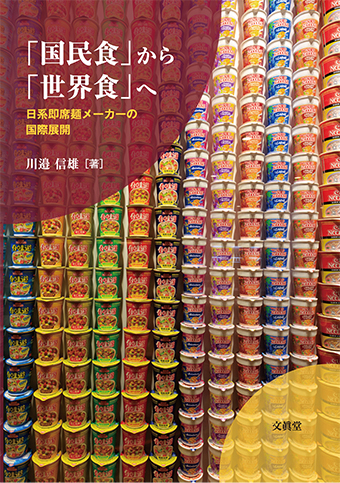 「国民食」から「世界食」へ:日系即席麺メーカーの国際展開
本体価格:2,800円+税 2017年10月
「国民食」から「世界食」へ:日系即席麺メーカーの国際展開
本体価格:2,800円+税 2017年10月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂
