世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
トランプ関税と貿易赤字
(亜細亜大学アジア研究所 特別研究員)
2025.03.24
増加した米国の貿易赤字
第1期トランプ政権が中国に対して最大25%の追加関税をかけた2018年に8,748億ドルだった米国の貿易赤字は2024年に1兆2,022億ドルに増加した。国別にみると,対中貿易赤字は4,195億ドルから2,954億ドルに減少しているが,メキシコは806億ドルから1,718億ドルに912億ドル増加し,ベトナムは395億ドルから1,234億ドルに839億ドル増加している。そのほか増加額の大きい国は台湾509億ドル,韓国460億ドルなどであり,ASEANを合計すると1,284億ドルの増加となる。対中貿易赤字は減少したが,メキシコとベトナムなどアジアの国が代替する形になっている。
FTAの経済効果に関税が削減された国に輸入先が転換する貿易転換効果があるが,中国からの輸入にのみ関税を引き上げるのはFTAと逆の措置(逆FTA)である。そのため,中国からの輸入が減少しASEANやメキシコからの輸入が増加する貿易転換が起きたといえる(注1)。輸入者が追加関税を避けて他の国からの輸入に転換することに加え,中国からメキシコ,ベトナムなどASEAN,台湾などに生産拠点を移したことによる迂回輸出が背景にある。たとえば,ASEANからの製造業投資は2018年の15.6億ドルから2023年の69.6億ドルに4.4倍の増加となっている。中国への追加関税は対中貿易赤字を減少させたが,メキシコやASEANに対する貿易赤字が増加し,米国の貿易赤字は減少していない。なお,第2期トランプ政権で中国に対する追加関税は,2025年2月に10%,3月に10%が課され合計45%となっている(注2)。
2018年には鉄鋼に25%とアルミ製品に10%の追加関税が賦課された。鉄鋼の輸入は2018年に393億ドルから24年は406億ドルに若干増加している。輸出が24億ドル増加し,鉄鋼貿易の赤字額は252億ドルから241億ドルに微減している。世界鉄鋼協会によると鉄鋼の米国国内生産は2017年の8,160万トンから2024年は7,950万トンに減少しており,輸入代替は進んでいない。第2期政権では鉄鋼・アルミ二ウム製品は3月12日から25%の追加関税を全輸入相手国に賦課された。鉄鋼は第1期政権の25%が継続するがアルミ製品は10%から25%に引き上げられ,例外措置が廃止されるとともに対象製品が派生品目にも拡大された。
追加関税による貿易赤字削減は困難
第2期トランプ政権の追加関税は,選挙期間中の発言や検討中のものを含めると,①10-20%のユニバーサル・ベースライン関税,②一律60%の対中関税,③フェンタニルと違法難民流入に対するカナダ,メキシコへの25%追加関税,④フェンタニル流入に対する対中20%追加関税,⑤鉄鋼,アルミ製品に対する25%関税,⑥メキシコから輸入される中国車への100~200%関税,⑦自動車に対する25%関税,⑧EUに対する関税など極めて多様である。4月2日に相互関税などの詳細が発表される予定だが,これらの関税は重層的に適用される可能性がある(注3)。追加関税の目的をみると,①ディールの手段として使われる追加関税,②相手国が高関税を課している品目に同レベルの関税を賦課する相互関税,③国内の製造業への回帰による製造業復活を目的とする関税(自動車など)の3種に分けられる。
相手国に要求を通すための経済的威嚇として使われるディールとして関税が濫用されている。不法移民を乗せた軍用機の着陸を拒否したコロンビアに対する追加関税の脅しは成功したが,フェンタニルの流入防止と違法移民取り締まりを目的とするカナダとメキシコへの25%追加関税は2度にわたり実施が延期されている。2月4日からの発動は1か月停止され3月4日に発動されたが,5日にUSMCAに適合する自動車は1か月の猶予期間が発表され,6日に自動車以外のUSMCA適合品にも4月2日までの猶予が発表された。
中国については2月4日から10%,3月4日には20%に追加関税が引き上げられた。発動延期はメキシコ,カナダからの輸入に2-4割依存する自動車業界の強い反発による。自動車については,1995年の日米自動車貿易摩擦時に米国は対米輸出高級乗用車の関税を2.5%から100%に引き上げるという脅しにより自動車部品輸入を迫り,米国製自動車部品の自主購入と北米での現地生産増加を日本メーカーが発表することになったという前例がある。
相互関税は相手国が高い関税を課す場合米国も高い関税を課すというものだが,対象国,品目,課税方法など具体的な内容は発表されておらず,現在調査が実施されている。米国が赤字を計上している国は多く,ASEANではシンガポール以外は赤字となっている。また,高関税品目もシンガポールとブルネイ以外は多い。そのため,相互関税が課される国および品目は多くなる可能性がある。追加関税が課されると関税分は商品価格に転嫁され国産品の価格も上昇し,インフレを招き金利が引き上げられる可能性がある。米国のような大国が関税を引き上げると外国企業の輸出価格引き下げが起こることがあり,物価への影響も多少抑えられる可能性があるが,相手国が報復関税を課すと米国の輸出を減少させてしまう。
金利が上昇するとドル高となり,米国からの輸出に不利となる。また,高関税賦課で米国への輸入が減少すると外国の輸出者が稼得するドルが減少し,自国通貨と交換するためのドル売りが減少するためにドル高を招き,米国からの輸出を不利にする(注4)。輸出が減少すれば高関税を賦課して輸入が減少しても貿易赤字は減らない。
相互関税は,高い関税をかけると脅し関税を引き下げさせるというディールの手段でもある。相手国が関税を引き下げれば輸出が増える可能性はある。ただし,米国に対してのみ関税を引き下げるのではなくWTO加盟国全体に対して引き下げるため,米国製品に競争力がなければ米国の輸出は増えない。日本の自動車関税はゼロであるが,米国車の日本への輸出は極めて少ない。また,相互関税に対して報復関税が課され,米国に対してのみさらに関税が高くなれば米国からの輸出は難しくなる。
国内製造業は復活するか
国内製造業の復活を目的とする追加関税は,4月2日に発表されるといわれる自動車への関税が代表例である。自動車への追加関税によりメキシコなどからの自動車の輸入は減少し,米国に工場が移転することが期待される。こうした投資誘致のために高関税を設ける保護主義は19世紀末から欧米諸国で導入されており,1960年代以降途上国で輸入代替工業化戦略として採用されてきた(注5)。メキシコやカナダでの自動車生産を米国に移す動きはすでに始まっており(注6),自動車への追加関税が発動されればこうした動きは加速する可能性がある。完成車の組み立ては米国に移転しても部品は輸入が続く可能性が大きい。部品にも追加関税を課すと米国での製造コストが増加するだろう。部品製造も米国に移転すれば部品輸入は減少するが米国の製造コストはメキシコより高いため製造コストは増加する。自動化等の合理化によりコスト削減を図るだろうが,自動車の価格が上昇することは避けられない。また,関税保護下で製造された工業品は価格,品質の面で競争力がないことが多く,輸出は期待できない。輸入に依存しているその他の製造業も米国の優位性が失われており,復活には関税保護が必要となるため高コスト,高価格の製品となる可能性が高い(注7)。
国際ルールを無視するトランプ関税
トランプ関税により米国の貿易赤字を大幅に削減することは期待できない。そもそも2国間の貿易赤字を問題視することや特定品目の貿易赤字を問題視し追加関税で是正しようとすることは合理性に欠けている。自国で効率的に生産できる財を輸出し,効率的に生産できない財は輸入するという国際分業により全体として生産力が高まる国際分業の利益を否定している。
輸入は自国で生産されない財や自国では効率的に生産できない財を供給し国民生活を豊かにするものであり富の流出ではない。米国の国際収支(2023年)をみると,貿易収支は1兆632億ドルの赤字,経常収支は9,054億ドルの赤字に対し,証券投資が1兆1,495億ドルの流入など金融収支は9,241億ドルの流入となっている。
貿易収支は好況時には輸入が増加し不況時には輸出が増加するなど景気変動により変化するし,エネルギーなど資源価格の変化や為替レート変動により変化する。投資貯蓄バランスからみると,経常収支赤字は貯蓄に対する投資超過と財政赤字から説明できる(注8)。経常収支赤字を減らすためには,投資を抑制するか財政赤字を削減する必要があるが,トランプ政権は所得税の減税の延長と恒久化を目指しており,投資抑制も財政赤字削減も期待できず,貿易赤字の解消は不可能である。
特定国に一方的に追加関税を課すことは,GATT時代からの商品貿易の大原則となっている無差別原則であるGATT第1条の最恵国待遇原則に違反している。また,WTO加盟国はWTOで認めた譲許税率以上の関税の賦課は認められておらず(GATT第2条),関税率を譲許税率を超えて一方的に引き上げることは認められていない。また,WTOのパネル(上訴機関)の了承なしに一方的に関税を引き上げることも認められていない(紛争処理了解事項)(注9)。ましてや,デンマークの自治領グリーンランドを米国に譲らなければ高関税を賦課するなどの自国の要求を実現するために経済力や軍事力を背景に関税を賦課することは全く容認できるものではない。
トランプ関税は米国内でインフレを招くだけでなく,相手国が報復関税を導入すれば,第1期と同様な米中貿易戦争が米国と世界各国で起こり世界規模に拡大し,世界経済の成長のマイナス要因となる。日本は,ASEAN,EU,豪州とFTAを締結しており,マルチのFTAとしてRCEP,CPTPPに参加するとともにIPEFでも中核メンバーである。日本はASEAN,EUなどのミドルパワーと連携し,ルールに基づく自由な通商秩序を維持・推進する役割を果たさねばならない。
[注]
- (1)高橋俊樹(2025)「トランプ次期大統領による関税引き上げのアジアへの影響」,ITI コラム144号。
- (2)選挙期間中に中国に対しする一律60%の追加関税賦課は,全品目一律に60%賦課するのか,あるいは25%に追加して賦課するのかなど詳細は不明である。対中追加関税はすでに45%となっており,15%を上乗せすれば60%となる。
- (3)トランプ関税の概要と根拠法,影響と対応などについては,高橋俊樹(2025)「米新政権の日本やIPEFに与える影響と対応」,『IPEFなど米通商政策がビジネス活動に与える影響に関する調査研究』,ITI調査研究シリーズ,No.163,国際貿易投資研究所,が詳細に論じている。
- (4)米国は関税による脅しを使い各国に通貨切り上げを迫るという見方がある。日本経済新聞2025年3月17日付け「歴史を背景に骨太な対策を」。
- (5)カナダでは外資を誘致し,自国の幼稚産業を育成するために高率関税を導入し,米国の3大自動車メーカーが1904年から25年にかけてカナダに進出した。小室程夫(2003)「ゼミナール 国際経済法入門」日本経済新聞社。また,ASEAN主要国は1960年代から70年代に高関税による国内市場保護と外資導入政策を組み合わせた製造業の国産化政策を実施した。その結果,工業製品価格が国際価格を超える「ハイコストエコノミー」に苦しみ,輸入自由化や輸出産業支援により輸入代替型工業化から輸出指向型工業化に転換した。
- (6)日本経済新聞2025年3月5日付け「車産業,コスト9億円増」。
- (7)プロダクト・サイクル・モデルでは,新製品の段階→製品の標準化段階→製品の成熟化段階→輸入段階という段階を辿る。製品の成熟化段階では技術が他国でも利用され大量生産によりコストが低下し,米国での生産の優位性は失われ海外生産が始まる。米国の輸入に依存する製造業は日米貿易摩擦時代から「輸入段階」に入っていた。このプロセスを(アジアの)途上国から捉えたモデルが雁行形態論であり,輸入段階→国内生産→輸出というプロセスを辿って発展する。末廣昭(2000)『キャッチアップ型工業化論』名古屋大学出版会,42~48頁。
- (8)国民総生産=民間消費+民間貯蓄+政府収入,支出面からみると国民総生産=民間消費+民間投資+政府支出+(輸出-輸入),従って,経常収支(輸出-輸入)=(貯蓄-投資)+(政府収入-政府支出)となる。
- (9)畠山襄(1996)『通商交渉 国益を巡るドラマ』日本経済新聞社,104~106頁。
関連記事
石川幸一
-
[No.4120 2025.12.08 ]
-
[No.3957 2025.08.18 ]
-
[No.3856 2025.06.02 ]
最新のコラム
-
New! [No.4149 2025.12.29 ]
-
New! [No.4148 2025.12.29 ]
-
New! [No.4147 2025.12.29 ]
-
New! [No.4146 2025.12.29 ]
-
New! [No.4145 2025.12.29 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
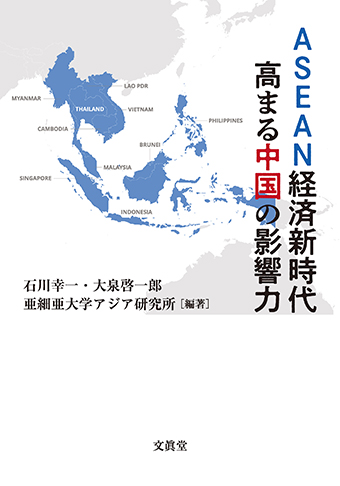 ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
文眞堂 -
 高まる地政学的リスクとアジアの通商秩序:現状と課題、展望
本体価格:2,800円+税 2023年9月
高まる地政学的リスクとアジアの通商秩序:現状と課題、展望
本体価格:2,800円+税 2023年9月
文眞堂 -
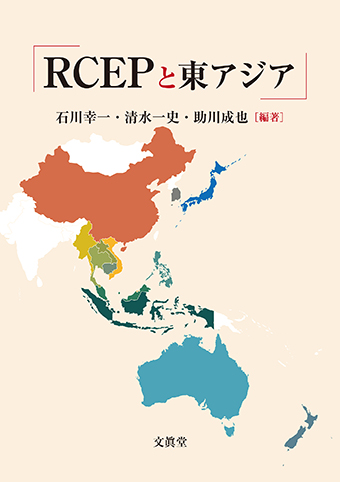 RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂

