世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
第6次エネルギー基本計画に盛り込まれた二つのトリック
(国際大学 副学長・大学院国際経営学研究科 教授)
2022.07.18
2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画には,二つのトリックが盛り込まれている。一つは50年の電源構成見通しに関するトリックであり,いま一つは30年度の総発電電力量見通しについてのトリックである。
第6次エネルギー基本計画は,50年の電源構成見通しについて,複数シナリオの必要性に言及しながらも,ひとまずの「参考値」として,再生可能エネルギー50~60%,水素・アンモニア火力10%,CCUS(二酸化炭素回収・有効利用・貯留)付き火力及び原子力30~40%という数字を示した。また同計画は,30年度の電源構成見通しについては,再生可能エネルギー36~38%,原子力20~22%,水素・アンモニア1%,火力41%,とした。
50年の電源構成見通しについて注目したいのは,政府が,原子力の比率を,CCUS付き火力の比率と一括して30~40%とした点である。この一括視は,明らかに奇妙である。本来,「再生可能エネルギー」/「水素・アンモニア・CCUSによるカーボンフリー火力」/「原子力」と分類すべきだったにもかかわらず,あえて,「再生可能エネルギー」/「水素・アンモニア火力」/「それ以外のカーボンフリー火力と原子力」という3分割を採用した。もし,「原子力」を単独で取り出していたとすれば,現時点で原子力発電のリプレース(建て替え)を避けている以上,50年の電源構成に占める原子力の比率が10%程度にとどまる事実を明らかにしなければならなかったことだろう(原発のリプレースには時間がかかるから,もし21年時点ですぐにリプレースの方針を打ち出したとしても,2050年に間に合う確率は低い)。政府は,原子力施設立地自治体などに配慮して,そのような事実が表面化することを避けたかった。これが,水素・アンモニア以外のカーボンフリー火力(CCUS付き火力)と原子力とを一括するという奇策に出た理由だろう。この奇策が,第1のトリックである。
一方,第6次エネルギー基本計画が打ち出した30年度の電源構成見通しには,大きな問題点がある。それは,再生可能エネルギーと原子力の比率を高めるための帳尻合わせをした結果,総発電電力量を不自然な形で削減することになり,その過程で日本の未来をあやうくする「産業縮小シナリオ」が部分的な形ではあれ導入されてしまったことである。同見通しでは,再生エネルギー36~38%,原子力20~22%という,いずれも実現不可能な高い数値が打ち出された。これらは比率であるから,分子と分母から構成される。しかし,分子の積み上げは困難をきわめた。
再エネについては,第6次エネルギー基本計画策定時に,なんとか30%分までは目算がたっていた。問題はさらに6~8ポイント分を積み増すことであり,その作業は困難をきわめた。
一方,原子力についてみれば,第6次エネルギー基本計画の策定を所轄した資源エネルギー庁(以下,「エネ庁」と表記)は,30年に27基の原子炉が80%の稼働率で動けば「2030年度20~22%」の達成は可能であると主張した。しかし,同じエネ庁は,18年に第5次エネルギー基本計画を策定した際には,「2030年度20~22%」の実現のためには,30基の原子炉が80%の稼働率で動くことが必要だとしていた。つまり,いつのまにか原子力比率の分子は,30基相当分から27基相当分へ,1割ほど削減されたことになる。
分子の積み上げに窮したエネ庁は,帳尻合わせのために,分母を削減するという「奥の手」を繰り出した。30年度の年間総発電電力量を第5次エネルギー基本計画の1兆650億kWhから第6次エネルギー基本計画の9340億kWhへ,12%減らすという策を弄したのである。
分母を1割強削減した結果,分子の積み上げがうまくゆかなくとも,比率は何とかつじつまが合うことになった。「2030年度再エネ36~38%」を掲げることもできたし,分子が1割減ったにもかかわらず分母も1割強縮小したため,「原子力20~22%」を維持することも可能になった。
ただし,ここで,想起すべき事実がある。それは,20年12月にエネ庁が50年度の電源構成見通しについて再エネ50~60%,水素・アンモニア火力10%,CCUS付き火力プラス原子力30~40%という参考値を提示した際,2050年度の総発電電力量を1兆3000億kWh~1兆5000億kWhとし,現状より3~5割増えると見込んだことである。これを受けて,21年5月にこの参考値にもとづくモデル分析の結果を発表したRITE(地球環境産業技術研究機構)は,50年度の総発電量が1兆3500億kWhになるとの見通しを示した。つまり,エネ庁は,電化の進展によって50年度には総発電電力量が現状より3~5割増加するという認識をもちながら,そこまでの中間点である30年度については総発電電力量が1割強減少するという,矛盾に満ちた未来図を描いたことになる。この矛盾が,30年度の電源ミックス策定時の「分母減らし」という,無理な帳尻合わせによってもたらされたことは,言うまでもない。この「分母減らし」こそ,第6次エネルギー基本計画に盛り込まれた第2のトリックである。
エネ庁は,無理な「分母減らし」である総発電電力量削減を合理化するために,「省エネの深掘り」という理屈を持ち出した。確かに,2021年8月にエネ庁が配布した参考資料によれば,深掘りの結果,多くの産業で30年へ向けての省エネ量の見通しは増えた。しかし,最大の二酸化炭素排出産業である鉄鋼業については,深掘りしたにもかかわらず,省エネ量見通しが280万klから174万kl(原油換算値)へ大幅に縮小した。これは,30年度の粗鋼生産量見通しを従来の電源構成見通し策定時(2015年)の1億2000万トンから9000万トンへ,25%も引き下げたからである。同様のケースは,30年度の生産量見通しを2700万トンから2200万トンへ19%縮小した紙・板紙製造業についても,観察された。つまり,今回の帳尻合わせのための総発電電力量削減のプロセスでエネ庁は,「省エネの深掘り」を超えて,「産業縮小シナリオ」に踏み込んだことになる。
このことのもつ意味は重大である。もちろん,30年度のエチレン生産量見通しのように,従来の電源構成見通し策定時の水準(570万トン)を維持したケースもあるから,今のところ,エネ庁による「産業縮小シナリオ」への踏み込みは部分的なものにとどまっている。しかし,第6次エネルギー基本計画に盛り込まれた30年度の電源構成見通しが,産業縮小のきっかけとなる危険性は十分に存在する。
ここまで述べてきたように,第6次エネルギー基本計画には,二つのトリックが盛り込まれている。その他にも同計画は,天然ガスの役割を過小評価するなど,問題が多い。ただちに改定作業に取り掛かり,第7次エネルギー基本計画を策定すべきであろう。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4246 2026.03.09 ]
-
[No.4221 2026.02.23 ]
-
[No.4210 2026.02.16 ]
最新のコラム
-
New! [No.4257 2026.03.09 ]
-
New! [No.4256 2026.03.09 ]
-
New! [No.4255 2026.03.09 ]
-
New! [No.4254 2026.03.09 ]
-
New! [No.4253 2026.03.09 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
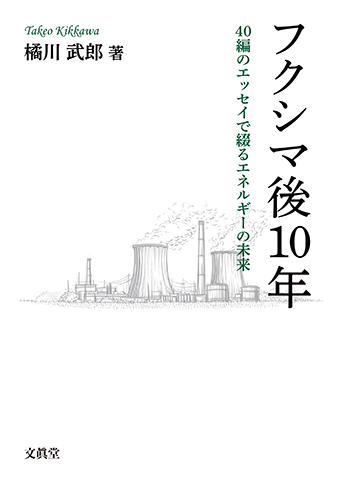 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 貿易実務:新たな研究潮流
本体価格:3,500円+税 2026年1月
貿易実務:新たな研究潮流
本体価格:3,500円+税 2026年1月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 詳説 国際人的資源管理:多国籍企業の人材マネジメントの理論的・実証的研究
本体価格:4,500円+税 2026年1月
詳説 国際人的資源管理:多国籍企業の人材マネジメントの理論的・実証的研究
本体価格:4,500円+税 2026年1月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
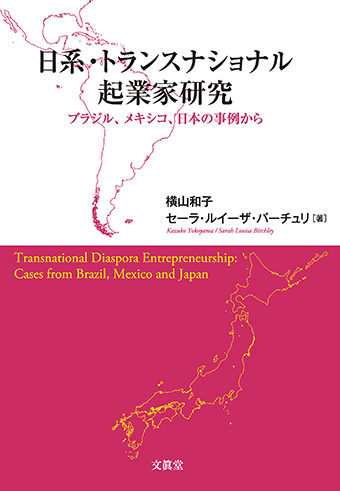 日系・トランスナショナル起業家研究:ブラジル、メキシコ、日本の事例から
本体価格:2,600円+税 2026年2月
日系・トランスナショナル起業家研究:ブラジル、メキシコ、日本の事例から
本体価格:2,600円+税 2026年2月
文眞堂
