世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
カーボンニュートラルへの挑戦とエネルギー産業の立ち位置
(国際大学大学院国際経営学研究科 教授)
2020.12.21
今年の10月,就任後最初の施政方針演説で菅義偉首相は,2050年に国内の温室効果ガスの排出量を「実質ゼロ」にする方針を打ち出した。この「カーボンニュートラル宣言」は,国内外で,サプライズとともに共感を呼んだ。
その直後,11月に行われたアメリカ大統領選挙で民主党のジョセフ・R・バイデン候補が勝利し,新型コロナ対策,経済再建,人種問題への取り組みとともに,気候変動対策を新政権の重点政策とすることを表明した。カーボンニュートラルをめざす動きは,世界中で加速している。
このような流れのなかで,10月中旬には,総合資源エネルギー調査会基本政策分科会が,次期(第6次)エネルギー基本計画の策定作業を開始した。その会合で注目されたのは,出席した梶山弘志経済産業大臣が,まず,50年に温室効果ガス排出量を実質ゼロにするビジョンを明確にし,それをふまえてバックキャストの方法によって30年のエネルギーミックスを定める方針を打ち出したことである。この進め方は,前回,17~18年に,第5次エネルギー基本計画を策定したときの手順と,まったく異なる。
前回は,50年時点での状況について審議するエネルギー情勢懇談会と30年時点での状況について審議する基本政策分科会とが別々に設置され,それぞれの結論が第5次エネルギー基本計画において機械的に合体併記されるにとどまった。その結果,50年の見通しと30年の見通しとのあいだに,深刻な齟齬が生じることになった。第5次エネルギー基本計画は,50年に再生可能エネルギーを主力電源化するとしながらも,30年の電源構成における再生可能エネルギーの比率を上方修正せず,従来どおりの22~24%(パリ協定採択以前の15年に決めた水準)に据え置いたままにした。このことは,単に平仄が合わないという問題だけでなく,政府はそもそも「再生エネ主力電源化」を本気で遂行する気がないのではないかいう疑念を喚起した。
したがって,今回,50年の見通しを明確にしたうえでそれをふまえて30年の見通しを設定するという新手順が明確にされたことは,大きな意味をもつ。そこには,50年カーボンニュートラル方針に対する政府の「本気度」を見てとることができるからである。政府が本気である以上,電力・石油・ガスなどの主要なエネルギー産業は,50年カーボンニュートラルへ向けた具体的なビジョンを明確にせざるをえない状況となった。
50年へ向けたビジョンを比較的打ち出しやすいのは,電力産業である。カーボンニュートラルの実現には電化の進展をともなうから,電力需要の拡大が期待できる。また電力会社は,原子力発電や再生可能エネルギー発電に携わっているから,二酸化炭素を排出しないゼロエミッション電源を有するという強みをもつ。本業の遂行にともない必然的に二酸化炭素を排出せざるをえない石油産業やガス産業とは,事情を異にするのである。
電力業にとっての最大の課題は,火力発電のカーボンニュートラル化にある。再生可能エネルギーが主力電源化すると,太陽光や風力などの変動電源の比率が高まる。蓄電池の大規模開発の見通しが不透明な状況下では,変動電源がもたらす電力系統の不安定化を解消する手立ては,火力発電による出力調整しかない。その調整用電源としての火力発電が,現在と同じように二酸化炭素を排出したままでは,そもそもカーボンニュートラルを達成できるはずがない。そうであるとすれば,火力発電の二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることが,50年カーボンニュートラル化の鍵を握ることになる。
菅首相の施政方針演説の直前にJERAは,50年に二酸化炭素排出量実質ゼロ化をめざす方針を明らかにした。日本最大の火力発電会社であるJERAがカーボンニュートラル方針を表明したため,施政方針演説のリアリティがある程度担保されることになったのである。
JERAは,火力発電用燃料としてアンモニアを使用することによって,カーボンニュートラルを達成しようとしている。当初は火力発電所においてアンモニアを混焼することから始め,徐々にアンモニア専焼に移行しようというのである。このような動きは,他の電力会社のあいだでも広がりつつある。
一方,石油産業は,主要なエネルギー産業のなかで,最も厳しい状況に直面している。石油製品を使用すると二酸化炭素の排出が避けられないという事情のほかに,国内市場における燃料油需要が1999年度をピークにして一貫して減少しているという事情が,存在するからである。苦境に立たされた石油会社は,水素の利活用やCCS(二酸化炭素回収・貯留)の遂行によって,カーボンニュートラルへの道を切り拓こうとしている。そのことは,業界最大手のENEOSが今年10月に発表した『統合レポート2020』からも読み取ることができる。
石油産業ほどの苦境には立たされていないが,電力産業よりは厳しい状況に直面しているのが,ガス産業である。ガス産業に関して注意を要する点は,今から30年までに吹く風と,30年から50年にかけて吹く風とが,180度方向を転換することである。30年までのあいだには,「低炭素化」を実現するために重油や石炭から天然ガスへの燃料転換が進み,ガス産業にとって順風が吹く。しかし,30~50年には,天然ガス使用時の二酸化炭素排出も問題視される「脱炭素化」の時代がおとずれ,ガス産業にも逆風が吹くことになる。30年向けのビジョンと50年向けのビジョンとの関係について言えば,電力産業と石油産業は,それらを直線的,連続的に設定することができる。これに対してガス産業は,30年向けの「低炭素化ビジョン」と50年向けの「脱炭素化ビジョン」とを非連続的に策定することを迫られ,両者のあいだに何らかの方向転換を織り込まざるをえない。カーボンニュートラルの実現へ向けて,50年と30年をどう位置づけ,どう関係づけるか。ガス産業は,この難問に直面している。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4221 2026.02.23 ]
-
[No.4210 2026.02.16 ]
-
[No.4179 2026.01.26 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
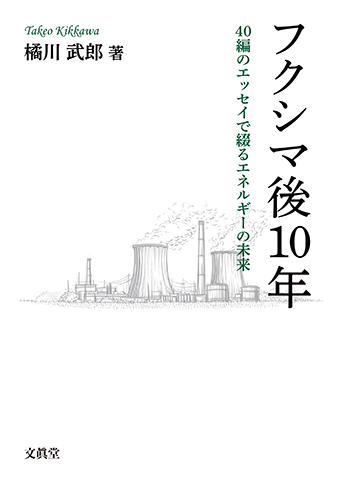 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
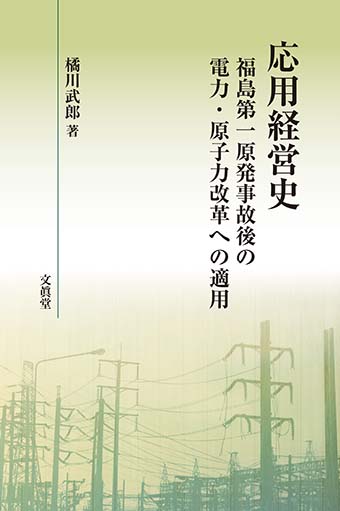 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂
