世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
世界の先頭を走るアイスランドのDACCS
(国際大学 学長)
2025.10.27
2025年8月,(株)ガスエネルギー新聞が主催した欧州視察ツアーに参加して,アイスランドを訪問した。具体的な訪問先は,レイキャビクからバスで1時間ほどの距離に,互いに隣接して立地するクライムワークス(Climeworks)社のマンモス・プラント,へトリスヘイジ地熱発電所,およびカーボフィクス(Carbofix)社の二酸化炭素(CO2)鉱石化プラントである。
スイスに本社を置くクライムワークス社は,世界で初めてDAC(CO2の直接空気回収)を商用化したことで知られる。同社は,まず第1段階として,2017年にスイス国内でkg規模(年間のCO2回収量,以下同様)のパイロット実証を始めた。その後第2段階として,アイスランドで2021年に4000トン規模のオルカ・プラント,2024年に同じくアイスランドで3万6000トン規模のマンモス・プラントを相次いで稼働させ,DACの商用化に成功した。マンモス・プラントへの投資額は,約2億ドルである。
現地を訪れてわかったのは,マンモス・プラントが,稼働を開始したものの,まだ建設中だということである。視察時点での稼働率は,15〜20%程度であった。2026年中の完成を見込んでおり,その時には,オルカ・プラントの実績並みの85%程度の稼働率が期待できると言う。
ツアーでは,マンモス・プラントの諸装置を間近から観察することができた。また,現場では,溶媒を砂状に加工して機能を高めている,空気吸収とCO2回収の効率を上昇させるために装置に工夫を加えている,などの説明があった。
クライムワークス社のマンモス・プラントは,隣接するへトリスヘイジ地熱発電所から,電力,温水,冷水,排熱の供給を受けている。このうち電力は,11kVの地下送電線で送られてくる。
日本では,DACは,まだまだ未来の技術だと考えられている。しかし,この認識は甘い。再生可能エネルギーのうちバイオマスは,風力,水力,太陽光・熱,地熱とは異なり,使用時にCO2を排出する。また,カーボンニュートラル燃料のうち合成メタン(eメタン),合成液体燃料(eフュエル),グリーンLPガスは,水素やアンモニアとは違って,使用時にCO2を排出する。今後,脱炭素に関する社会的要請のレベルが高まると,バイオマス,eメタン,eフュエル,グリーンLPガスを取り扱う事業者は,あわせてDACを遂行することを求められるようになる。これらの事業者は,クライムワークス社および同社のマンモス・プラントの動向から,目を離すわけにはいかないのである。
クライムワークス社のマンモス・プラントに続いて,隣に立地するへトリスヘイジ地熱発電所を見学した。同発電所の出力は,30.3万kW。日本の場合,全地熱発電所の合計出力が約54万kW,最大の地熱発電所である九電みらいエナジーの八丁原(はっちょうばる)発電所の出力が11万kWであることを考えると,へトリスヘイジ地熱発電所がいかに大規模であるかがわかる。電源構成に占める地熱発電の比率は,日本では0.2%にとどまるのに対して,アイスランドでは約30%に達する(ここでの日本に関するデータは,JOGMEC[独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構]「地熱資源情報 日本の地熱発電」による)。
へトリスヘイジ地熱発電所は,発電だけでなく,温水による熱供給も行なっている。発電時に使用する熱水とともに,冷水もあわせて地中から汲み上げ,両者のあいだで熱交換を行なって冷水を温水に変え,それをレイキャビク周辺の工場・住居・商店等に向けてパイプラインで送り出している。温水パイプラインの普及率は,レイキャビクではほぼ100%,アイスランドの全土平均でも約70%に達するそうだ。
このような熱電併給の仕組みを有するからこそ,へトリスヘイジ地熱発電所は,クライムワークス社のマンモス・プラントに対して,電力,温水,冷水,排熱を供給することができる。マンモス・プラントにとってへトリスヘイジ地熱発電所は,無くてはならない存在なのである。
2025年8月の視察ツアーがアイスランドで最後に訪れたのは,やはりへトリスヘイジ地熱発電所のすぐ近くで稼働するカーボフィクス社のCO2鉱石化プラントである。このプラントでは,CO2を水に混ぜて地下の玄武岩の層に埋め,約2年間でCO2の鉱石化に成功しているとの説明を受けた。玄武岩には穴状の部分が多く,そこにCO2が入り込んで鉱石化が促進されると聞いた。
一つ一つのプラントは,白色をしており,大きさも含めて,イヌイットの雪の家であるイグルーにそっくりの形をしている。視察メンバーはイグルー形のプラントの内部に5人ごとのグループに分かれて交代で入り見学したが,CO2と水の配管がそれぞれ地下に延びているだけの極めてシンプルな構造であった。
これらのプラントでは,へトリスヘイジ地熱発電所が操業過程で排出するCO2を使っている。また,近隣にクライムワークス社のマンモス・プラントができてからは,そこで回収されたCO2も使用している。CO2が不足する場合には,スイスから輸入することもあるそうだ。
クライムワークス社のマンモス・プラントで得たCO2をカーボフィクス社のCO2鉱石化プラントが使用しているということは,DACとCCS(CO2回収・貯留)とが結びついて,いわゆる「DACCS」(DAC+CCSの意味の造語)が実行されていることを意味する。現時点でアイスランドは,DACCSの最先進国だと言えるのである。
カーボフィクス社によれば,同社のCO2鉱石化技術を使ってCCSを行えば,貯留期間が永遠化する(長期のモニタリングが不要となる),安全性が高い,地下の浅い場所での貯留ができるなど低コストである,大規模化が可能である,などのメリットが生じる。地下の玄武岩層は日本を含め世界に広く賦存することもあって,同社のCO2鉱石化技術が世界的な注目を集めているのは,これらのメリットが存在するからである。
レイキャビク電力の100%であるカーボフィクス社は,6億ユーロを投じて,アイスランドの国内2ヵ所で同様の事業を展開している。同社の従業員数は,約60名である。
一方で,カーボフィクス社のCO2鉱石化技術には,問題点もある。それは,CO2を迅速かつ永遠に固定化するため,CCU(CO2回収・利用)への道を閉ざしてしまうというデメリットである。将来的にCO2の商品化が進めば,このデメリットがクローズアップされることになるかもしれない。
2025年8月にアイスランドで訪れた三つの施設は,「三位一体」とでも言うべき強い関係性を有していた。この「三位一体」的システムを可能にする地域特性こそが,アイスランドをしてDACCSの世界的フロンティアたらしめている理由だと言えよう。
それにしても驚かされるのは,アイスランドのカーボフィクス社の従業員数が極めて少ないことである。クライムワークス社のマンモス・プラントも,50人でフル稼働させることができると聞いた。同じく2025年8月にフィンランドで訪れたメタネーションの旗手であるノルディックレンガス(Nordic Ren Gas)社の従業員数も,わずか30名に過ぎなかった。小さな会社や小さな事業所が世界を動かす。欧州に息づくそのようなダイナミズムには,改めて驚嘆せざるをえない。
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4179 2026.01.26 ]
-
[No.4158 2026.01.12 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
最新のコラム
-
New! [No.4186 2026.01.26 ]
-
New! [No.4185 2026.01.26 ]
-
New! [No.4184 2026.01.26 ]
-
New! [No.4183 2026.01.26 ]
-
New! [No.4182 2026.01.26 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
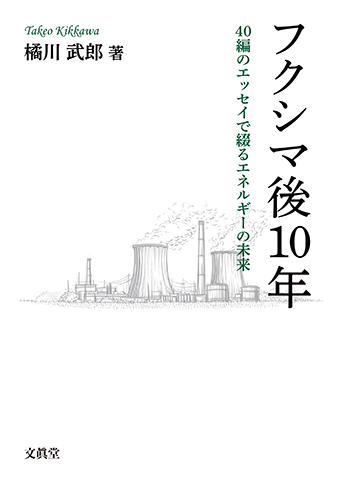 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
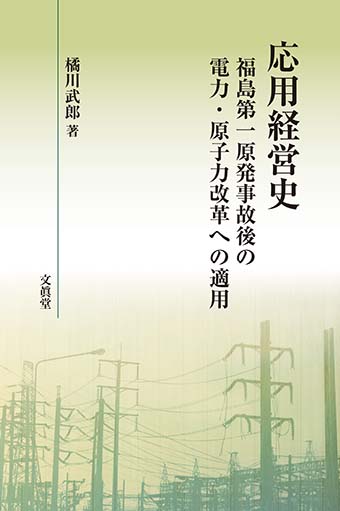 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂

