世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
デンマークの再生可能エネルギー主力電源化と新世代地域熱供給
(東京理科大学大学院経営学研究科 教授)
2019.11.11
2018年8月に続いて19年9月にもデンマークを訪れ,主として地域熱供給(DH)の最新状況について調査する機会があった。ここで,2年分の調査の結果をまとめておこう。
デンマークでのDHの歴史は19世紀末にさかのぼるが,200℃以上(供給温度,以下同様)の蒸気による第1世代(~1930年ごろ),100℃以上の加圧高温水による第2世代(~1980年ごろ),100℃以下の高温水による第3世代(~2020年ごろ)を経て,現在は50℃以下の低温水による第4世代に移行しつつある。時代の進展とともに供給温度が低下しているが,その理由は,①送配熱によるロスを縮小できる,②より多くの種類の排熱・余熱を利用することができる,という2点にある。
1970年代に石油危機が生じたとき,デンマークは中東原油への依存度が高く,エネルギー自給率はきわめて低かった。デンマーク政府は,石油から中東依存度が低い石炭への転換を急ぐ一方,新設する火力発電所はすべてCHP(Combined Heat and Power,熱電併給,日本では「コジェネレーション」と呼ばれることが多い)とする方針をとった。やがて,自国領の北海で原油・天然ガスが発見,開発され,デンマークのエネルギー自給率は改善されることになった。同時に,CHPの増設を通じて熱利用も拡大した。1980年代半ばには,原子力発電所を将来にわたって建設しないことを決めた。90年代半ばごろから風力発電が急伸し,2010年代には太陽光の普及が進んだ。また,デンマークは,周辺諸国との送電連系の構築にも力を入れた。その結果,2018年の電源構成は,風力41%,太陽光3%,バイオマス・廃棄物18%,化石燃料23%,輸入15%となった。エネルギー消費全体で見れば,17年の構成は,再生可能エネルギー33%,バイオマス以外の廃棄物2%,石油38%,天然ガス16%,石炭9%,輸入2%であった。また,このうちの再生可能エネルギーの内訳は,バイオマス55%,風力22%,太陽光6%,バイオガス4%,バイオフュエル4%だった。
デンマーク政府は,2030年までに電源の100%,エネルギー消費全体の55%を再生可能エネルギーで充当する方針を明確にしている。そして50年までに,エネルギー源としての化石燃料の使用を全面的に廃止することをめざす。そのために例えば,今後10年でCHPでの石炭利用を停止する。また,天然ガスのバイオガスへの転換に力を入れている。
デンマークのエネルギー政策の基本は,化石燃料から再生可能エネルギーへの移行を進めること,および電気と熱を効率的に組み合わせることにある。当然,省エネを推進したうえで再生エネに依存することになるが,再生エネの拡大は消費者の負担が増えない形で実現する。しかも,エネルギーの安定供給はきちんと確保する。そんな夢のような仕組みを可能にする大きな要因の一つは,エネルギー媒体としての熱の徹底的な活用だ。
デンマークのエネルギー政策については,「パワー・トゥー・ヒート」という言葉がよく使われる。「電気から熱へ」あるいは「電気を熱の形で蓄える」という意味だが,これによって,柔軟でかつ堅固なエネルギー供給体制の構築が可能なる。電気が足りないときないし電気の市場価格が高いときには,風力だけでなくバイオマスも電力生産に充てる。一方,電気が余っているときには,再生エネで発電した電力を使って温水を作り,それを貯蔵する。その場合,熱需要が高ければ(例えば冬季),バイオマスを発電ではなく熱生産に振り向ける。大まかに言えば,このような仕組みだ。
デンマークの全世帯における熱源の構成比は地域熱供給(DH)が63%,天然ガスが15%,石油が11%,電気等その他が11%であり,コペンハーゲンではじつに98%の世帯にDHの導管がつながっている。火力発電設備のうちの66%がCHPであり,その燃料は59%がバイオマス中心の再生エネ,24%が天然ガス,15%が石炭,その他が2%であるのだ(数値はいずれも2017年実績値)。全国各地に展開するDHの事業主体は自治体で,非営利事業として営まれている。多くはタンク式やプール式などの温水貯蔵施設を擁しており,そのなかには,昼夜間調整だけでなく季節間調整(夏期に貯めた温水を冬季に使う)が可能なものもある。
デンマークでの調査を通じて,二酸化炭素削減の話題があまり登場しなかったのは,やや意外であった。しかし,よくよく考えると,風力を中心に再生可能エネルギーがすでに主力電源化しているこの国では,もはや地球温暖化対策を中心課題とする必要はなくなっているのかもしれない,と思うにいたった。デンマークでは,いわゆる「3E」のうち,環境保全(Environment)よりも,安定供給(Energy Security)や経済効率(Economy)の方が話題にのぼる回数が多かった。再生エネへの転換も,エネルギー自給率の向上やエネルギーコストの低減という文脈で語られていた。
もう一つ,デンマークで印象的だったのは,石炭や天然ガスで時間を稼いで,上手に再生可能エネルギーの時代を切り拓いてきたという経験談を聞けたことであった。このリアルでポジティブな「移行戦略」の素晴らしさこそ,デンマークの「エネルギーシフト」「セクターカップリング」の本質であろう。日本が,最も学ぶべき点でもある。
デンマークで起きていることを,そのまま日本に持ち込むことは,たしかに難しい。しかし,再生可能エネルギーの主力電源化にしろ,温水による新世代熱供給にしろ,その基本的な考え方は,日本にも適用可能である。電力・ガスの小売全面自由化で始まったエネルギー大競争時代を勝ち抜くのは,「熱を制した者」,そして「分散型を制した者」である。デンマークで実装されている次世代エネルギーシステムを組み込んだビジネスモデルを構築した事業者のみが,大競争時代の勝者となりうることを肝に銘じるべきだ。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :アジア・オセアニア
- 地 域 :欧州
- 分 野 :国際経済
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4221 2026.02.23 ]
-
[No.4210 2026.02.16 ]
-
[No.4179 2026.01.26 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
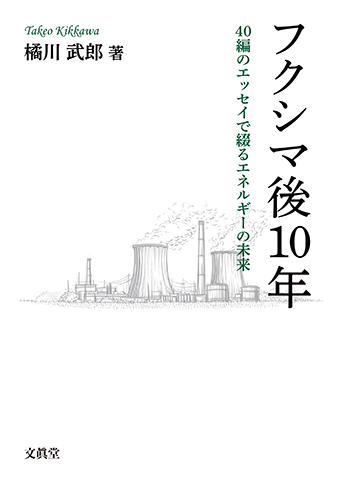 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
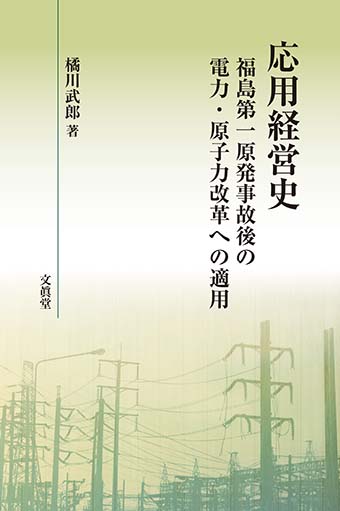 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂
