世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
米国の貿易赤字構造の見直しと世界経済への波紋
(慶應義塾大学 教授)
2025.05.19
トランプ政権は第2期目に入り,長年続いてきた「米国の輸入主導で成り立ってきた世界の貿易構造」の見直しに本格的に取り組み始めている。背景には,米国が抱える巨額の財貿易赤字への根強い不満がある。側近の発言からも,そうした構造変革への意図が読み取れる。
世界経済は,長く米国の旺盛な内需に支えられている。米国は世界中から財を大量輸入し,貿易赤字を資本流入で補ってきた。輸入額は3兆ドル超で,2.5兆ドルの中国,1兆ドルのドイツを大きく上回る。
だが米国は1兆ドル超の世界最大の貿易赤字国である一方,中国とドイツは第1位と第2位の黒字国だ。しかも米国の赤字額は他国を大きく引き離している。
米国の輸入額は世界の13%前後だが,輸出はそれ以下にとどまる。貿易収支は世界全体で均衡するため,米国の恒常的な赤字は他国の黒字と裏表の関係にある。アジアでは域内貿易とサプライチェーンが活発だが,域内全体としては米国への純輸出が大きく,黒字を維持している。
米国の経常赤字の主因は財の貿易赤字であり,1980年代以降は経常赤字が常態化している。これを補う形で,米国には直接投資,証券投資,銀行融資などの資本が流入し,結果として世界最大の純債務国となった。ただし,ドルが基軸通貨であることで,米国は依然として低コストで資金を調達できている。
一方,アジア諸国は貿易黒字を重ね,ドル建て資産を中心に外貨準備を拡大してきた。外貨準備は危機時に通貨防衛や輸入財確保に用いられ,経済安定に寄与する。とりわけ米国債の保有が多く,米国の資本市場の深さや流動性を支えてきた。
多くの国は貿易黒字を通じ,外貨準備や対外資産を蓄積しようとしている。過去の新興国危機の多くが外貨不足に起因したため,資本の流動性が高い中では,一定の外貨準備の確保が安全とされる。
日本は低成長とGDP比240%超の政府債務に直面しているが,2010年までの貿易黒字の累積で得た外貨準備に加え,民間を含む多額の対外純資産により,一定の経済の安定性を維持できている。
ただし,各国が貿易黒字を目指すと,消費を抑えて貯蓄を増やすことになり,内需が弱く外需依存型の構造が定着しやすくなる。米国はこの構造を是正しようとしており,相互関税を発表して,それをテコにして内需拡大と米国からの輸入増を求めて相手国の関税・非関税障壁を下げようと試みている。
さらに,米国に向けて輸出するよりも米国に生産拠点を移して米国内で生産するよう促している。うまくいけば米国の輸入が減って,国内生産と雇用が増え,米国からの輸出も増える可能性もある。
米国は財政赤字の削減を通じて,経常赤字の是正を図ろうとする姿勢も見せている。関税収入も期待できるが,ベッセント財務長官は「手遅れになるまえに財政の持続性を高めるために,現在の財政路線の本格的な転換が必要だ」と議会で指摘している。仮に,その結果,資本流入が減少し,ドルの需要が減ったとしても,ある程度のドル安も容認していく構えである。不均衡是正を目指した強力な手段の一つが輸入関税政策である。
ただし,物価高騰による企業・消費者への負担増が懸念され,景気後退への不安が広がるなか,構造転換の実現性には懐疑的な見方も強い。
支持率が低下する中,トランプ政権は英国と急ぎ交渉合意に至り,中国に対しても90日間限定で追加関税を145%から30%へ大幅に引き下げた。
とはいえ,第1期政権下(2018–19年)で適用された平均20%程度の対中関税が残っており,品目によっては30%を上乗せした50%程度の高関税が維持されることになる。鉄鋼・アルミニウムは従来の25%が倍となり,ガソリン車・ハイブリッド車も2024年に25%に引き上げられた。EVは125%相当と非常に高くなっているとみられる。
つまり,中国製品の輸入価格は2025年に入って段階的に高騰しており,90日間の交渉が不調に終われば再引き上げも起こり得る。不確実性は依然として高い。
日本を含む他国では米中合意により安心感が広がっているが,注意が必要だ。米国の貿易不均衡是正は政策の一貫性をかいており,不透明感が強い。
しかし,仮に米国が今後も構造転換方針を維持していくのであれば,アジアも輸出依存型経済の見直しを迫られよう。世界第2位の経済大国・中国は内需が弱く,米国に代わる需要の受け皿となるのは難しい。
さらに,米国が経常赤字縮小を目指すなら,将来的にドル以外の通貨にも準備通貨機能を分担させる可能性もある。
今後,世界経済は過度な不均衡に依存しない,より持続可能でバランスの取れた成長モデルを模索すべき段階に来ている。その際には,一方的な関税政策ではなく,アジア域内においても内需拡大や経済構造の多様化に向けた政策協議が求められよう。
関連記事
白井さゆり
-
[No.4160 2026.01.12 ]
-
[No.4054 2025.10.27 ]
-
[No.3952 2025.08.18 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
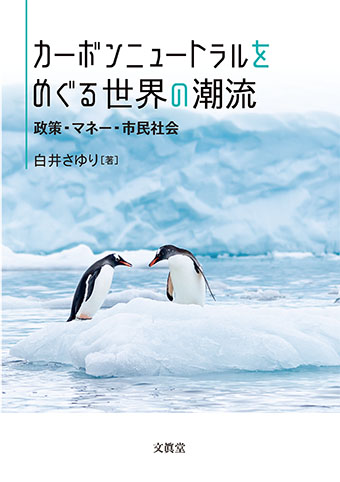 カーボンニュートラルをめぐる世界の潮流:政策・マネー・市民社会
本体価格:2,300円+税 2022年7月
カーボンニュートラルをめぐる世界の潮流:政策・マネー・市民社会
本体価格:2,300円+税 2022年7月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂

