世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
カーボンニュートラル実現後も重要な天然ガス:第7次エネ基「新方針」のインパクト
(国際大学 学長)
2025.05.05
2025年2月,第7次エネルギー基本計画(エネ基)が閣議決定された。この計画でとくに注目されるのは,天然ガスにきわめて高い位置づけを与え,「天然ガスはカーボンニュートラルの実現後も重要なエネルギー源である」と言い切った点である。
第7次エネ基は,同計画書の53頁で,「天然ガスは,熱源として効率性が高く,地政学的リスクも相対的に低く,足下,電源構成の約3割を占める。また,化石燃料の中で温室効果ガスの排出が最も少なく,再生可能エネルギーの調整電源の中心的な役割を果たすと同時に,燃料転換等を通じた天然ガスシフトが進むことで環境負荷低減にも寄与する。さらに,将来的な技術の進展によりガス自体の脱炭素化の実現が見込まれ,水素等の原料としての利用拡大も期待される等,カーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー源である」,と述べている。もちろん,天然ガスからeメタンへの転換(=「ガス自体の脱炭素化の実現」)の重要性にも言及しているものの,この文章の主語はあくまで「天然ガス」それ自体であり,修飾語を加えた述語は「カーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー源である」なのである。
第7次エネ基のこの文章のもつインパクトは大きい。なぜなら,これまでは,日本ガス協会が発表したロードマップにおいても,政府の公式文書(例えば,経済産業省「『トランジションファイナンス』に関するガス分野における技術ロードマップ」,2022年2月)においても,カーボンニュートラルが実現した暁には,天然ガスは使われなくなるという見通しが示されてきたからである。ところが,第7次エネ基はこの見通しを真っ向から否定し,「天然ガスはカーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー源である」とした。「コペルニクス的」とまでは言わないにしても,大きな転換であることには間違いない。
どのようにすれば,カーボンニュートラルの実現と天然ガスの使用継続とは両立するのだろうか。天然ガスが使用時に排出する二酸化炭素を,CCUS(二酸化炭素回収・利用,貯留)やDAC(二酸化炭素の直接空気回収技術)によって回収すれば良い。また,カーボンクレジットによってオフセットすることもできる。その前段で,天然ガスにバイオガスや水素を混入することによって,二酸化炭素排出量を低減することも有用である。もちろん,これらの施策を実施する技術的,制度的条件は,現状では十分には整っていない。しかし,カーボンニュートラルが実現する2050年までには,条件整備が進むだろう。そうなれば,カーボンニュートラルの実現と天然ガスの使用継続とが両立することは可能になるわけである。
とは言うものの,今でも,二酸化炭素と水素からeメタンを製造するメタネーションが,都市ガス産業のカーボンニュートラル施策の主軸であることに,変わりはない。第7次エネ基も,eメタンに対して,高い位置づけを与えている。eメタンが重要な役割を担うことは事実であるが,これまで考えられてきたように,2050年までに都市ガスの90%をeメタン化するほどの措置を講じる必要はない。「天然ガスはカーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー源である」とした第7次エネ基の「新方針」は,このように言っていると読み取れる。
天然ガスに関する第7次エネルギー基本計画の「新方針」は,同計画に盛り込まれたリスクシナリオと密接に関連している。このリスクシナリオは,2040年度までにカーボンニュートラルに資する革新技術の進展が不十分であったケースを想定したものである。同シナリオによれば,2040年度における再エネの電源構成比は35%まで下がり,火力の電源構成比は45%まで上昇する。この再エネ35%という数値は,第6次エネルギー基本計画が2030年度の電源構成見通しで示した再エネ36〜38%より低い。また,火力45%という数値は,第6次エネルギー基本計画が2030年度の電源構成見通しで示した火力42%より高い。
さらに,リスクシナリオによれば,2040年度における一次エネルギー供給の構成比において,天然ガスは26%,石油は28%,石炭は14%を占める。一方,再エネの構成比は21%,水素等の構成比は2%にとどまる。この天然ガス26%という数値は,2022年度における実績値である21%よりも,5ポイントも高い。2040年度には,一次エネルギー供給における天然ガスの構成比が,現在よりも大幅に上昇するという見通しなのである。
リスクシナリオに従えば,2040年度において日本での天然ガスの一次エネルギー供給量は,7400万トン程度に及ぶことになる。2021年に策定された第6次エネルギー基本計画では,字面のうえでは「天然ガスシフト」を掲げながらも,2030年度の天然ガスの一次エネルギー供給量を5500万トン程度と,低く見積もった。2021年度のわが国のLNG(液化天然ガス)輸入量が7146万トンであったことを考慮に入れれば,第6次エネルギー基本計画の「天然ガスシフト」は偽物であったと言わざるをえない。一方,2023年度のわが国のLNG輸入量が6488万トンであったことを考慮に入れれば,リスクシナリオで2040年度7400万トンを打ち出した第7次エネルギー基本計画の「天然ガスシフト」は本物だとみなすことができる。
現在,政府関係者やエネルギー業界関係者のあいだでは,第7次エネ基に関して,ベースシナリオよりもリスクシナリオの方が蓋然性が高いという見方が強まっている。カーボンニュートラル実現後も,天然ガスは使い続けられる可能性が大きいのである。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4179 2026.01.26 ]
-
[No.4158 2026.01.12 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
最新のコラム
-
New! [No.4186 2026.01.26 ]
-
New! [No.4185 2026.01.26 ]
-
New! [No.4184 2026.01.26 ]
-
New! [No.4183 2026.01.26 ]
-
New! [No.4182 2026.01.26 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
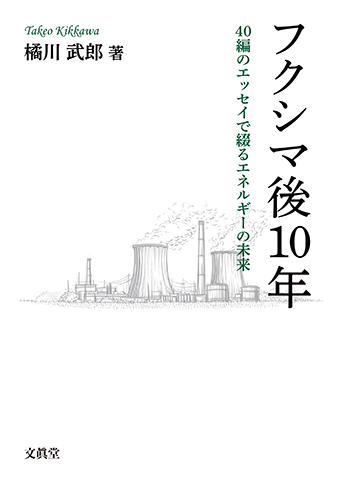 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
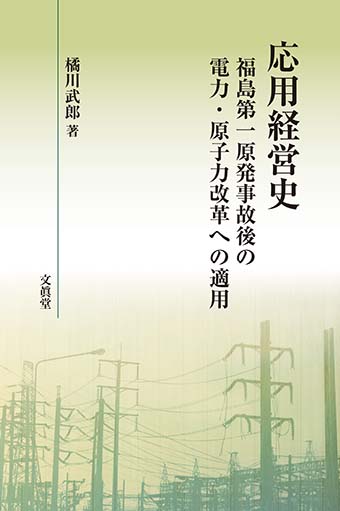 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂

