世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
ゼロエミッション火力へ多彩な技術開発:三菱重工長崎カーボンニュートラルパーク見学記
(国際大学 学長)
2025.09.15
2025年6月,三菱重工業(株)(以下,三菱重工)の長崎カーボンニュートラルパークを見学する機会があった。三菱重工は,ゼロエミッション火力発電へ向けて多彩な技術開発に取り組んでいるが,兵庫県の高砂水素パークでは高効率天然ガスタービン,水素ガスタービン,水素製造技術(長期・大型化実証)の開発に,長崎県の長崎カーボンニュートラルパークではアンモニア・バイオマス混焼ボイラ,CCUS(二酸化炭素回収・利用・貯留),水素製造技術(要素)の開発に,それぞれ取り組んでいる。
今回見学した長崎カーボンニュートラルパークでは,まず,アンモニア混焼試験設備に向かった。アンモニアは,室温(25℃,1メガパスカル)でも液化状態になるため輸送に適している,また,生産・輸送・貯蔵に関して既存のインフラ技術を使用することができる,さらにボイラー・ガスタービン等の燃料として直接燃焼させることも可能で熱分解して水素を製造することができるなどの特徴をもつ。一方で,毒性が強く厳重な管理を必要とする,発熱量が小さく安定着火が難しい,などの難点もある。
日本では,主として石炭火力発電所における混焼用燃料としての需要拡大が見込まれるが,長崎カーボンニュートラルパークでは,2024年度にアンモニア専焼バーナーの開発を完了していた。実際にその試験設備を目の当たりにしたが,今後,石炭火力発電所におけるアンモニア混焼率が高まってゆけば,このバーナーが幅広く使われるに違いないと確信した。また,地球温暖化の原因となる一酸化二窒素(N2O)を含む窒素酸化物(NOx)の抑制にも成果をあげていると聞いた。
続いて,一連の水素製造関連装置を訪れ,SOEC試験設備,AEM水電解試験設備,ターコイズ水素試験設備の順に見学した。水素製造には,①再生可能エネルギーを使って水を電気分解する,②天然ガスを使ってメタン改質ないしメタン熱分解を行う,③原子力を使って水を電気分解したり高温ガス炉で水蒸気を改質したりする,などの方法がある。長崎カーボンニュートラルパークでは,これらのうち①と②にかかわる技術開発を行なっており,SOEC試験設備とAEM水電解試験設備は①に,ターコイズ水素試験設備は②に,それぞれ関係する。
SOEC(Solid Oxide Electrolyzer Cell)は日本語では「固体酸化物形電解セル」と表記される。固体電解質を用いた水の電気分解装置であり,非常に高温かつ高効率で作動する。定置型燃料電池としてエネファーム(家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの愛称)などに幅広く利用されているSOFC(Solid Oxide Fuel Cell:固体酸化物形燃料電池)の逆反応で水素を製造する技術と,みなすことができる。SOECは高出力化が可能で,水素の大規模製造に道を開く。長崎カーボンニュートラルパークでは,三菱重工が有するSOFCセル技術と火力発電技術(蒸気・高温・高圧・伝熱等)との統合技術として,SOECの開発に取り組んでいた。水素の外部調達を必要とせずに合成メタンを生成する革新的メタネーション技術として同じくSOECの開発を進める他社の平板型セルは一部に金属を使用しているが,三菱重工のセルは円筒状のオールセラミクス製である。耐久性に優れ,頑丈である点が,セラミックを使用する理由だそうだ。
AEM(Anion Exchange Membrane)水電解は,アニオン交換膜で高電流密度を実現する技術であり,装置の小型化を可能にする。長崎カーボンニュートラルパークでは,膜電極接合体の設計,気液二相流の制御,面圧の制御,耐久性の評価,水電解システム全体の検証などに力を注いで,技術開発を進めていた。AEM水電解は,アルカリ水電解と比べて電流密度が高いためスタックを小型化し,プロトン交換膜(PEM:Proton Exchange Membrane)水電解に比べて貴金属を使わないためコストを低減できる,との説明を受けた。
「ターコイズ水素」とは,天然ガスの主成分であるメタン(CH4)を熱分解して生成する水素のことである。太陽光や風力などから得たグリーン電力を使って水を電気分解し作る水素は,「グリーン水素」と呼ばれる。グリーン水素は,生成過程で二酸化炭素を排出しない。一方,生成過程で二酸化炭素を排出するものの,その二酸化炭素を回収して再利用ないし貯留する仕組み(CCUS)を有する水素は「ブルー水素」と呼ばれる。ターコイズ水素は,いわばグリーン水素とブルー水素との特性をあわせ持つ存在であり,緑(グリーン)と青(ブルー)との中間色である青緑(ターコイズ)が名称に冠せられているのは,そのためである。
ターコイズ水素の生成に際しては固体炭素が併産されるが,その固体炭素は,化学材料(タイヤやコーティング剤,バッテリーなど)や炭素貯蔵など,多岐の用途がある。長崎カーボンニュートラルパークでは,ターコイズ水素製造工程のバッチ運転から連続運転の切替えに成功しており,建屋内には最新鋭のターコイズ水素製造連続試験設備がりりしく屹立していた。ターコイズ水素には,既存のLNG(液化天然ガス)関連インフラをそのまま活用して大量生産できるという特性があるため,都市ガス業界や電力業界から高い期待が寄せられている。
見学の最後に向かったのは,二酸化炭素回収試験設備である。三菱重工は,1990年代以降,世界のリーディングカンパニーとして,燃焼排ガスから高効率で二酸化炭素を回収する技術をグローバルに提供してきた。アメリカ・テキサス州で稼働する世界最大規模の二酸化炭素回収設備にて使用中の吸収液も,ノルウェーの実証施設で最大99.8%の二酸化炭素回収率を実現した吸収液も,同社が関西電力と共同開発した技術によるものである。その二酸化炭素回収技術開発の主要拠点となっているのが,ほかならぬ長崎カーボンニュートラルパークなのである。
このように,三菱重工長崎カーボンニュートラルパークでは,ゼロエミッション火力発電へ向けての技術開発が「てんこ盛り」の状態で進められている。大いに満腹感を覚えた初夏の一日であった。
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4221 2026.02.23 ]
-
[No.4210 2026.02.16 ]
-
[No.4179 2026.01.26 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
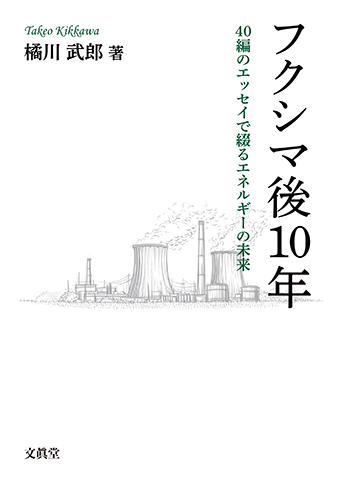 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
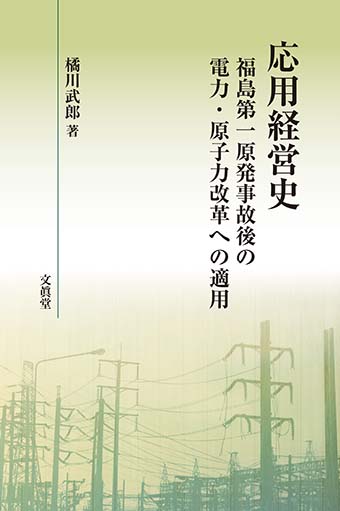 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂
