世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
第7次エネルギー基本計画に欠落した二つの論点
(国際大学 学長)
2025.04.21
2025年2月,第7次エネルギー基本計画(エネ基)が閣議決定された。2025年2月24日に本欄で発信した拙稿「複数シナリオ導入で無意味化:第7次エネルギー基本計画」(『世界経済評論インパクト』No.3734)で書いたように,同計画は,複数シナリオを導入したため,長期的な電源開発や原燃料調達に関する投資判断の目安を民間企業に示すという,基本的な機能を喪失するにいたった。
このように定量的記述では欠陥がある第7次エネ基も,定性的記述に関しては,随所に見るべき内容を含んでいる。LNG(液化天然ガス)の長期的な役割の強調や,LPガス(液化石油ガス)へのrDME(リニューアブル・ジメチルエーテル)の混入などが,それである。ただし,その定性的記述においても,本来言及すべきあった二つの大きな論点が欠落していることは,問題視せざるをえない。
欠落した一つ目の論点は,再エネの事業主体に,地元の住民や関係する当事者を,株主などの形で加えることである。
再エネの普及にとって,地元とのトラブル頻発は,大きな阻害要因となっている。これに対し第7次エネ基は,「事業規律の強化」や「地元理解の促進」を謳っているが,それだけでは決定的に不十分である。再エネ事業を担う主体の構成にまで踏み込まなければ,問題は根本的には解決しないのである。
ここで想起する必要があるのは,世界の風力大手であるデンマークのオルステッドが,当初,住民の反対運動に遭遇して苦労したものの,住民や当事者が出資主体として参加する「市民風車」「漁民風車」方式を導入したところ,状況は一変したという逸話である。再エネ事業の主体を固有の株式会社にし,その株式の一定部分を地元の住民や当事者に配分すれば,住民や当事者に経済的効果をもたらすだけではない。住民・当事者が参画することによって事前から情報のやりとりがきちんと行われるようになり,崖崩れが起きやすい場所へのメガソーラーの設置,景観を損ねたり鳥の通路を邪魔したりする場所への陸上風力の建設,漁場に否定的な影響が出る海域への洋上風力の設置などの事態が回避できるようになるのである。
温泉業者の反対によって普及が進展しない地熱発電に関しても,この方式は,有効であろう。温泉業者が地熱発電の事業主体に加わることによって,温泉業と地熱発電との共生が可能になる。
欠落したもう一つの論点は,既存の原子力発電所で得た電力で水を分解し,カーボンフリー水素の国産化を実現することである。
第7次エネ基では,2040年度における水素・アンモニア火力の比率を示さないなど,水素・アンモニアに関する記述の後退が目立つが,その最大の原因は,基礎的な原料であるグリーン水素のコストが高いことにある。しかし,原子力を使ってカーボンフリー水素を作れば,太陽光や風力に依拠するグリーン水素の場合と異なり,電気分解装置の稼働率を高めることができ,コストを下げることが可能になる。また,海外からの輸入コストも節約でき,エネルギー自給率を高めることにもつながる。さらに,再エネ発電の出力制御を抑制することにもなるのである。
この原子力を使った水素の製造は,次世代革新炉の一角を占める高温ガス炉の社会実装を待たずとも,既存の軽水炉を使って,今すぐにでも実現することができる。2040年度を目標年度とした第7次エネ基は,それまでに間に合わない次世代革新炉の建設だけを強調するのではなく,既設炉によるカーボンフリー水素の製造にも言及すべきだったのである。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4179 2026.01.26 ]
-
[No.4158 2026.01.12 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
最新のコラム
-
New! [No.4186 2026.01.26 ]
-
New! [No.4185 2026.01.26 ]
-
New! [No.4184 2026.01.26 ]
-
New! [No.4183 2026.01.26 ]
-
New! [No.4182 2026.01.26 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
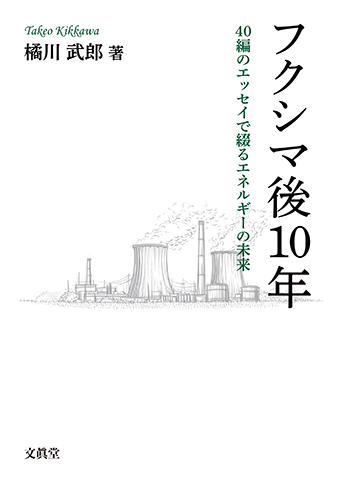 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
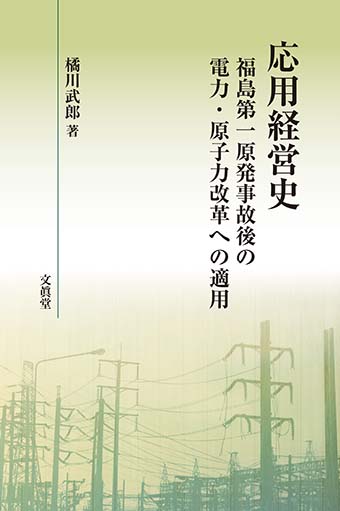 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂

