世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
「相互関税」による米国産業の復活?
(桜美林大学 名誉教授・国際貿易投資研究所 客員研究員)
2025.04.07
その制度の内容を巡って,さまざまな憶測を呼んでいたトランプ大統領の「相互関税(Reciprocal Tariff)」の仕組みが,ようやく明らかになった。トランプ大統領が4月2日発表したその仕組みは,次のようなものである。
- ① まず全世界から米国に輸入される全品目に例外なく一律10%の追加従価関税を賦課する。
- ② 米国が大規模かつ継続的な赤字を記録している67ヵ国には,上記の10%に加えて,従価税による「相互関税」を賦課する。
- ③ 相互関税の税率は品目別ではなく国別に設定し,南アフリカのレソトの50%を筆頭に,カンボジア49%,ラオス48%,ベトナム46%,ミャンマー45%,スリランカ44%,タイ37%,台湾32%と東アジアの小国が高く,大国では中国34%,インド27%,日本24%などとされた。米墨加協定を結んでいるメキシコとカナダは対象から除外された。
- ④ 相互関税率はトランプ大統領が従来から主張しているように,当該国の輸入関税率,非金融的な障壁,およびその他の不正行為を複合したものとされ,経済諮問委員会が計算した。税率の計算式は,USTRが公表した “Reciprocal Tariff Calculations” に書かれているが,4月2日付のニューヨーク・タイムズ(NYT)によると,各国の相互関税率は,〔(米国の当該国との貿易赤字額)÷(米国の当該国からの輸入額)×100〕÷約2〕で求められるという(注1)。
- ⑤ 課税開始日は,一律10%が4月5日,相互関税はその4日後の4月9日とされた(いずれも米国東部夏時間午前零時1分から)。
相互関税に関する大統領令のタイトルは,「米国の年間の物品貿易赤字が大規模かつ継続的に増加している原因となっている貿易慣行を是正するための相互関税で輸入を規制する」という長いもので,しかも全文は段落も少なく,びっしりと書かれ,6ページに及んでいる。経済諮問委員会は,米国の貿易赤字は当該国の不公正貿易慣行と“だまし”(cheating)の総計であるから,これらを相殺する相互関税をかければ,貿易赤字は払拭できるとしている。トランプ大統領が,相互関税を発表した日を,米国に対す諸外国による略奪を終わらせる「解放の日」と命名したのは,この論理による。しかし,米国の当該国との貿易赤字の要因は,決してそれだけではないことは言うまでもない。「解放の日」が,米国の産業にとって新たな発展へのスタートとなる日だと言うのは「空文」に過ぎない。
大統領令でトランプ大統領は,「貿易相手国の不公正貿易慣行が解決され,または緩和されたと,私が判断するまで,相互関税制度を適用する」と書いているが,トランプ大統領が在任する今後の4年弱でそれを実現するのは到底不可能であろう。それよりも,一連のトランプ関税政策によって,米国経済はスタグフレーションに陥り,トランプ政権の維持さえ困難になるとの見方がはっきりしてしてくれば,トランプ大統領の関税政策に変化が起こる可能性の方が高くなる(注2)。
第一生命経済研究所の熊野英生は,「今後,トランプ大統領はどこかでトランプ関税の中断・修正に動くと考えており,そのタイミングは,今年夏以前とみている」(3月31日付「株価急落,トランプ爆弾の炸裂~嵐の先行きをどう読むか?」)。しかし,相互関税実施から3ヵ月後の方向転換は,あまりにも早すぎるし,強硬なトランパーがそうはさせまい。相互関税では,スコット・ベッセント財務長官でも政策を緩和させることに失敗したようだから,閣内の誰も,得意満面のトランプ大統領の首に鈴をつけることは不可能だろう。結局,トランプ大統領自身が方向転換を決断するしかない。その時期は,米国経済の実勢と先行きがより深刻化し,有権者のトランプ離れがさらに進展し,このままでは2026年11月の中間選挙が危ういと考え始めた時であろう(注3)。
我が国はそうした状況を注視しつつ,トランプ関税からの免除や除外を求め続けるのではなく,WTO加盟国として,トランプ政策のルール違反をWTOに訴えることが,まず必要だ。同時に日本は,単独で行動するのではなく,欧州の同盟国および一衣帯水の東アジア諸国と連携,連帯してトランプ政策の撤回に努力することが肝心であろう。
[注]
- (1)NYTは,記事中で,相互関税率を求めるのは極めて困難だから,急いでそれを求めるとすれば政策目標に合わせた近似値ということになるとの元USTR副代表補の発言を引用している(また,英The Economistは4月3日号で,この計算式は馬鹿げていると酷評した)。なお,NYTの写真を見る限りでは,トランプ大統領がホワイトハウスのローズガーデンで発表の際に掲げたボードの国別税率と大統領令の付属書に書かれた税率とは一部違っているようにみえる。
- (2)米国憲法では大統領の任期は2期8年と限定されている(1951年批准された憲法修正22条)が,最近トランプ大統領は2期を越えて在任することも可能だとほのめかしている。これについては稿を改めて報告したい。
- (3)トランプ政権の陰で影響力を発揮していると言われる共和党改革保守派の動向も注目しておきたい。特にAmerican Compass の創始者でチーフエコノミストのOren Cassは,これから議論が本格化するトランプ減税について労働者側に立って忠告している。
関連記事
滝井光夫
-
[No.4141 2025.12.22 ]
-
[No.4109 2025.12.01 ]
-
[No.4030 2025.10.13 ]
最新のコラム
-
New! [No.4209 2026.02.09 ]
-
New! [No.4208 2026.02.09 ]
-
New! [No.4207 2026.02.09 ]
-
New! [No.4206 2026.02.09 ]
-
New! [No.4205 2026.02.09 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
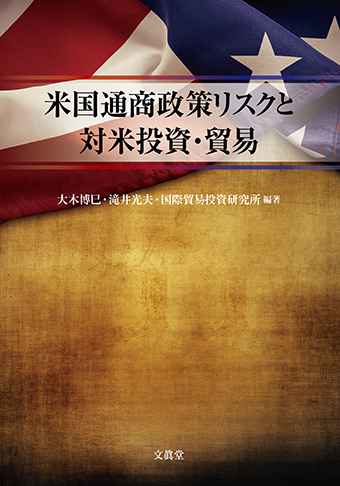 米国通商政策リスクと対米投資・貿易
本体価格:3,000円+税 2018年8月
米国通商政策リスクと対米投資・貿易
本体価格:3,000円+税 2018年8月
文眞堂 -
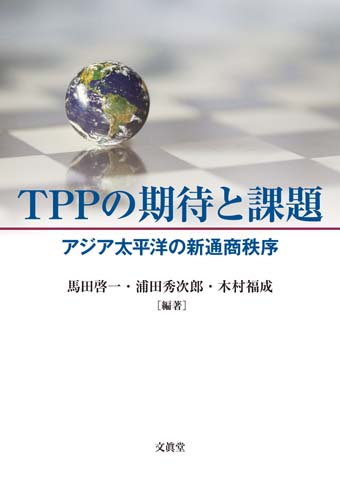 TPPの期待と課題:アジア太平洋の新通商秩序
本体価格:2,750円+税 2016年10月
TPPの期待と課題:アジア太平洋の新通商秩序
本体価格:2,750円+税 2016年10月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂
