世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
報告書で同質組織のハラスメント体質をさらけ出す
(神戸大学大学院経済学研究科 研究員・国際貿易投資研究所 客員研究員)
2025.04.07
フジテレビ(CX)を傘下に持つフジ・メディア・ホールディングス(FMH)の2024年3月期売上高は約5,64億円で,地上波放送局を傘下に持つ上場企業としては日本最大である。全上場企業で売上高は306番目,日本を代表する企業のひとつだ。
第3者委員会報告書に対する評価は高い。公表を受け,関西テレビの大多亮社長(当時CX専務)が4日,辞任した。かつて,俳優を起用するドラマ制作者で,担当番組は当時の若者から指示された。
日本を代表する企業で,なぜ,ハラスメントが起きたのか。言い替えれば,旧ジャニーズ事務所で問われた問題をなぜ,自社で掘り起こせなかったのか。
中居氏によるCX社員の性被害は,報告書で詳細が明らかにされた。故ジャニー喜多川氏による性被害は,国内の週刊誌のほか,2023年3月,イギリスの放送局BBCのドキュメンタリーによって,同年8月29日,旧ジャニーズ事務所の再発防止特別チーム報告書につながった。2023年9月11日の論考で,放送局に加害者はいないのかと問いかけたが,中居氏が旧ジャニーズ事務所出身であることを考えれば,FMHやCXの経営陣に主体性があれば,防げた事案である。なぜなら,中居氏が女性社員を自分のマンションに呼び出したのが2023年6月だからである。経営陣の主体性の欠如についての私の疑問は,取引先との関係よりも,むしろFMX・CX内部で広範にハラスメントが蔓延していたとの報告書指摘で解けていく。ハラスメントは,女性アナウンサーに限らず,バラエティ・ドラマ・映画制作局,報道局・ニュース総局と,番組制作にかかわるすべての部署に及んだ。バラエティ・ドラマが高い視聴率を獲得した1980年代から経営トップの日枝久氏が社長退任後も,長く人事権を握っていた。例えば,亀山千広氏(元CX社長)は「踊る大捜査線」,港浩一氏(前CX社長)は「オールナイトフジ」,大多氏は「東京ラブストーリー」などバラエティ・ドラマ担当者だ。しかも,三氏の出身大学は日枝氏と同じ。男性中心に番組制作部門から取締役が選ばれるなど同質的な組織は,構造的なハラスメント体質,ガバナンスの欠如の原因と言えそうだ。このため,同委員会は,中居氏案件にとどまらず,組織の構造問題の解明に挑んだ。守秘義務があったものの,同委員会は女性社員から守秘義務解除を得た。複数の女性弁護士も加わっている委員会が,被害者から一定の信頼感を得たことになる。
さて,役職者アンケートは2回,それぞれ90%近い回答率で社員の関心の高さ,いや,経営・管理職への不信感を越えて怒りに近いものを感じた。
第1回調査では,ハラスメントを体験の有無について,110人(うち女性43人)があると回答。加害者を問う設問では,1位が「FMH,CX役職員」で101件,2位が「その他」で39件,3位が「広告代理店」で30件,4位が「芸能プロダクション」で23件,5位が「番組出演者」17件である,このほかは,「スポンサー」13件,「制作会社」10件となった。この設問は複数回答と考えられる。被害内容については,1位が「セクハラ」で118件,2位が「パワハラ」で86件である。
さらに,第2回調査で,社内や社外に分けたアンケート調査を実施。「社内で役職員からハラスメントの被害に遭ったことがありますか」。すると,回答数が417人に増えている。第1回の110人の3.8倍だ。解釈は,2月の第1回調査では,同委員会への評価を逡巡し,社内ヒアリングも踏まえて,信頼感が生まれたのだろう。
ハラスメント経験は,バラエティ・ドラマ・映画制作局が45%(うち女性45%),ニュース総局が57%(うち女性43%),報道局が56%(うち女性43%)と,アナウンサーだけではなく,制作現場の問題であることを浮き彫りにした。
具体的事案では,中居氏のほか,石原正人CX常務と反町理CX取締役のハラスメントを明らかにした。反町氏の場合,2006年までさかのぼって報告書に記載されている。報道番組に出演するメインのキャスターでもあり,報告書公表後,番組降板につながった。
報告書は,FMH取締役(常勤監査等委員も含む)及びCXの取締役・常勤監査役の人事は日枝氏が最終決定してきたことや,兼職も含めると役員報酬が会長や社長を上回る年があったことも明らかにした。
最後に,電通によると,テレビは1975年,金額で新聞を上回り,広告媒体の王者になった。だが,2019年,インターネットに抜かれた。NHK放送文化研究所の調査では,購買意欲が高い10代・20代の楽しみは,SNS,インターネット動画,ゲームなどにシフトしており,もはやテレビではない。
報告書への評価の高さは,ハラスメント体質をさらけ出したことである。構造問題のため,信頼回復にはかなりの時間がかかる。
トランプ政権など不透明ななかで,製造業,サービス業問わず,国内,海外での新たな市場獲得に腐心している。
スポンサーが拙速にCXに広告出稿すると,視聴者・株主も含め忌避的な行動が出るリスクがある。企業は視聴率以外の世論調査(世代別の政党支持率など)も参考に社会の動向を慎重に見極めたい。
関連記事
小原篤次
-
New! [No.4224 2026.02.23 ]
-
[No.4196 2026.02.09 ]
-
[No.4172 2026.01.19 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
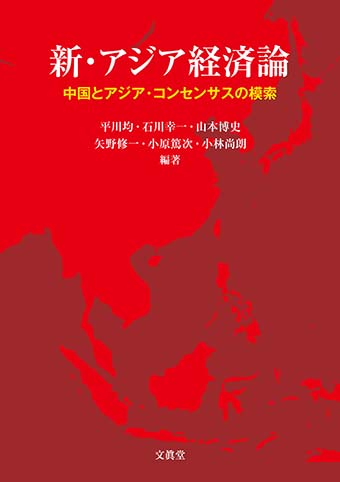 新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂
