世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
都心部の集積 スピルオーバーの行方
(国際貿易投資研究所 客員研究員・元帝京大学 教授)
2023.04.17
コロナ・パンデミクの収束が見え始め,コロナ前への復帰が希望的観測として語られることが多くなってきた。しかし労働や資本や技術の「分断」は資本主義としてどこまで可能なのか。
まず第1にウクライナ戦争も手伝い,世界的なサプライチェーンの分断が語られることが多いが,テレワークやデジタル,AIビジネスなどによって多分,資本主義は労働と資本が始めて分離するようになったのか。前掲の本コラムでもこのような供給の寸断のことを通商白書が「分解」(unbundling)と呼んでいることにも言及した。資本と経営は,産業革命以降,大量生産体制の出現によって株式会社を通じて経営と所有の分離が生じた。しかし現場では,株式所有の分散の高度化によって経営に専従するホワイト・カラーという階層を生み出した。中間管理職以上に照準を当てたドラッカーの組織論やコースの内部化理論,あるいはポーターの競争優位の戦略論がグローバル化のなかで風靡した。しかしここにきてOECDなどが注目してきた都心部のCBD(セントラル・ビジネス・ディストリクト)モデルなどの企業集積論は,テレワーク比率やオフィス空室率の上昇傾向の定着によって,コロナ前への復帰という守旧派の希望的観測を裏切りつつある。
第2に経営と所有を分離することで,広範な資金調達が可能となり,人材も幅広く登用できる。その結果,多様な事業展開を効率的に進めるなどのメリットが生まれる。しかしながら高度で戦略的な世界戦略に関わる意思決定は米国のソーングレン(Thorngren)らの言う通り,対面の突き合わせを従前以上に集積の拠点で行うことが肝要であるとされている。英国のアルフレッド・マーシャルが産業集積の「雰囲気」は移転できないと言った言葉は有名である。集積とスピルオーバーの効果は,グローバル化の2000年代,あるいは日本ではアベノミクスの時代に危機の出口戦略の有力な政策ツールとしてもてはやされた。満杯のコップの水が外側に滴りこぼれるように,経済活動の空間的密度の高さは経済成長の追加的な波及に結びついていくものとされた。第1に企業内部ではフェイス・トウ・フェイスのコンタクトを通し相乗効果が創出される。人と人が接触し合うことによって創造されるプラスアルファのカフェテリア効果である。第2に多数の産業・業種の企業が集積するとき,①同一集積業種の地域特化が形成され,また②異業種の企業が集積による異業種交流が形成される。集積の経済外部性が全要素生産性の技術進歩とてしてインプットされていくようになる。
21世紀の資本主義は世界の多国籍企業が目論む戦略的なグローバルな都市においては,多くの国籍の人々が異文化交流を通じてハイブリッドな雑種の創造的都市空間が醸成され,形成されていく。ジャック・アタリが「新たなユートピア~博愛」,カナダのリチャード・フロリダが「創造都市」(creative city)というそれぞれの著書の中で,このように遊牧民族ノマードのごとく彷徨し,諸文明,諸文化が集積し,接触し合うような都市こそ成長・発展していくと説いている。
第3に都市集積論には過密コンパクト都市としての神話と現実がある。世界銀行は日本で言う3密に相当する3Ds,すなわち,高密度(higher density),近距離(shorter distance),非分散(fewer divisions)は収穫逓増につながる経済外部性を創出する経済成長に不可欠な経済空間であると新経済地理学路線に沿って説明されてきた。世界的にも国内的のみならず,国際的にも産業クラスター間の提携協力関係が推奨されきたことはまだ記憶に新しい。
しかしコロナ・パンデミクは,2重の意味でこのような期待と希望を打ち砕いてしまった。経済的相乗効果についてはパンデミク誘発リスクによって叶わぬ夢となってしまった。そして感染リスクの実態については,郊外田園都市や,農村と都市の間,あるいはこれまでの世界地図にすぐに現れてこないような場所,例えば中国の武漢とかイタリアのロンバルディア州ベルガモ市のようなところで深刻であった。巨大な逆説である。それは従来の都市の概念が変化し,むしろ都市の周辺部が人の移動の場所として人々が体を接触し合うという現代都市圏の特徴のひとつである郊外の田園都市地帯などであることが実証されたのである。感染クラスターの存在が1平方キロメートル当りの人口密度でなく個人と個人の間の身体的近さこそ重視されるべきであるという,実は単純な論理的帰結に人間は気づかなかったのである。
第4にカナダ・トロント都市圏のオンタリオ湖畔にグーグル・グループのサイドウォーク・ラボ社(Sidewalk Labs)が2017年に5,000万ドル規模のウォーター・フロント再開発プロジェクト(12エーカー,約48,500平方メートル,東京ドーム5個分)を発表。木造の高層ビル群からなるスマート・シティ構想をトロントの住民に約束した。しかし,都市生活最適化を謳いながらも新技術の実験データ収集,市街地自動運転,キャッシュレス決済,遠隔医療・教育,ドローン配達などは結局,人々の願いとは掛け離れた未来物語で,新しい商品を売りたい企業と低コストで人々を管理するために住民が使われる「監視社会のディストピア」であると告発するビアンカ・ウィリ(Bianca Whyly)などの市民の反対運動がその本末転倒を見抜きこの都市開発は拒否されたのである。
集積についての新たな条件と制約の登場によって,今やコンパクト性に影響を与える「人口密度」の概念がロンドン経済学大学院都市研究センター(LSE Cities)などで真剣に再検討されるようになってきた。人口密度は確かに都市の構造と都市空間の効率性を計測する有力な方法であるが,その定義とされる「1平方キロメートルに24時間の時間帯に算出される住民の数。100平方キロメートルの地域空間を対象に24時間における住宅街の立地,職場の位置,旅程(トリップ),移動などの経済社会的データを都市のビジネス・ライフの空間的な水準」を把握するためにその空間の占有利用“occupation” した状態が人口密度であるとする考えが台頭しつつある。
関連記事
瀬藤澄彦
-
[No.4208 2026.02.09 ]
-
[No.4151 2026.01.12 ]
-
[No.4139 2025.12.22 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
文眞堂 -
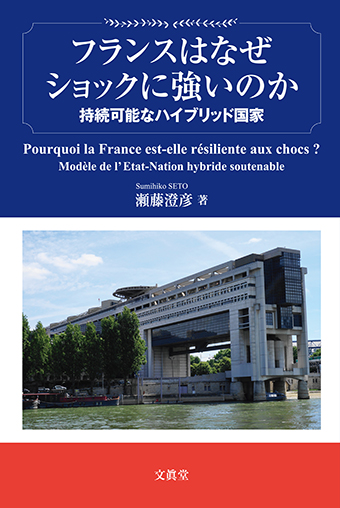 フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂
