世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
既存資源の組み合わせによるイノベーション:陸上養殖における事業創造
2023.01.23
水産業界でのデシタル化が急激に進んでいる。とくに養殖事業分野での技術は加速度的な進化を遂げている。その技術の一つが陸上養殖である。海上養殖の場合,天候,海水温,赤潮などの自然界の不確実性要因に生産性が左右される。しかし,陸上養殖の場合は,陸上に建設した施設で養殖が行われるため,外部環境の不確実要因をかなりコントロールすることが可能になる。その陸上養殖には,「かけ流し式」と「閉鎖循環式」の大きく二つに分けることができる。
「かけ流し式」は,海や川,地下水などを取水・排水して養殖を行う方法である。それに対して,「閉鎖循環式」は飼育水をろ過システムで浄化,循環し繰り返し使いながら養殖を行う方法である。閉鎖循環方式の方が,水質管理をより人為的にコントロールすることが可能になるだけではなく,環境負荷の影響も軽減することができる。さらには,トレサービリテイの観点からも優れている。しかし,施設の投資や維持に膨大なコストがかかることになり,大きな参入障壁となる。実際,閉鎖循環方式で陸上養殖事業に参入している企業は,資本力のある大手の水産企業や商社などが多い。
将来的にも発展可能性の高い陸上養殖事業ではあるが,中小・ベンチャー企業が簡単に参入できるわけではない。たとえ大企業からの資本や技術提供を受けても,事業創造に向けてのさまざまな壁を打ち破る必要が出てくる。この陸上養殖事業に立ちはだかる壁を次々に突破し,設立からすぐに事業を軌道に乗せたベンチャー企業がある。大阪に拠点を置く株式会社陸水(以下,陸水)である。
2021年に創業し,わずか2年で大阪サーモンというブランドの認知度を高め,急成長を遂げている。この急成長を可能にしたのが立地の優位性である。大阪の漁港の近くに生産拠点を構えることで市場と生産の距離を縮め,競合他社よりも養殖魚の鮮度という点で,圧倒的な差別化を実現している。つまり,陸水のビジネスモデルは,消費地により近い場所で養殖できるという陸上養殖の最大のメリットを活かしている。陸上養殖の方式も,設備投資とランニングコストが大きな負担となる閉鎖循環方式ではなく,掛け流し方式を選択している。
このような市場ベースのビジネスモデルを構築できた要因は,陸水の養殖技術の捉え方にある。陸水では,日本の陸上養殖の技術は世界的にみてもかなり高度なレベルに達していると認識していた。そのため,陸上養殖をいち早く事業的に軌道に乗せるには,輸送費のコスト削減と魚の鮮度を維持することが,いちばんのポイントであると考えた。換言するならば,市場創造のネックがどこにあるかを見極めたとも言える。
技術が世界的なレベルに達していると考えたため,陸水では既存の資源や技術を活用することで市場創造に取り組んだ。例えば,既存の使用されていない漁港の設備を利用することで,陸上養殖事業の最大の参入障壁である設備投資の課題を乗り越えている。設備だけではなく,技術も地下水から汲み上げて海水を紫外線で殺菌するという既存の技術を利用することで,生け簀のマネジメントを行っている。
市場の壁の突破にも既存の資源が活用されている。社長の奈須悠記が,大手企業時代に培った市場のネットワークを活用し,顧客からの受注生産をベースにすることで,全量正規価格で商品を市場に流通させている。しかも,大手企業のようにサーモンなどの単一の魚種に絞り込むのではなく,市場のニーズと季節に合わせて柔軟に養殖する魚種を変えている。また,予想以上に市場の需要がある場合は,他の養殖事業者から魚を調達して販売するという商社的な機能を有することで,年間需要に対応している。まさに川上から川下まで,内部資源と外部資源をうまく連動することで独自性を創り出し,養殖事業にあるさまざまな壁を乗り越え急成長を遂げてきたのである。
陸水の事業創造から学ぶべきことは,必ずしも最新のデジタル技術に拘っていないということである。そもそも,養殖事業は暗黙知な部分が多い産業である。そのため,デジタル化によって経験や勘の部分をできるだけなくすことが,生産の効率性を高める鍵であると言われてきた。しかし,陸水の事例をみれば,やみくもにデジタル化を進めることが必ずしも経営的には正解とは言えないことがわかる。というのも,養殖事業の場合,既存のモノの生産と違い,デシタル化が著しく進化したとても,常に魚とのコミュニケーションスキルが重要になるからである。集団で泳ぐ魚の場合,違った泳ぎ方をする1匹の魚の見つけることで,魚病の感染リスクなどを押さえ込むことができる。依然として経験や勘が活きる産業であり,モノづくりの生産とは異なる。
確かに,デジタル化は養殖事業の効率性につながることは間違いない。しかし,地方の中小企業が多い養殖業界にとって,各企業が自社の立ち位置を考えずに,デジタル化への投資を進めることは,必ずしも成果に結びつくものではない。その意味で,陸水の事例は,改めてデジタル化の進化を,企業の目指すべき成長規模や,既存の強みとどのように組み合わせるかを教えてくれる事例と言えるであろう。
[謝辞]
- (株)陸水の事例を作成するにあたっては,奈須悠記氏(代表取締役社長)に貴重な情報を提供して頂いた。ここに記して感謝の意を表したい。
関連記事
髙井 透
-
[No.2642 2022.08.22 ]
-
[No.2288 2021.09.20 ]
-
[No.1967 2020.12.07 ]
最新のコラム
-
New! [No.4257 2026.03.09 ]
-
New! [No.4256 2026.03.09 ]
-
New! [No.4255 2026.03.09 ]
-
New! [No.4254 2026.03.09 ]
-
New! [No.4253 2026.03.09 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 パーソナルファイナンス研究の新しい地平
本体価格:4,200円+税 2017年11月
パーソナルファイナンス研究の新しい地平
本体価格:4,200円+税 2017年11月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 日本における異文化適応力(CQ)の効果に関する実証分析
本体価格:3,500円+税 2026年2月
日本における異文化適応力(CQ)の効果に関する実証分析
本体価格:3,500円+税 2026年2月
文眞堂 -
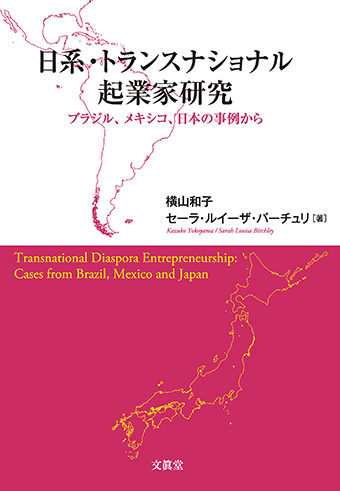 日系・トランスナショナル起業家研究:ブラジル、メキシコ、日本の事例から
本体価格:2,600円+税 2026年2月
日系・トランスナショナル起業家研究:ブラジル、メキシコ、日本の事例から
本体価格:2,600円+税 2026年2月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 詳説 国際人的資源管理:多国籍企業の人材マネジメントの理論的・実証的研究
本体価格:4,500円+税 2026年1月
詳説 国際人的資源管理:多国籍企業の人材マネジメントの理論的・実証的研究
本体価格:4,500円+税 2026年1月
文眞堂
