世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
絶対的貧困線と相対的貧困線の収斂は可能か
(青山学院大学経済学部 教授)
2022.08.01
6年前の本コラムの拙稿「貧困線の設定は政治的地雷原?」では,OECD諸国が使用する「相対的貧困線」が貧困概念と不平等(格差)概念の混同を引き起こしていると主張した。コロナ禍を経て日本における貧困論議が再燃しているなかで,前稿の考察を多少前進させたい。
再度確認しておくが,発展途上国一般で使用されている「絶対的貧困線」は,貧困家計が生きていくのに最低限必要な食糧支出額(食糧貧困線)に衣・住の生活必需品への支出額を加えた支出総額として設定される。この絶対的貧困線を購買力平価でドル換算して加重平均し,世界の貧困者を数える目安として求めたものが「国際貧困線」である。世界銀行が中心となって考案したこの国際貧困線は,当初の1985年価格で1人当たり1日1ドルから,2011年価格では1日1.9ドルに上昇したが,これは貧困国全体の物価上昇にスライドしたもので,各国の所得水準の増減に直接影響されない。
一方,OECDが定義する「相対的貧困線」は,当該国の中位所得世帯の「等価」可処分所得額(可処分所得を世帯人数の平方根で割り1人あたりに調整)の半額というもので,これは各国の所得水準の増減に直接的に依存し,例えばある国の中位所得がある期間に2倍(あるいは半分)になれば,その国の相対的貧困線も2倍(あるいは半分)になる。その半面,当該国の所得分布(ローレンツ曲線の形状)に変化がなければ,所得水準とそれに依存する相対的貧困線がいかに変動しようとも,相対的貧困「率」はまったく変化せず,逆に所得移転政策の強化を政治的に実現できさえすれば(ローレンツ曲線の左下側を45度線に近づけることができれば),相対的貧困の削減はいくらでも可能となる(撲滅は不可能だが)。
したがって,相対的貧困率は,貧困指標というよりは「所得最上位5分位の国民所得シェアの最下位5分位のシェアに対する比率」といった指標に類する不平等指標として認識すべきだと筆者は考える。
OECDの現加盟38国と加盟協議中の6カ国を含む44ヵ国の相対的貧困率をみると,2019年データで上位ランキングはブラジル21.5%,コスタリカ19.9%,米国18.0%,ブルガリア17.6%,イスラエル17.3%,ルーマニア17.0%,チリ16.5%,韓国16.3%,ラトビア16.2%,メキシコ15.9%,日本15.7%などとなっている。日本は第11位と上位4分の1に属するが,これをもって「日本は貧困大国だ」と大雑把な主張するのには反対である。
日本の相対的貧困率は1985~2015年の期間で6年ごとに12.0%,13.5%,14.6%,14.9%,16.0%,15.7%と推移した。これをもって「この30年間で日本の貧困状況は深刻化した」という解釈よりは「日本の所得移転機能が衰退し,可処分所得分布が悪化した」という解釈のほうが正確だと考える。
絶対的貧困を削減するための「ターゲッティング」政策については実証研究の蓄積があるが,相対的貧困を減らすためのターゲッティングという話は聞いたことがない。後者に対する一般的処方箋が資産や所得に対する累進的課税政策の強化だとすれば,相対的貧困は「貧困問題」ではなく「不平等問題」(格差問題)として議論すべきだろう。もちろん母子家庭,低学歴若年者,低収入単身高齢者など低所得に固定されやすい層は存在するが,それらは絶対的貧困予備軍として所得移転プログラムをターゲティングすればよい。
さて,絶対的貧困対相対的貧困の議論は,世界銀行エコノミストとして貧困分析をリードしてきたMartin Ravallionがその著書『貧困の経済学The Economics of Poverty』(日本語訳2018年,日本評論社)の第7.4節「世界全体の貧困」で詳しく論じている。
そのなかでRavallionは「貧困をどう見るかは発展途上地域でも変わりつつあり,例えば2011年に中国は貧困線を1日90セントから1.8ドルへと2倍にした(2005年購買力平価換算)。30年ほどで平均所得が4倍になったことからすれば,中国が貧困線を実質値で高めたことになる。コロンビア,インド,メキシコ,ペルー,ベトナムなどの諸国も,近年に同様の変更を行った。…この根底には絶対的貧困の定義に,相対欠乏,恥ずかしさ,社会排除といった関心事が配慮されない不満があった。…」と,発展途上国においても社会包摂の意識が高まり,貧困線に相対的要素が混入している事実を指摘する。しかし,その一方で,OECDが使用する,中央値の一定割合に定められる「強い意味」での相対的貧困線を途上国に適用するのは不適切だと断じている。
そこで,「2つの世界のどちらにも適切であるように,相対貧困の通常の見方を変えることが求められる」とし,Ravallionは収斂案として「弱い意味」での相対的貧困線を提唱する。その一案は,国際貧困線(絶対基準)に[当該国の所得調査の中央値と国際貧困線値の差]に2分の1のウェイトを付けて加算する,というものである。この換算式を適用すると,世界全体として貧困線の平均は2008年で1人あたり1日5.88ドルとなる。所得グループ間で比べると高所得国の平均貧困線は同23ドルと,途上国平均同2.9ドルの8倍になる。これでも「2つの世界」における貧困線の乖離は依然として大きいものの,途上国における現状の絶対水準1日1.9ドルと,例えば日本の相対水準の1日約36ドル(2009年の厚生労働省データ「年間125万円」を同年平均為替レートで換算)を比べた19倍よりは乖離が縮小する。
残念ながら,今のところRavallionが提示するような収斂案が広く議論されている様子を筆者の見聞の限りでは観察しておらず,当面,2つの世界の平行線は継続しているもようである。
関連記事
藤村 学
-
[No.4230 2026.02.23 ]
-
[No.4119 2025.12.08 ]
-
[No.3862 2025.06.09 ]
最新のコラム
-
New! [No.4257 2026.03.09 ]
-
New! [No.4256 2026.03.09 ]
-
New! [No.4255 2026.03.09 ]
-
New! [No.4254 2026.03.09 ]
-
New! [No.4253 2026.03.09 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
文眞堂 -
 アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済:最後のフロンティアの成長戦略
本体価格:3,200円+税 2019年12月
アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済:最後のフロンティアの成長戦略
本体価格:3,200円+税 2019年12月
文眞堂 -
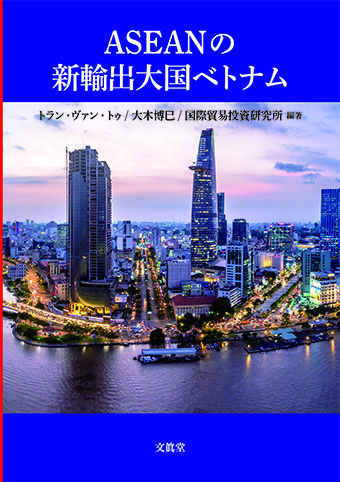 ASEANの新輸出大国ベトナム
本体価格:3,000円+税 2018年12月
ASEANの新輸出大国ベトナム
本体価格:3,000円+税 2018年12月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
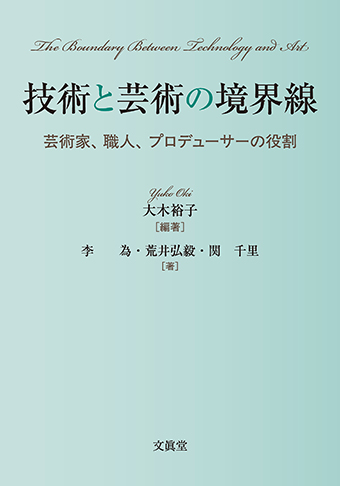 技術と芸術の境界線:芸術家、職人、プロデューサーの役割
本体価格:4,000円+税 2026年2月
技術と芸術の境界線:芸術家、職人、プロデューサーの役割
本体価格:4,000円+税 2026年2月
文眞堂 -
 日本における異文化適応力(CQ)の効果に関する実証分析
本体価格:3,500円+税 2026年2月
日本における異文化適応力(CQ)の効果に関する実証分析
本体価格:3,500円+税 2026年2月
文眞堂 -
 貿易実務:新たな研究潮流
本体価格:3,500円+税 2026年1月
貿易実務:新たな研究潮流
本体価格:3,500円+税 2026年1月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂
