世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
新型コロナ・ウィルス時代における都市計画:コンパクトシティの終焉?
(帝京大学 元教授)
2020.05.25
存在理由問われるコンパクト・シティ論
世界の都市はそのあり方,そのモデル,そのパラダイムの大きな変化の時代に入った。新型コロナウィルス・パンデミックの全世界的発生は,ここ30年間余り推進されてきたコンパクト・シティという都市計画モデルに見直しを迫っている。
スプロール化現象と呼ばれる都市郊外の延伸的拡大現象のマイナス面を克服する都市政策としてコンパクト・シティがOECDなどの支援を背景に米国を中心に多くの国で採用されてきた。2000年代に入りインターネットのIoT化によってコンパクト・シティは,先端技術ネットワークを利用して産業インフラと生活インフラを効率よく管理運営,環境に配慮でき生活の質を高める持続可能なエコシステムを目指すスマート・シティとしてドイツなどを筆頭に導入されてきた。そして次いで,AIやビッグデータ活用しながらこれまでの多くの成長戦略を包括的に連携させる未来都市のショーケースのための共通プラットフォーム作りとなるスーパー・シティ構想が,例えばトロントなどでは批判も多いが,グーグルが主導して立ち上げられるようにまでなった。しかし今,このコンパクトで集積度の高い都市空間がコロナ・ウィルス疫病の感染拡大の前にその存在理由を失いつつある。機能や人口密度の高さは,多国籍企業の立地や先端的な産業クラスターの集積にもつながる競争優位を象徴するものでもあった。都市は水平でなく高層建築タワーのように垂直に成長することを志向してきた。
コンパクト・シティの欠点については,空間の狭隘化,都心部の交通渋滞,住宅難,生活の質の悪化,都市の温暖化,エネルギー多消費などがすぐに指摘される。さらに高密度の地区は地震,津波,洪水,火災などの自然災害に見舞われる可能性が高い。さらに気候変動にも影響されるであろう。従ってコンパク・シティを構築するにあたっては都市の脆弱性を克服し,自然災害と人災によるリスクに対して耐久力のある都市として事前の防災政策の周到な配慮が欠かせなくなった。しかしこのような高密度の都市ではさらに,糖尿病,気管支炎,高血圧,心臓病,肥満病など人体への悪影響が明らかになってきたことが物語るように,今回の新型コロナ・ウィルス病原菌は都市化の著しい人口密の高い空間ほどウィルスの感染が高いことが感染者数,死亡者数などのデータでも多いことが裏付けられた。これまでの自然災害でもテロでも大事故でも難民でもないこの疫病は社会科学,なかんずく近代経済学の経済成長論や経営学の競争優位モデルに大きな試練を課している。これまでの回帰分析の説明変数や内生的経済成長論の全要素生産性でも取り込むことができていないのである。
「創造的復興」(Build Back Better)という考え
さてわが国では「コロナ後」,欧米では「COVID-19後の世界」という論調が増えているが,ユネスコや世界銀行ではすでに復興防災という観点から「BBB」(Build Back Better than before)という考えのなかで社会的な包括的受容性,デジタル革命,持続可能な開発など耐性力を一段と強靭にしていくことが求められている。
国際連合災害リスク防止局の定義する耐性力とは,都市の基本構造や機能を十分に維持しながら都市としての共同体が迅速に効率的に災禍の悪影響に抵抗,吸収し,さらに災害前よりも強靭な形で復興し立ち直ることのできるシステムである。国連防災機関(UNDRR: United Nations Office for Disaster Risk Reduction)は第3回世界会議(仙台)で今後,次の災害に備えて気候変動と防災管理に関連した都市の耐性力ある強靭な地域づくりに焦点を当てる必要があるとした。2030年までの国連持続発展目標では新たな都市アジェンダとして持続可能な環境と耐性力,すなわち“レジリエント(resilient)”のある都市開発に重点を置いているが,明らかに耐性力の役割に力点を絞るようになってきた。専門家の間ではこの耐性力についてショックやストレスに耐えるシステムと,個別のそうしたケースに対処するものとに区別することが多い。これらはどちらかというと定量的な側面への取り組みであり,そこに現実の方向性との間にずれがある。それは持続可能でない都市の新陳代謝モデルあるいは社会的不平等,そして細菌感染パンデミックのような人災などを包含するかどうかのことから来ている。
新たな都市計画の動き
米国では80年代,90年代から「ニュー・アーバニズム」と呼ぶ都市デザイン論が存在する。新都市主義とも言えるこの考えは実は伝統回帰的な都市計画で電車や鉄道を基点に商業施設や住宅がその周りを取り囲むというモデルである。西海岸のポートランド,フロリダ州のシーサイドの都市づくりがその事例である。ブラジルのクリチバ市は建築家で市長だったJ.レルネル(Jaime Lerner)が高密度でバスの公共交通と歩行者を優先する都市づくりでTOD(公共交通指向型都市開発)を先行した事例がよく知られている。英国では「アーバン・ビリッジ」と呼ばれ多くの階層の混在する持続可能なコミュニティ形成を目指して,住民参加と公共交通を利用する職住接近を目指す都市づくりである。英国でもコンパクト・シティ論は「アーバン・ルネサンス」計画に大きな影響を与え,ロンドンの都市計画にも選択的に簡略化されて実践されてきた。しかしロンドンでは性急なコンパクト化論には都市計画専門家と開発業者の癒着や金銭主義のために本当の都市のニーズや課題に答えていないという批判がなされている。これが巨額な投資にも拘わらず市民の住みやすい街づくりにつながっていないというのである。フランスでは2000年代以降,SCOT(Schéma de cohérence territorial)と呼ぶ広域統合都市計画が推進されている。しかしグラン・パリ・メトロール(MGP)となづけられたパリ首都圏の広域都市計画も思惑通りに進んでいない。21世紀は「都市の世紀」(Guillaume Faburel)であるとも言われるが,今,その真価が問われようとしている。
関連記事
瀬藤澄彦
-
[No.4208 2026.02.09 ]
-
[No.4151 2026.01.12 ]
-
[No.4139 2025.12.22 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
文眞堂 -
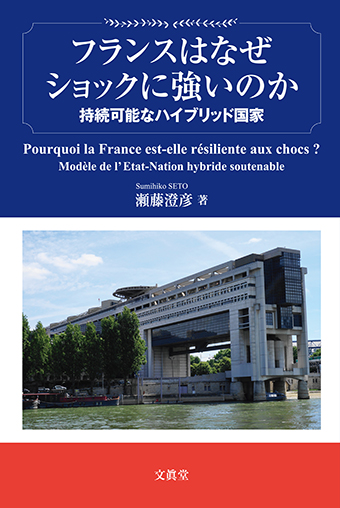 フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂
