世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
室蘭市のGXへのユニークな取組み
(国際大学 学長)
2025.01.20
水素の低圧低コスト配送と洋上風力用SEP船の基地港化
2024年10月,北海道室蘭市を訪れる機会があった。北海道では,石狩市・札幌市・千歳市・苫小牧市・室蘭市という「J字」状に並ぶ各市が,それぞれ違ったアプローチでGX(グリーントランスフォーメーション)に取り組んでおり,社会的な注目を集めている。
これらのうち室蘭市についてみれば,二つの特徴的な動きがある。水素吸蔵合金を使った低圧低コストの配送システムを確立する動きと,洋上風力のSEP船(自己昇降式作業台船)の基地港となる動きが,それである。
このうち前者の正式名称は「既存のガス配送網を活用した小規模需要家向け低圧水素配送モデル構築・実証事業」であり,環境省の「既存のインフラを活用した水素供給低コスト化に向けたモデル構築・実証事業」に採択されている。多くの企業や大学が参加しているが,世話役をつとめるのは,室蘭ガスと室蘭市である。
この実証事業では,次の4点を重視している。第1は,再生可能エネルギーの変動に追従した水素製造である。同事業では,水の電気分解により水素を得るが,電源となるのは,近隣にある室蘭市所有の祝津(しゅくづ)風力発電所(出力1000kW)である。同発電所の稼働率は40%と,陸上風力としてはかなり高いが,それでも風任せの変動電源であることには変わりはない。その変動に追従しながら,蓄電池等を使わず水素製造を行うことによって,コストを抑制しているのである。祝津風力発電所を間近から見上げたが,小ぶりながら,力強く羽根(ブレード)を回転させていた。
第2は,既存のLPガス配送網を活用した水素配送である。水素吸蔵合金を使って水素を高さ1mほどの特殊なボンベ(スリムな円筒形の“MH:メタルハイドライド”タンク)に注入し,通常のLPガスボンベと混載して中型トラックで低圧配送する。水素パイプラインはもとより,液化水素専用ローリーなども使わないため,高圧ガス保安法等の規制対象にならず,配送コストの低廉化が実現されるわけである。MHタンクは,地元室蘭に立地する日本製鋼所M&E製である。まさに,室蘭ならではのプロジェクトだと言える。
第3は,水素利用システムの多様化である。水素吸蔵合金を使ったMHタンクの配送先は,一般住宅(室蘭工業大学職員宿舎),ロードヒーティング(室蘭テクノセンター駐車場),小規模店舗(道の駅みたら室蘭の「くじら食堂」),宿泊施設(室蘭ユースホステル),金属加工工場(楢崎製作所)と,多彩である。このうちの「くじら食堂」で給湯用に水素が使われている様子を見学したが,同食堂がある「道の駅みたら室蘭」の入口には,この実証事業全体の内容をわかりやすく伝える掲示板が設置されている。見学したのは24年10月上旬であるが,同年4月の実証開始から約5ヵ月のあいだに,合計822本のMHタンクを配送し,約3万キログラムの二酸化炭素排出量を削減したと,その掲示板は伝えていた。
第4は,副生酸素の有効利用である。水を電気分解すれば,水素とともに酸素が生成される。水分を多く含む酸素である。その有効利用として最適なのは,魚類の養殖である。じつは,この実証事業の中核装置である水電解装置,MHタンク充填装置,副生酸素回収装置などはみな,市立室蘭水族館に隣接する市有地に設置されている。そこから副生酸素は隣の水族館に送られ,養殖用に使われる。実証事業の経済性向上に貢献しているのである。
GXの柱の一つである水素・アンモニアの供給拠点形成レースで,水素は,アンモニアに押され気味である。アンモニアの場合には,それを混焼することにより二酸化炭素排出量の削減をめざす石炭火力発電所という明確なオフテーカー(買い手)が存在するのに対して,水素の場合には,はっきりとしたオフテーカーが見当たらない。22年にGXが始まった当初は,液化水素などを使う大規模プロジェクトが脚光を浴びたが,そのほとんどは後退を余儀なくされた。ここに来て,急浮上してきたのが,小規模だが堅実で,地に足のついた水素利用プロジェクトである。室蘭ガス等が取り組む実証事業は,その典型とも言える。他都市への波及も含めて,今後の広がりに期待したい。
今回の室蘭訪問では,室蘭港の崎守(さきもり)埠頭で,SEP船の「柏鶴(はっかく)」を目の当たりにすることができた。SEP船は,洋上風力発電所の建設・メンテナンスに携わる自己昇降式作業台船であり,見学したときには,自分の脚(支柱)で少し上昇した状態にあり,埠頭からも船底を覗くことができた。
しばしば「港なくして洋上風力なし」と言われるように,SEP船の基地港は,洋上風力プロジェクトにとって死命を制する重要な意味をもつ。室蘭港は,もともと,水深が十分あり,内湾に立地するため波浪が穏やかな天然の良港である。それだけではなく,風力発電の風車等の巨大な部材を扱える固い地盤と広いヤード(作業場)を擁し,近隣にはメンテナンス等の際に活躍する有力な金属・機械メーカーが多数存在する。これほど,SEP船の基地港としての好条件が揃う場所は,日本広しといえども,あまりないのである。
室蘭港は,石狩沖や秋田沖などのいわゆる「洋上風力の銀座」からは少し離れている。しかし,この程度の距離は問題ではない。欧州最大級のSEP船基地港であるデンマークのエスビアウ港は,ユトランド半島の西岸に位置し,同国周辺の洋上風力集積地とはやや離れた位置にある。船は海上を容易に移動できるのである。
吸蔵合金を使った水素の低圧低コスト配送と洋上風力に不可欠なSEP船の基地港化という2点で,室蘭は,GXへ向けてユニークな道を歩む。今後の展開に注目したい。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国際ビジネス
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4221 2026.02.23 ]
-
[No.4210 2026.02.16 ]
-
[No.4179 2026.01.26 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
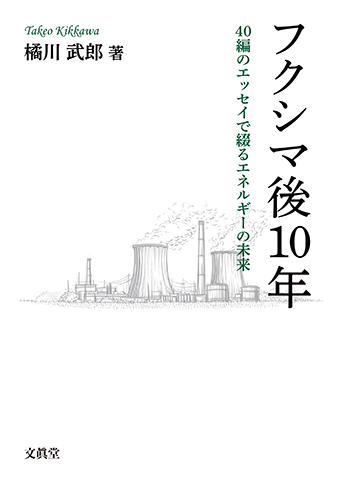 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
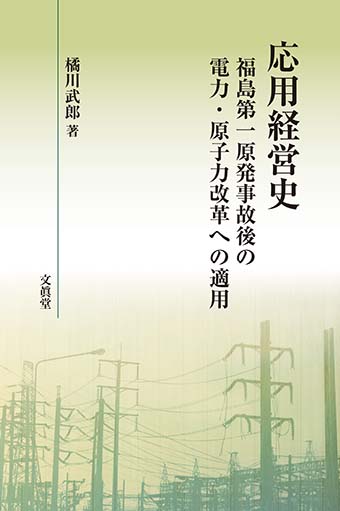 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂
