世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
賃金や物価が失業率の水準に感応しなくなった時
(帝京大学 元教授)
2022.02.28
2021年後半以降,インフレの足音が次第に大きくなり,世界のエコノミストの間ではこの展望を巡って議論が日々,沸騰している。来るべき次の局面に移行する論点は何なのか。
賃金・物価上昇率と失業率のトレード・オフの相関関係,フィリップ曲線のことが日本では表舞台から議論に出なくなってしまった。あれ程,待ちわびていた2%インフレ目標に向かうデフレ経済からの脱却が,ほとんどあっという間に本当に実現してしまうのだろうか。2%物価上昇率は言わば,リーマンショック以降のテーラー・ルールからその妥当性を与えられた米欧日の中央銀行の金利水準の世界的な指標であった。中央銀行の決定していく金利である名目金利は長い間,米国FRDや欧州中央銀行(ECB)の政策金利として現実と目標のインフレ率と,現実と潜在GDP,この両者の乖離,需給ギャップを勘案したものであった。2%はECB,FRB,日銀の3中央銀行主導の異次元金融政策体制の象徴的な期待インフレ率であった。確かに2010年代を支配していたモジリアーニ流のニューケインズ主義的な,当時のイエ―レン,ドラギのMITグループに黒田総裁も加わったケインズ色のある新古典派総合の登場によって「世界経済危機は終わった」といみじくも論じた慶応大学・竹森俊平教授の指摘は記憶にまだ焼き付いている。その潮が変わろうとしているのか。
当時の議論では失業率はNAIRU(Non accelerationg inflation Rate of Unemployment)というインフレ加速にならない上限の雇用水準であった。インフレ率が目標とする率を上回り,実質成長率が潜在成長率を上回るときは引き上げるという政策金利の考えが,米国連邦準備理事会だけでなく欧州中央銀行,日銀でも取り入れられた。アベノミクスはこの考え方に基づき,日銀はインフレ目標を掲げてデフレ脱却を図ろうとした。しかし1970年代のように失業率と物価上昇率は思惑通りに動いてこなかった。
20年にはコロナ禍が各国のマクロ経済状況に大きく影響するようになった。米国と程度はやや少ないがスペインとイタリアの失業率は確かに大きく上昇したが,仏独英日の失業率には大きな変化は見られない。それどころか21年には米国も欧州や日本同様,10%以下の失業率に雇用情勢は推移している。要するに賃金や物価は失業率の水準に感応しなくなっていた。
それでは一体,労働市場に何が起こっているのであろうか。今,注目すべきとされているのは,「大離職」(great resignation),「ビッグ・クイット」(Big Quit),フランス語で「グランド・デミッション」(grande démission)などと呼ばれる大量の離職者の発生である。この名付け親である米国テキサス大学経営心理学者であるアンソニー・クロツ(Anthony Klotz)教授によれば,ひとびとは,増えない賃金,テレワークの定着,生計費の上昇,コロナ対策救済措置,コロナ疫病からの逃避,仕事上の不満蓄積,などによって労働市場から退出している。この現象を労働者の一種のゼネストであるさえ見なすエコノミストもいる。昨年末時点で米国,英国ではそれぞれ380万人,450万人,ドイツやフランスで21年半ば頃より毎月数10万の単位で無期限雇用の正規労働者が退職するようになってきた。この大規模な新たな自発的な失業者たちの登場は深刻な熟練労働者不足を惹起するようになった。欧州では向こう10年にかけて数百万人の良質な労働力が確保できる見通しは容易ではなくなったとされている。しかし同時にこの影響は欧州の中東欧も含めた周辺国には深刻な「頭脳流出」とさえ言われる深刻な熟練労働者不足を招き経済発展の桎梏になり始めている。人材の確保は極端に難しくなっている。ギリシャ,ルーマニア,チェコ,ポルトガル,スペインなどの国では賃金など雇用条件を引き上げても人材の採用は容易でない。今や高等教育も受け職業上のキャリアもある有能な労働者は「失業」状態を自ら選ぶ時代になった。長いコロナ禍は世界のひとびとの生活様式を確実に変えつつある。フランスの報道によれば賃金や報酬の少々の低さより自分自身の人生設計を重視するようになった。
米国の賃金上昇の理由も,新型コロナの感染拡大とともに離職率が急上昇,離職者数300万にも達するなど労働市場の逼迫がある。そして,この背景にあるひとつの有力な要因として「ベビーブーマー世代の大量引退」があり,もう働かなくてもいいという豊かな世帯がラフスタイルそのものを見直しているのだ。良質な労働者の不足が深刻化して賃金上昇だけが定着するリスクが心配されている。米国は21年,楽観と悲観が交錯した。NYTimesの論説でP.クルーグマンは次のように言う。「一方で失業の減少,他方でここ10年来の高いインフレ率が発生した。ここで2つの問題。深刻な失業でない状態で低いインフレ率は可能だったのか。あるいは低いインフレ率のためには緩やかな雇用の回復の方がベターだったのか」と。クルーグマン自身は前者でなく後者であると述べる。コロナ・パンデミックの災禍のなかで21年度来の経済政策は「ゴルディロックス」(Goldilocks)と形容される「適温」であったと評価されている。その背景として米国では需要の方は対面サービス接触を恐れて飲食消費を回避し,その代わりにコロナ前の20%以上も耐久所費財の消費が選好された。サプライチェーンはその購買の前に厳しい局面に立たされた。配達遅延の急増による「シッパゲドン」“物流終末現象”(shipageddon)は結局起こらなかった。世帯援助カットや金利引上げによる個人消費支出の抑制によってサービス財価格を圧縮していたのでインフレ率はより低位だった。
このような新たな労働市場の動きは,企業,即ち資本の側の都合で就業機会を奪う失業はあくまで非自発的であるとするケインズ経済学のこれまでの公準を根底から覆すものである。あまつさえ賃金等の雇用条件は下方硬直的でなく高水準の厚遇条件にも関わらずである。これはまたマネタリストの「非自発的失業を減らすケインズ政策はインフレを助長し不安定要因になる」としてきた70年代以降の米国金融政策の議論に大きな影響を与えるはずである。長期的にインフレ率に関係なく存在する自然失業率,あるいは完全雇用でも産業構造・技術進歩・高齢化・社会保障など社会経済の構造要因で不可避な失業率を論じるフリードマンのフィリップ曲線は垂直であるという議論が優勢になるかもしれない。
[参考文献]
- 竹森俊平著,『世界経済危機は終わった』日本経済新聞出版社 2014年
- PAUL KRUGMAN The Economic Case for Goldilocks Jan. 6, 2022 NY Times
- Simon Wren-Lewis Mainly Macro, Why are interest rates on the rise in the UK and US ? University of Oxford, Monday, 7 February 2022
関連記事
瀬藤澄彦
-
[No.4208 2026.02.09 ]
-
[No.4151 2026.01.12 ]
-
[No.4139 2025.12.22 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
文眞堂 -
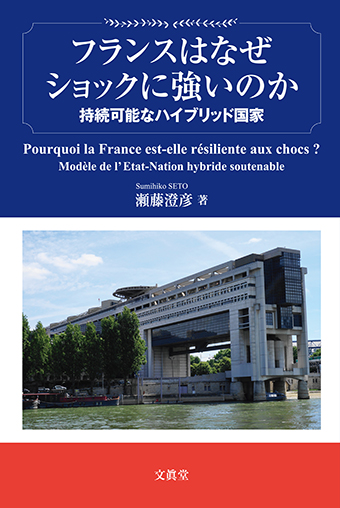 フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂
