世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
福島事故から10年:副次電源化しつつある原子力
(国際大学大学院国際経営学研究科 教授)
2021.03.15
2011年3月に発生した東京電力・福島第一原子力発電所事故から,10年の歳月が経過した。事故当時,日本には54基の発電用原子炉が存在し,ほかに3基が建設中であった。21年3月11日までにこれら57基のうち21基の廃炉が決まった。一方,12年に発足した原子力規制委員会の許可を受け,同時点までに再稼働までこぎつけた炉は9基にとどまる。今後,わが国の原子力発電はどのような道をたどるのだろうか。
20年9月,安倍晋三に代わって総理大臣に就任した菅義偉は,翌10月,最初の所信表明演説で,2050年に国内の温室効果ガスの排出量を「実質ゼロ」にする方針を打ち出した。同じ20年10月には,総合資源エネルギー調査会基本政策分科会(以下では,「基本政策分科会」と略す)が,次期(第6次)エネルギー基本計画の策定作業を開始した。政府は,同年12月に開かれた基本政策分科会において,あくまで議論を深めていくための「参考値」としながらも,2050年の電源ミックスについて,「再生可能エネルギー5~6割,水素・アンモニア火力1割,その他のカーボンフリー火力および原子力3~4割」とする目安を示した。再生エネ主力電源化の具体的なあり方を,一応,明示したことになる。
菅首相のカーボンニュートラル宣言を受けて,原子力推進派のあいだには,ゼロ・エミッション電源である原子力発電にも追い風が吹くという「希望的観測」が広がっている。しかし,この見方は「期待はずれ」に終わるだろう。なぜなら,菅首相も梶山経産相も,原発のリプレース(建て替え)を含む新増設を避ける姿勢を崩していないからである。
たしかに政府が20年12月に打ち出したグリーン成長戦略では,成長が期待される14産業のなかに原子力産業を含め,SMR(小型炉)など新型炉の開発に取り組むとしている。しかし,新増設を回避したままでは,技術開発には着手するものの,新型炉が実用化されることはないということになる。社会的実装を想定しない新型炉は「絵に描いた餅」の域を出ないわけであり,「原子力産業=成長産業」という見立ては「絵空事」だと言わざるをえないのである。
2018年に閣議決定した第5次エネルギー基本計画で原子力を「脱炭素化の選択肢」にするとしながら政府は,これまで,原子力のリプレースに関して言及を避ける方針をとってきた。リプレースには30年近い歳月を要するから,今,問題提起しなければ,2030年はおろか2050年にも間に合わない。そうであるにもかかわらず,リプレースへの言及を回避している背景には,原子力についてはできる限りことを荒立てず,問題の「先送り」を決め込むという,政治家や官僚の思惑がある。
日本の原子力開発は,「国策民営方式」で進められてきた。福島第一原子力発電所事故のあと,事故を起こした当事者である東京電力が,福島の被災住民に深く謝罪し,ゼロベースで出直すのは,当然のことである。ただし,それだけではすまないはずである。国策として原発を推進してきた以上,関係する政治家や官僚も,同様にゼロベースで出直すべきである。しかし,彼らは,それを避けたかった。そこで思いついたのが,「叩かれる側から叩く側に回る」という作戦である。
この作戦は,東京電力を「悪役」として存続させ,政治家や官僚は,その悪者をこらしめる「正義の味方」となるという構図で成り立っている。うがった見方かもしれないが,その悪者の役回りは,やがて,東京電力から電力業界全体,さらには都市ガス業界全体にまで広げられたようである。一方で,政治家や官僚は,火の粉を被るおそれがある原子力問題については,深入りせず先送りする姿勢に徹した。このように考えれば,福島第一原発事故後政府が,電力システム改革や都市ガスシステム改革には熱心に取り組みながら,原子力政策については明確な方針を打ち出してこなかった理由が理解できる。熱心に「叩く側」に回ることによって,「叩かれる側」になることを巧妙に回避しようとしてきたのである(誤解が生じないよう付言すれば,筆者は,電力や都市ガスの小売全面自由化それ自体については,きわめて有意義な改革だと評価している)。
結果として,福島第一原発事故後10年が経過したにもかかわらず,原子力政策は漂流したままである。あえて強調するが,次の選挙・次のポストを最重要視する政治家・官僚の視界は,3年先にしか及ばない。しかし,原子力政策を含むエネルギー政策を的確に打ち出すためには,少なくとも30年先を見通す眼力が求められる。このギャップは埋めがたいものがあり,そのため,日本の原子力政策をめぐっては,戦略も司令塔も存在しないという不幸な状況が現出するにいたったのである。
この状況は,菅政権の発足によっても,基本的に変わっていない。菅首相も梶山経産相も,原発のリプレースを避けたままである。リプレースを行わない限り,日本の原子力発電に未来はない。政府がリプレースを回避する方針を変えていない以上,50年以降次々と廃炉に追い込まれる原子力は,「脱炭素の有力な選択肢」にはなりえないのである。
ここで注目したいのは,政府が20年12月に示した2050年の電源構成の参考値において,原子力の比率を,水素・アンモニア火力以外のカーボンフリー火力の比率と一括して,3~4割とした点である。この一括視は,明らかに奇妙である。水素・アンモニア火力を大規模に導入するためには,再生可能エネルギー発電と結びつけて水の電気分解を行い生産するグリーン水素・グリーンアンモニア以外に,CCUS(二酸化炭素回収・利用,貯留)を使って「二酸化炭素フリー」の措置を講じて調達するブルー水素・ブルーアンモニアを大量に活用せざるをえない。一方,「水素・アンモニア火力以外のカーボンフリー火力」とは,CCUSに立脚した火力発電のことである。つまり,「水素・アンモニア火力以外のカーボンフリー火力」と一括されるべきは水素・アンモニア火力であって,原子力ではけっしてない。本来,「再生可能エネルギー」/「水素・アンモニア・CCUSによるカーボンフリー火力」/「原子力」と分類すべきだったにもかかわらず,政府はあえて,「再生可能エネルギー」/「水素・アンモニア火力」/「それ以外のカーボンフリー火力と原子力」という3分割を採用した。もし,「原子力」を単独で取り出していたとすれば,現時点でリプレースを避けている以上,2050年の電源構成に占める原子力の比率が10%以下にとどまる事実を隠すことはできなかったことであろう。政府は,政界,経済界,原子力施設立地自治体などに配慮して,そのような事実が表面化することを避けたかった。水素・アンモニア火力以外のカーボンフリー火力と原子力とを一括するという奇策に出た背景には,このような事情が存在する。
そもそも,「再生可能エネルギーの主力電源化」とは,裏を返せば,「原子力の副次電源化」のことである。リプレースが現時点でも打ち出されていない以上,われわれは,日本における原子力の未来について,きわめて厳しい見方をとらざるをえない。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4221 2026.02.23 ]
-
[No.4210 2026.02.16 ]
-
[No.4179 2026.01.26 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
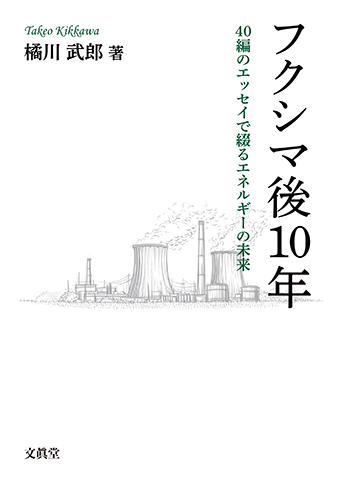 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂
